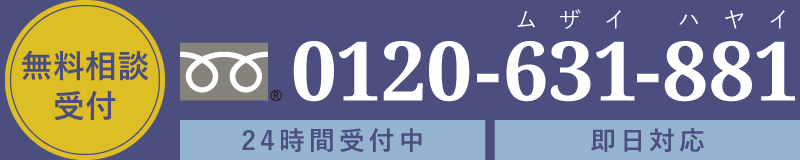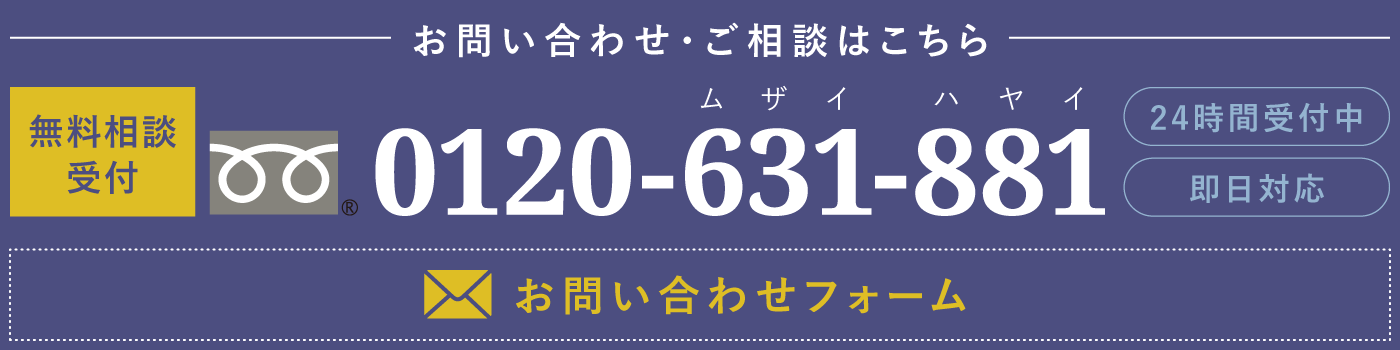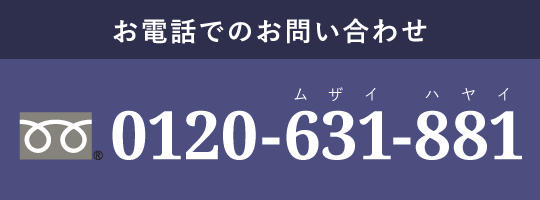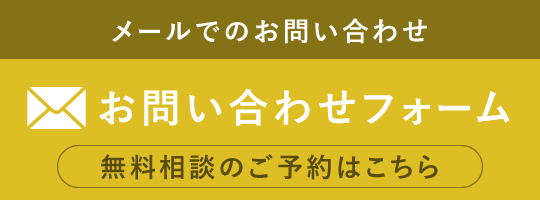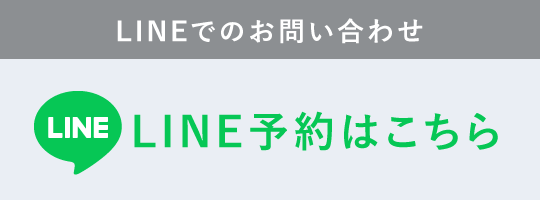このページの目次
所得税法違反で実刑判決を受けた事例を紹介するとともに、実刑判決を避けるためにはどうしたらよいかを弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説していきます。全3回のうち、最終回の今回は、実刑判決を避けるためにはどうすればよいのかを中心に解説します。
実刑判決を避けるために重要な「反省」と「納税」
これまで紹介してきた事例から明らかなように、たとえ所得税の無申告・過少申告による脱税であっても、悪質性が高ければ実刑判決が現実のものとなります。
では、逮捕・起訴されてしまった後に実刑を避ける余地はあるのでしょうか。
絶対ではありませんが、裁判で情状が考慮され執行猶予付き判決(実刑回避)となるためには、以下の点が重視されます。
①速やかな納税措置
起訴後でも遅すぎることはありません。可能な限り早く修正申告を行い、免れた税額や加算税の納付に努めることが肝要です。
実際に、ある事件では被告人が脱税分と重加算税を既に納付済みであることが考慮され、懲役刑に執行猶予が付されたケースもあります。
納税義務の履行は反省の具体的な証左として評価されやすく、「社会復帰後も更生して納税を続ける意思あり」と裁判官に示す効果があります。
②深い反省と再発防止の誓約
被告人自身が犯行を認めているか、法廷でどれだけ真摯に謝罪・反省を述べるかも重要です。
脱税額が高額でも全額を納付し関与を認めて猛省していると裁判所が判断すれば、執行猶予を付して更生の機会を与えることがあります。
逆に「バレないと思った」「他にもやっている人がいる」などと言い訳したり反省が見られなかったりすれば、裁判官の心証は悪化し実刑可能性が高まります。
③初犯かつ社会的更生状況
前科がない初犯であること、家族や雇用主など周囲からの支援が期待でき、更生環境が整っていることも情状として有利に働きます。
一般的に前科がなく反省している初犯者は執行猶予となる場合が多い傾向です。
ただし再犯者や、過去に税務署の指摘で修正申告をしたのにまた隠ぺいを繰り返したようなケース(事例①のように前科猶予中の再犯)は極めて厳しく扱われ、執行猶予は期待しにくくなります。
また、脱税に関する前科ではなく、たとえば薬物に関する前科などであったとしても、初犯の方に比べると厳しい判断が出やすくなります。
さらに、すでに前科の執行猶予が満了しており、かつ、起訴をされた脱税の期間には含まれていなかったとしても、前科の執行猶予中から脱税行為に手を染めていたという内容が裁判で明らかになった場合には、かなり厳しく判断されることになります。
実際に、弊所で担当した脱税事件では、起訴されたのは直近3年間の脱税でしたが、薬物前科執行猶予中であった6年前にも脱税行為に手を染めていたということが考慮されて、実刑判決を受けた事案があります。この事案では、前科がなければ執行猶予が付けられてもおかしくはありませんでした。
弁護活動としては、上記の点を踏まえて被告人の反省文提出、税務当局との交渉による納税の実施、再発防止策の準備(税理士をつけ修正申告や納税をする誓約等)、家族の監督誓約書の提出などが考えられます。
実際、裁判例を見ても脱税額そのものだけでなく「犯行後にどう対応したか」が量刑に反映されています。巧妙な無申告による所得隠しであっても追徴税を完納したことで執行猶予となっている例もあります。
まとめ
無申告・過少申告による脱税は、「うっかりミス」では済まされない重大な犯罪です。
判決年月日や裁判所名は異なれど、紹介した事例はいずれも悪質な税逃れに対し裁判所が毅然とした態度で臨んだものです。
逮捕された被疑者本人やご家族にとっては大変な精神的負担でしょうが、まずは事実関係を認めた上で専門家(弁護士・税理士)の力を借り、一日も早く適正な納税と再発防止策を講じることが肝要です。
それが結果的に情状酌量につながり、執行猶予獲得や刑の減軽につながる可能性があります。
判決が出るまでのプロセスは苦難ですが、適切な対応次第でその後の人生を立て直す余地は残されています。
「逃れ得た税より失うものの方が大きい」――本記事の事例が示す教訓を胸に、真摯な反省と更生への努力を続けることが何より重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、所得税法違反で告発された方など、刑事裁判になりそうで不安な方の相談を随時受け付けています。
初回のご相談は無料ですので、不安な方は一度弊所までお電話下さい。