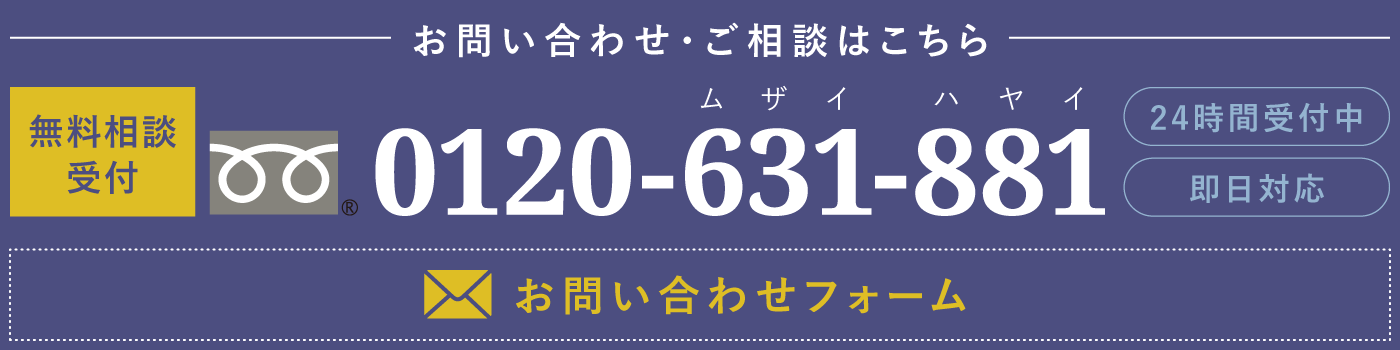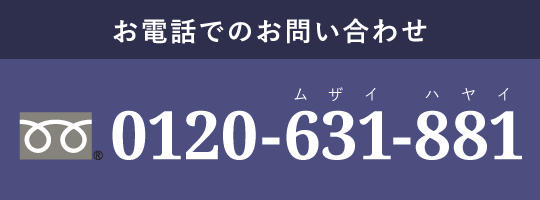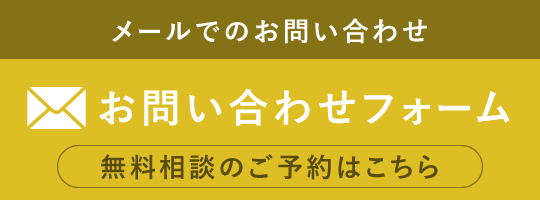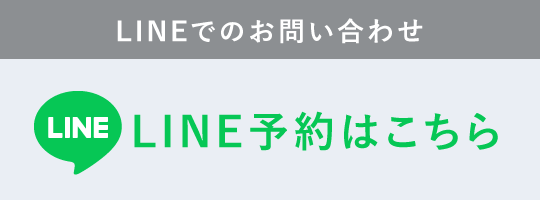Archive for the ‘所得税・法人税’ Category
【裁判例解説】無利息で貸し付けたのに収益が発生?

無利息で貸付を行った際にも、利息相当額の収益を計上しなければならないかが争点となった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
1 事例
株式会社X(以下、「X社」といいます。)は、子会社である株式会社T(以下、「T社」といいます。)に対し、その事業達成を援助する目的で、期間を3か年に限り、4000万円を限度として、「無利息」で融資する契約を締結しました。
そして、X社は、この契約に基づき、T社に対して、○年度において、2000万円を融資しました。
これに対し、税務署長Yは、X社の融資について、通常当事者間で行われる融資における利率による利息相当額を収益として計上する旨の更正処分をしました。
(なお、事例につきましては、実際の裁判例を若干修正、簡略化しています。)
2 争点~法人税法22条2項
法人税法21条1項において、法人の「各事業年度の所得の金額」は、「当該事業年度の益金の額」-「当該事業年度の損金の額」とされています。
その上で、同条2項において、益金の額に算入すべき金額には、「無償による資産の譲渡又は役務の提供」により生じた収益を含むとしています。
こうした法律からすれば、X社のT社に対する融資は、無償による役務の提供として、利息相当額の収益が発生しているものとも考えることができることから問題となりました。
なお、現在、この点については、平成30年に法人税法が改正され、22条の2が設けられ、法律上の解決がなされていますが、この後紹介する裁判例は、またそのような規定がない頃の判断です。
3 裁判所の見解について
この点が問題となった大阪高裁昭和53年3月30日判決(判時925号51頁)は、X社が行ったのが無利息の融資であったとしても、X社には、通常、当事者間で行われる利息相当額の収益があり、その分を計上する必要があるとしました。
その上で、X社のそうした収益は、X社がT社に無償で給付(すなわち寄付)したであるとし、法人税法37条1、7項により、一定限度を超える寄付については損金計上できないとしました。
実際の判決文は、次のとおりです。
「資産の無償譲渡、役務の無償提供は、実質的にみた場合、資産の有償譲渡、役務の有償提供によって得た代償を無償で給付したのと同じである」とした上で、「営利法人が金銭(元本)を無利息の約定で他に貸付けた場合には、借主からこれと対価的意義を有するものと認められる経済的利益の供与を受けているか、あるいは、他に当該営利法人がこれを受けることなく右果実相当額の利益を手離すことを首肯するに足りる何らかの合理的な経済目的その他の事情が存する場合でないかぎり、当該貸付がなされる場合にその当事者間で通常ありうべき利率による金銭相当額の経済的利益が借主に移転したものとして顕在化したといいうるのであり、右利率による金銭相当額の経済的利益が無償で借主に提供されたものとしてこれが当該法人の収益として認識される」。
4 現在の法律―法人税法22条の2第4項
先ほども少し触れましたが、現在は、法人の資産の販売・譲渡、役務の提供において、原則として、その販売・譲渡をした資産の引渡時の価額、その提供した役務について通常得るべき対価の額に相当する金額を収益とするという法律が設けられています(法人税法22条の2第4項)。
5 予想される問題点・弁護活動
以上のような裁判例、法人税法22条の2第4項の規定からすれば、たとえば、無償で第三者に会社の資産を譲った場合においても、その資産の引渡時の価格を収益として計上する必要があることになり、これを怠ると、法人税法違反(場合によっては消費税法違反も)となります。
こうしたことは、税務調査の場面で問題になることが考えられますし、他にも脱税をしており、査察を受けている場面でも問題になることも考えられます。
もっとも、大阪高裁が指摘するように、①対価的意義を有する経済的利益の供与を受けていたり、②対価を受けることがなく利益を手離すことに合理的な経済目的がある場合には、収益として計上する必要がないという解釈も可能です。
そこで、こうした点が問題になった場合には、弁護士に的確なアドバイスを受け、仮に収益として計上する必要がある場合には、その旨の修正申告をするといったことが考えられます。
5 最後に
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、脱税事件に強い弁護士が所属し、法人税法違反など多数の事件を取り扱っています。法人税法違反の疑いがあるとして税務調査を受けた方は、初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
【制度解説】青色申告制度

青色申告制度について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
1 青色申告とは
青色申告とは、税務署長の承認を受けて、青色の申告書を用いて行う納税申告のことをいいます。
各事業年度の所得に対する法人税や不動産所得・事業所得または山林所得を生ずる業務を行う個人の所得税などについて認められています。
青色申告は、帳簿書類を基礎とした正確な申告を勧めるための制度であり、青色申告を行うことに対する特典が用意されています。
2 青色申告における特典
青色申告を行うことによって享受できる特典には、次のようなものがあります。
青色申告を行った者に対しては、青色申告特別控除という制度が設けられており、簡単にいえば、支払うべき税金を減らすことができます。
また、所得税法・法人税法および租税特別措置法の規定の多くは、青色申告の場合に限って適用されることになっています。
こうしたことと同様に、青色申告と白色申告(通常の納税申告)を通じて適用される措置についても、青色申告を行った者により多くの利益が与えられているものもあります。
つまり、青色申告を行った者だけが税制上の優遇措置を受けることができるとされています。
その他、青色申告に対し、更正(間違った申告内容を正すことです)が行われる場合、推計によって行うことができないといった違いもあります。
3 青色申告を行うためには
先ほども少し説明しましたが、青色申告を行うためには所轄税務署長の承認を受ける必要があります。
この承認を受けようとする者は、一定の事項を記載した申告書を税務署長に提出する必要があります。
4 青色申告の承認の取消し
青色申告を行うために上記の承認を得たとしても、一定の事実が存在する場合には、税務署長は、その承認を取り消すことができるとされています(所得税法150条1項、法人税法127条1項)。
その一定の事実とは、
①その年における帳簿書類の備え付け、記録または保存が財務省令で定めることころ、または電子帳簿保存法の関係規定にかかる財務省令で定めるところによって行われていないこと
②その年における帳簿書類について税務署長の指示に従わなかったこと
③その年における帳簿書類に取引の全部または一部を隠蔽しまたは仮想して記載・記録し、その他その記載・記録事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること
④確定申告書をその提出期限までに提出しなかったこと
⑤連結納税の承認取消(④、⑤については法人税法のみ)
が挙げられます。
なお、現金売上の一部等を除外した帳簿書類を作成した上で内容虚偽の青色申告書を提出し、法定納期限までに納付すべき税の一部を納付しなかった場合において、青色申告承認処分が過去に遡って取り消され、先ほど説明した特典がなかったもの(たとえば、青色申告控除が受けられなくなるなど)として、その分についても納付すべき税額に含まれるかが問題となった事案において、判例は、その部分についても納付すべき税額に含まれるとしています(最高裁昭和49年9月20日判決・刑集28巻6号291頁)。
過去に遡って、その分の税金を納める必要があるとすれば、その金額は高額になる可能性も十分あります。
税務調査を受け、結局、青色申告の承認が取り消される可能性が出てしまった場合には、少しでも負担を減らすことができる道を模索する必要があります。
また、税務調査の結果、脱税しているとされた場合、その金額などのよっては、刑事責任を問われる可能性も出てきます。
5 最後に
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、脱税事件に強い弁護士が所属し、所得税法違反、法人税法違反など多数の事件を取り扱っています。税務調査を受けた方は、初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
所得税における所得の帰属について

所得税において所得が誰に帰属するか、すなわち所得の人的帰属の問題について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
実質所得者課税の原則
所得の帰属とは、ある所得があった場合にそれを誰に帰属すべきかという問題です。
所得税における所得の帰属について、所得税法12条に、実質所得者課税の原則と呼ばれる規定が置かれており、「資産又は事業から生じる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律を適用する」としています(なお、法人税法11条、消費税法13条にも同様の規定があります。)。
たとえば、その仕事の性質上、名義人の名義を借りて仕事をしている場合には、その名義を貸した名義人ではなく、借りた名義を利用して仕事をし、その利益を得ている人が申告、納税をする必要があることになります。
この規定の理解の仕方(解釈)には2つの見解がある
まず1つの考え方は、所得税法12条は、単なる名義人と法律上の真の所有者がいる場合に、法律上の真の所有者に課税することを定めたものと解する立場です。この考え方は、法律上の形式と法律上の実質を区別し、実質に即して帰属を判定すべきであるというものであり、法的帰属説といわれます。真の法律関係を明確にすべきことは、税法の場合に限らず全ての法領域において当然の要求ですから、この考え方によれば、実質所得者課税というのは税法独自の原則ではなく、当然のことを規定した確認規定ということになります。
もう1つの考え方は、所得税法12条は、法律上の所有権者と経済上「収益を享受する」者とがいる場合に、経済上「収益を享受する」者に課税することを定めたものと解する立場です。この考え方は、所得の法律上の帰属と経済上の帰属を区別し、経済上の帰属という面に着目して帰属を判定すべきであるというものであり、経済的帰属説といわれます。したがって、実質所得者課税の原則は、税法固有の原則であるということになります。
条文上はいずれの解釈も可能です。しかし、法的実質と経済的実質が異なる場合とは具体的にどのようなケースであるのか必ずしも明確ではありません。私法上の法律関係に応じて課税関係が決まる方が納税者の予測可能性が高まること等から、法的帰属説の考え方が通説とされています。
事業から得られる所得の帰属について
所得税基本通達12-2は、「事業主から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その事業を経営していると認められる者(「事業主」という。)がだれであるかにより判定するものとする。」と規定しており、事業から得られる収益は、基本的にはその事業の事業主(事業を経営している者)に帰属すると考えられますいます。)。法的帰属説の立場からは、「事業主」とは、法律的な意味でその事業を実質的に経営している者(経営主体)だということになります。
しかしながら、事業主が誰かの判断は必ずしも容易なことではありません。特に親族による家族経営の場合の事業主の判定には困難が伴います。そのため、課税実務においては、通達でいくつかの判断基準が規定されています。
所得税基本通達12-5によると、生計を一にする親族間における事業(農業を除く)の事業主がだれであるかの判定は、まず、その事業の経営方針の決定につき支配的影響力を有すると認められる者を事業の事業主と推定します。
次に、誰がその事業の経営方針決定につき支配的影響力を持つ者か明らかでないときは、原則として、「生計を主宰している者」が事業主と推定します。
この点は、判例があり、歯科医師の親子が親の歯科医院でともに診療に従事していた場合の事業主の判断が争われた事案(親子歯科医師事件)において、裁判所は、ある事業による収入はその経営主体であるものに帰したものと解すべきとした上で、従来父親が単独で経営していた事業に新たにその子が加わった場合においては、特段の事情のない限り、父親が経営主体で子は単なる従業員としてその支配に入ったものと解するのが相当であるなどとして、医院の経営に支配的影響力を有しているのは父であり、その経営による本件収入は経営主体である父に帰すると判断しています(東京高判平成3年6月6日訴月38巻5号878頁)。この判決も上記通達と同様の考え方に立つものと考えられます。
最後に
誰に課税されるのかという判断を間違うと、課税されるべき人の確定申告が間違いであったということになり、過少申告加算税などのペナルティを受ける可能性があります。所得の帰属について迷った場合には、税理士ないし弁護士等の専門家に早めに相談しましょう。(課税処分に納得ができない場合には、こちらの記事も参照してください。https://datsuzei-bengoshi.com/fufukumousitate/)
確定申告をしなかったことが重大な犯罪になる場合とは

確定申告を怠った場合の刑事責任について、事例を参考に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
1 事例
一人親方として、内装工事などを行っていたAさんは、売上の管理を怠っていたため、売上を、自身の名義の口座に入れてもらう場合もあれば、妻であるBさんの口座に入れてもらうようにしていました。
Aさんは、開業以来、自身の名義の口座に入った分のみについて確定申告を行ってきましたが、次第に、申告して納付するのは馬鹿馬鹿しいと考えるようになり、令和○年分は確定申告をしませんでした。
2 確定申告をしないとどうなる?
所得税の納税義務は期間の経過によって成立し、一定の確定手続を経て納付すべき税額が確定します。
納付すべき税額を確定させる手続が確定申告と呼ばれるものです(所得税法120条1項)。
会社員のように源泉徴収される人は、その収入のみであれば確定申告を行う必要はありません。
しかし、今回の事例のような個人事業主として収入を得ている人や、会社員であっても副業や投資などで収入があった人については、確定申告を行う必要があります。
正当な理由がなく確定申告を行わない人については、単純不申告罪として、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処するとされています(所得税法241条本文)。
また、故意に確定申告書等を提出しないことにより租税を免れた場合、単純不申告逋脱(ほだつ)罪として、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金(または罰金を併科)に処するとされています(所得税法238条3、4項)。
3 Aさんはさらに重い罪に問われる?
ところが、Aさんのような人が、上記の犯罪ではなく、(狭い意味での)逋脱罪(以下、単純に「逋脱罪」というときは、狭い意味での逋脱罪をいいます。)とされた事例があります。
この場合の法定刑は、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金(または罰金を併科)とされています(所得税法238条1項)。
逋脱罪とは、「偽りその他不正の行為により」、所得税を免れた場合をいいます。
「偽りその他不正の行為」とは、逋脱の意図をもって、その手段として税の賦課徴収を不能もしくは著しく困難ならしめるようななんらかの偽計その他の工作を行うことをいいます。
そうすると、Aさんは、売上の一部を妻名義の口座に入れてもらっていたにすぎず、税の賦課徴収を不能もしくは著しく困難ならしめるようななんらかの偽計その他の工作を行ったとはいえないようにも思われます。
しかし、判例は、売上を帳簿に正確に記載していたところ、その一部を仮名・借名の預金口座に入金保管した事例で、逋脱罪の成立を認めました(最高裁平成6年9月13日決定・刑集48巻6号289頁)。
この決定では、「仮名又は借名の預金口座に売上金の一部を入金保管することは、税務当局による所得の把握を困難にさせるものであることに変わりはなく、ほ脱の意思に出たものと認められる以上、所得秘匿工作に当たる」としています。
4 予想される問題点・弁護活動
ここで注意すべきなのは、売上を仮名や借名の預金口座にて入金管理していたことで直ちに逋脱罪に該当するわけではないと考えられることです。
当然ですが、たまたま手違いでそうした預金口座に入金されていたということであれば、逋脱罪が成立しない可能性もあり、結局はケースバイケースと言わざるを得ません。
Aさんは、税務調査や査察を受け、さらには検察官へ告発されるということが考えられます。
そうした手続の中で、税務署、国税庁、検察庁にどのように説明していくかというのは非常に重要になり、弁護士によるアドバイスを事前に聞いて、そうした調査などに対応していく必要があります。
5 最後に
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、脱税事件に強い弁護士が所属し、所得税法違反など多数の事件を取り扱っています。所得法違反の疑いがあるとして税務調査を受けた方は、初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
脱税事件における刑事手続の特徴

脱税で刑事事件化した場合の特色や、刑事裁判において減刑を求めるうえで有利になる事情について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
脱税に関する罰則規定
法律上、正式な定義があるわけではありませんが、脱税とは、不正の目的をもって払うべき税金の納付を免れたり、本来受けられない還付を受けたりすることを指します。
それゆえ、脱税を行った場合、法人税法や所得税法といった、各種税法に違反していることになります。法人税を例に挙げると、架空の経費計上のように、虚偽の申告内容によって納税を免れた場合(虚偽過少申告ほ脱犯)は、「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と罰則が規定されています(法人税法159条1項)。税法ごとの罰則については、こちらの記事もご参照ください。https://datsuzei-bengoshi.com/datuzei_syurui/
脱税と刑事事件の関係
もっとも、あらゆる脱税が刑事事件として扱われるわけではありません。脱税事件として刑事事件化するのは、国税局によって検察庁に告発された場合です。税務署による税務調査や、国税局による査察調査を実施した場合でも、検察庁への告発がされなければ、刑事事件にはなりません。
脱税の金額や手法によっては、各調査を行ったうえで、修正申告を促されて終わりということもあります。このように,脱税を行ってしまった場合でも、必ずしも刑事事件化するわけではありません。
脱税事件における刑事裁判の特徴
検察庁に告発されてしまうと、通常の刑事事件と同様に、逮捕や勾留といった身体拘束や、取調べが行われることになります。
告発を受けても起訴されない場合はありますが、ひとたび起訴されてしまうと、ほぼ例外なく有罪になってしまうのが脱税事件における刑事裁判の特徴です。検察官が起訴できる事件を選別しているため、通常の刑事裁判でも有罪率は高いですが、脱税事件ではその傾向がより顕著になります。
国税局による令和4年度の発表資料においても、一審判決すべてに有罪が言い渡されており、有罪率は100パーセントになっています。
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2023/sasatsu/r04_sasatsu.pdf
すなわち、脱税事件で検察庁に起訴されてしまうと,個人については懲役刑が,法人に対しては罰金刑が必ず科せられることになります。
脱税事件の刑事裁判で有利になる事情
懲役刑に執行猶予がつかなければ、刑務所へ服役することになります。また、脱税事件では高額な罰金も科せられます。そのため、服役の回避や罰金の減額を求めるためにも、脱税事件において裁判所に考慮される有利な事情(情状)が何かを把握しておくことは、極めて重要になってきます。
脱税事件の刑事裁判において、実際に裁判所が判決理由の中で有利な事情として言及したものとしては、以下のような事情があります。まず、脱税以外の通常の刑事事件とも共通する事情としては、事実を認めて反省していることや、前科がないこと、個人については監督者の存在があることなどが挙げられます。
脱税事件に特有の事情としては、告発後の取調べといった捜査のみならず、それ以前に行われた税務調査の段階で積極的に協力したことも、有利な事情として考慮されています。
再犯防止の観点からは、経営体制の改善も有利な事情となります。具体的には、脱税に関与した者が役員を辞して代表者を刷新したこと、外部から顧問や監査役、監査法人を招くといった事情が考慮されます。
脱税は国の課税権を侵害するという意味では財産犯でもあるため、事後的な被害(損害)の回復、すなわち、修正申告を行うことで本税や重加算税などの各種附帯税を納付したことも有利な事情とされます。なお、判決の時点で納付が完了していなくても、納税のための資金を準備していることも考慮されています。
このように、脱税の刑事裁判において有利に考慮される事情は、ある程度の類型化はできます。もっとも、具体的な刑事裁判においてどのような判決が見通されるか不安な場合は、弁護士に相談することが重要です。早期に相談を行えば、刑事事件化に至る前に解決が図られるケースもあります。脱税をしてしまってお悩みの場合は、まずは弁護士にご相談ください。
ネットオークションと課税

ネットオークションを利用して利益を得た場合、課税対象となるでしょうか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
C社に勤める会社員Aさんは、古本屋で安く買った本を、自分で読むのではなく、ネットオークションで高く売ることを繰り返していました。Aさんとしては、小遣い稼ぎのつもりでしたが、気が付けば年間で30万円を超える儲けが出ていました。Aさんは、この金を遊興費等に費消しましたが、確定申告は必要ないと考えてしていませんでした。
(フィクションです)
解説
基本的に、どのような手段であれ、個人でお金を得る行為を行うと、課税対象となります。そのため、ヤフオクなどネットオークションに出品・売却して売り上げたお金は課税対象であり、確定申告が必要となるのが原則です。
しかし、実際にはすべての売買に対して確定申告が必要とされるわけではありません。
生活用動産に該当するものを売却した場合は、所得税法上、非課税となり確定申告は必要ない
この生活用動産とは、普段の日常生活で使っている物品のことを指します。生活用動産となるものは、具体的には、日常的に使っていた衣服や家具、家電などが該当します。また、書籍など、生活必需品とまではいえないものでも、生活用動産に該当し得ます。
ただ、本事例のAさんは、転売目的で古本屋から本を購入しており、この生活用動産の売却には当たらないと考えられます。
Aさんがネットオークションによって利益を得た場合、確定申告をしなければならないのは具体的にどのような場合か
この点、Aさんは、C社に勤める会社員であり、給与所得者です。所得税法上、給与所得者の場合は、1か所からの給与所得を受け、給与所得以外の所得が年間で20万円以下であれば、原則として確定申告の義務はありません。これは、給与所得者の場合は、確定申告に代わる年末調整という手続きにより、給与所得にかかる税額は確定しているからです。しかし、本事例のAさんのように、給与所得以外の副収入等によって年間で20万円を超える所得を得ている場合には、確定申告が必要となります。
このように、給与所得が片手間でオークション売買を行っている場合、年間の儲けが20万円以下であれば、確定申告をしなくてもよいことにはなっていますが、いつ20万円を超えるとも限りませんから、平素から売買の記録をつける習慣をつけておくべきでしょう。
ネットオークションによってAさんが得た利益は、所得税法上、どの所得に該当するか
給与所得者の副収入ということを前提とすれば、Aさんが得た利益は、雑所得に該当すると考えられ、雑所得として確定申告をしなければなりません。所得の金額を計算する際は、収入金額から経費を差し引いてその所得金額を求めます。収入金額とは、1年間に商品を売却して得た金額です。基本的には、ネットオークションに出品した商品が売れた場合、その売却代金が収入金額となります。
Aさんは今後どうなるか
ネット上の話なので、税務署に発覚することはないと思っているかもしれませんが、実際はそうではないことを知っておくべきです。取引履歴についても、照会をかけて調べることは簡単であり、ヤフオクなどネットオークションでの取引状況は、税務署に発覚しやすいといえます。
Aさんはネットオークションによって得た利益について確定申告をしていないので、税金の問題があり、税務署に把握されれば、無申告についてのペナルティを別途受ける可能性があります。
また、仮装隠ぺいなど悪質性が高いと判断された場合には、無申告加算税に代えて重加算税が課せられます。
さらに、納税が遅れると、その期間に応じた「延滞税」の支払いが求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を中心として扱っていますが、税法についても知識のある弁護士がそろっています。初回の相談は無料ですので、一度ご相談にお越しください。
FX取引と査察調査 無申告のままだと脱税事件に

FX取引によって得た利益と課税の関係や、無申告で脱税事件となってしまった場合の手続の流れや対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
Aさんは本業とは別にFX取引を行い、多額の利益を上げていました。しかし、AさんはFX取引で得た所得の申告をまったく行わず、3000万円以上の所得税の納付を免れていました。Aさんの脱税は国税局の査察調査によって発覚し、最終的に国税局は所得税法違反の疑いでAさんを検察庁に告発しました。
(この参考事件はフィクションです。)
FX取引とは
FXとはForeign Exchangeの略称で、外国為替証拠金取引と呼ばれています。名前のとおり、特定の国の通貨を別の国の通貨に交換することを意味します。外貨の売買で差益を得ることがその目的になります。
FXの最大の特徴は、取引額の一部に相当する証拠金(保証金)を預けるだけで、その何十倍もの額で取引が行えることです。レバレッジと呼ばれるこの特徴によって、少額でも多額の取引を行うことも可能になります。
レバレッジの仕組みを有効に活用すれば、少額の元手から取引を始めて、多額の利益を得ることも考えられます。
FX取引と課税の関係
FX取引によって得た利益は、先物取引に係る雑所得等として扱われ、所得税が課せられます(国税庁のホームページでもFX取引の定義や課税関係について紹介しています。詳細は以下のリンク先をご覧ください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1521.htm)。
そのため、副業による収入だからと申告を怠っていると、参考事件のAさんのように、脱税事件として刑事告発されてしまうおそれがあります。FX取引では、レバレッジにより証拠金以上の多額の損失が生じるリスクが問題視されることもありますが、反対に多額の利益を得た場合も、無申告のままでは脱税事件になってしまうため、注意が必要です。
脱税事件となってしまった場合
脱税の疑いが生じた場合、通常は税務署による税務調査が行われますが、ケースによっては証拠隠滅などを防ぐために、最初から国税局による査察調査が入ることもあります。脱税事件の流れについては、こちらの記事もご参照ください。
https://datsuzei-bengoshi.com/datuzei_nagare/
脱税額が多額にわたる、脱税に用いた手法が悪質といった事情がある場合、査察調査を行った国税局から検察庁に刑事告発がされることになります。参考事件のAさんのように、3000万円以上の所得税納付を免れたとなると、刑事告発されてしまうリスクが極めて高くなります。
国税局による告発がされてしまうと刑事事件となってしまうため、逮捕や勾留によって長期間の身体拘束を伴うことも考えられます。検察庁に起訴された場合、刑事裁判も受けなければなりません。
ひとたび脱税事件を起こしてしまうと、本来払うべき本税の他に、加算税や延滞税なども支払うことになります。これに加えて、刑事裁判になった場合は、同じく高額にわたることもある罰金まで支払う必要に迫られます。
このように、FX取引による所得を申告しなかった場合、一時的に利益は得られたとしても、最終的には脱税した額以上の損失を被ることになります。令和4年の国税庁の発表でも、FX取引によって得た所得を申告していなかったことで、告発からの刑事裁判になったケースが紹介されています。詳細は以下のリンクをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/release/r04/sasatsu/sasatsu.pdf
早期に弁護士への相談を
脱税を行ってしまった場合は、税理士による修正申告を行っていくことになります。もっとも、国税局によって告発がされた場合は刑事事件となるため、税理士だけでなく弁護士によるサポートが欠かせなくなります。査察調査以前の税務調査の段階であっても、後々に刑事告発や起訴のリスクがあり得る場合は、早期に弁護士にも相談をしておくことが肝要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の対応に注力してきた経験・実績を活かし、脱税事件における弁護対応も行っています。FX取引によって利益が出たものの、申告を怠ってしまった場合は、速やかに弊所にご相談ください。
不法な利益も「収益」となる

不法な利益を得ていた会社における問題について、事例を参考に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
1 事例
東京都にある会社X社は、金銭貸付等を事業を営んでいたところ、利息制限法の制限を超える利率で貸付を行っていました。
X社は、令和○年分の確定申告において、その年に回収した利息分のうち、利息制限法の制限を超える部分については、法律上無効なものであるから、収益として計上しなかったところ、税務調査を受けることになりました。
2 前提として―利息制限法
業者が金銭を貸し付ける際、利息を付けるのが通常です。利息制限法は、その利息が、不当に高いものとならないよう、一定の制限を設けています。たとえば、100万円以上の金銭を貸し付ける場合、年15%を超える利息については、無効とされ(利息制限法1条各号)、利息制限法を超える部分の返済は、残存元金に充当されます。
3 収益の意義
法人(ここでは日本国内に本店または主たる事務所がある法人を前提とします。)は、「当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額」など一定の事項を記載した申告書を提出する必要があります(法人税法74条)。確定申告と呼ばれるものです。
法人の各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額から同年度の損金の額を控除した金額とされています(同法22条1項)。
そして、法人税法22条2項において、益金の額に算入すべき収益は、「資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益」とされています。
紹介した事例においては、法律上無効な取決めに基づいて回収した利息が収益に該当するかが問題となります。
この点、判例は、回収した利息のうち、利息制限法所定の制限を超えた部分についても、収益に該当するものとしています(最判昭和46年11月16日刑集25巻8号938頁)。
よって、X社が、その年に回収した利息分のうち、利息制限法の制限を超える部分について収益として計上しなかったことについては、法人税を免れたものにあたり、その法人の代表者などは、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金(または罰金を併科)とされます(法人税法159条1項)。
4 法人税違反における弁護活動
X社は、税務調査を受けている段階ですので、早期に、修正申告をするということが考えられます。
修正申告は、たとえば会社に顧問の税理士がいる場合には、その税理士に行ってもらうことになりますが、法解釈について、弁護士のアドバイスを要することも考えられます。
特に、紹介した事例とは異なり、不法・違法な仕事によって収益を得る事案というのは、他にも様々なものが考えられ、収益として計上すべきかどうかということを慎重に判断する必要がある場合もあります。
また、顧問の税理士がいない場合にも、税務調査における対応や修正申告を取り扱っている税理士を探す必要があります。
税務調査の結果、法人税の過少申告だと発覚した際には、税務署長などが正しい税金の額を納めるよう命ずることになります(更正処分など)。
もっともそれにとどまらず、免れた法人税の額や行為態様、期間などによっては、税務調査にとどまらず、刑事事件に発展する場合もあります。そうしたことが予想される場合には、脱税事件の経験のある弁護士に、早期に相談する必要があります。
5 最後に
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、脱税事件に強い弁護士が所属し、法人税法違反など多数の事件を取り扱っています。法人税法違反の疑いがあるとして税務調査を受けた方は、初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
業務上横領と課税
業務上横領によって得た利益についても課税対象となるでしょうか?犯罪行為によって得た利益に対する課税について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
福岡県福岡市にある会社で経理を担当していたAさんは、会社のために保管していた現金を着服し、1年間で合計4500万円ほど横領していました。
会社の売り上げと決算書の内容に不審な点があることから、会社に福岡国税局資料調査課から税務調査が入り、Aさんの業務上横領が発覚しました。
今後のことが不安になったAさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談を利用することにしました。
(フィクションです)
解説
業務上横領によって得た利益は所得税の課税対象となるか
業務上横領によって得た利益は、違法な行為によって得た利益といえるため、所得と言えるでしょうか。
この点について、所得税基本通達36-1は、「法第36条1項に規定する『収入金額とすべき金額』又は『総収入金額に算入すべき金額』は、その収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わない」と規定しています。
したがって、本件のAさんが業務上横領によって得た利益についても所得として確定申告をする必要があるということになります。
一時所得か雑所得か
次にAさんが業務上横領によって得た利益が、「一時所得」なのか「雑所得」なのかが、税額を計算するベースとなる「課税所得金額」に大きな差がでるため問題となります。
①一時所得の場合
(一時所得の金額-必要経費-特別控除額)×2分の1=一時所得の課税所得金額
という計算式で求めます。
本件のAさんの場合、(4500万-0円-50万)÷2=2225万円となり、2225万円が一時所得の課税所得金額となります。
※一時所得の金額から経費を差し引いた金額が50万円以上の場合、特別控除額は50万円
Aさんに他に収入がない場合には、総所得金額も2225万円となるため、所得税の税率は40%となります。
また、この場合の所得税の控除額は279万6000円です。
そのため、Aさんに課税される所得税は2225万×0.4-279万6000円=610万4000円となります。
②雑所得の場合
雑所得の金額-必要経費=雑所得の課税所得金額
という計算式で求めます。
本件のAさんの場合、4500万-0円=4500万円となり、4500万円が課税所得金額となります。
4000万円を超えている場合の所得税の税率は45%、控除額は479万6000円です。
そのため、Aさんに課税される所得税は4500万×0.45-479万6000円=1545万4000円となります。
このように、一時所得か雑所得かでは、所得税の額に2倍以上の差が出てしまうことになります。
では、本件のAさんの場合には一時所得と雑所得のいずれに当たる可能性が高いでしょうか。
この点について、最高裁は「所得税法上、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得および譲渡所得以外の所得で、営利を目的とする継続的行為から生じた所得は、一時所得ではなく雑所得に区分されるところ、営利を目的とする継続的行為から生じた所得であるか否かは、文理に照らし、行為の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判断するのが相当である」と判示しています(最判平成29年12月15日)。
そのため、一時所得か雑所得かの区別は、ほかの8種類の所得に当たらないことを前提として、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」といえるか否かが主な基準となっているということができるでしょう。
本件のAさんの場合には、1度に4500万円を着服したのであれば、継続的行為とは明らかにいえないので、一時所得に当たるということになるでしょう。
一方、何回かに分けて着服していた場合には、行為の期間や回数、頻度そのほかの態様など判例が示している考慮要素をもとに判断していくことになり、一概にどちらに当たるということは難しいといえます。
一時所得に当たるのか否かについては、このように様々な考慮要素をもとに判断していくことになるため、一度専門家に相談してみるのがよいでしょう。
Aさんは今後どうなるか
Aさんは、会社のお金を業務上横領しているため、会社が警察などの捜査機関に被害届の提出や告訴をすれば、業務上横領の被疑者として取り調べを受けたり、刑事裁判で有罪の判決を受けて前科が付く可能性があります。
業務上横領の金額が多額ですので、会社と示談ができなければ実刑となる可能性が高いといえるでしょう。
一方、会社が被害届の提出など刑事事件化をしなかったとしても、会社から業務上横領によって失われた利益を返還するよう、損害賠償請求をされる可能性もあります。
このような会社との関係とは別に、Aさんは業務上横領によって得た利益について確定申告をしていないはずなので、無申告又過少申告についてのペナルティを別途受ける可能性があります。
確定申告期限内に一切の所得について確定申告がなされていなかった場合には無申告加算税、一部だけしか確定申告をしていなかった場合には、過少申告加算税がペナルティとして課されます。
また、仮装隠ぺいなど悪質性が高いと判断された場合には、無申告加算税又は過少申告加算税に代えて重加算税が課せられます。
さらに、納税が遅れると、その期間に応じた「延滞税」の支払いが求められます。
このほか、Aさんの場合には、税務調査が入っていますが、悪質性が高かったり脱税額が巨額になる場合には、査察調査に発展することもあります。
査察調査は財務調査と違い、強制的に調査をすることができ、最終的には刑事告発に至る場合が少なくありません。実際、査察調査から刑事告発される割合は約70%と言われています。
まとめ
Aさんのように犯罪によって得られた利益も課税対象になりますので、確定申告をしていなければ、業務上横領の罪とは別に所得税法違反など税法違反の罪にも問われてしまう可能性があります。
そのため、犯罪行為によって利益を得ている場合には、その犯罪だけではなく税金の問題についても考慮しておく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を中心として扱っていますが、税法についても知識のある弁護士がそろっています。
初回の相談は無料ですので、一度ご相談にお越しください。
金密輸が発覚すると厳しい処罰も
金密輸について、発覚するとどのような処罰が考えられるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
1.金密輸に関係する犯罪
金密輸の事例としては、東南アジアなどで金を買い付け、日本に持ち帰って買い取り業者に売るというものがあります。
海外で購入したものを日本に持ち帰ることは輸入に当たるといえますが、金を日本に持ち帰る場合には、注意が必要です。
①重量が1キログラムを超える金の地金(純度90%以上)又は②ほかのお土産と合わせて20万円を超える金の地金を携帯輸入する場合には、事前に税関で申告する必要があります。
このような場合に、無申告で日本に持ち帰ると、「関税法違反」として処罰の対象となります。
関税法違反となる場合には、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金またはその両方の刑罰が科せられる可能性があります。
また、日本で売買することによって得た利益については、所得となります。
この場合に問題となるのは、消費税法、所得税法、地方税法です。
金を売った利益が所得となるため、所得税や住民税の確定申告が必要になりますし、売った場合には消費税の納税義務も生じます。
そのため、確定申告をしていなかったり、消費税の納付をしていない場合には、消費税法違反や所得税法違反、地方税法違反という罪に問われてしまう可能性があります。
この場合の罰則は、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその併科となっています。
2.手続きの流れ
金の密輸が疑われる場合、税関から通報され警察の捜査が開始されることもありますが、税務調査によって発覚する場合もあります。
税務調査は、所得隠しの疑いがあったりする場合に、確定申告の内容が適切かどうかを見極めるために行われるもので、任意調査です。
しかし、この税務調査で所得隠しが明るみになり、意図的に所得を隠していて悪質性が高かったり、無申告にかかる税額が多額に上ったりした場合には、国税局の査察調査を受けることになります。
査察調査は、強制調査として行われ、刑事告発を視野に行われます。
国税局査察部が会社などに立ち入り、必要な資料などを強制的に押収して聴き取り調査などを行います。
その後、刑事告発するかどうかが検討され、刑事告発すべきとなった場合には、検察庁に対して告発がなされ、以後は刑事事件として捜査を受けることになります。
多くの場合には逮捕されて捜査を受けることになり、その後刑事裁判を受けることになります。
刑事裁判では、有罪無罪のほか、有罪の場合には実刑か執行猶予判決か、罰金をいくら併科すべきかが決められます。
このように、脱税を疑われる場合には、税務調査から査察調査、刑事事件手続まで発展する可能性があります。
3.どのように対処すべきか
税務署の税務調査が入った場合には、まずは専門家に相談することをおすすめします。
なぜ税務調査が入ったのかを専門家である税理士や弁護士とともに検討して、査察調査に発展したり、刑事事件化してしまう可能性があるのかを確認してもらいましょう。
場合によっては、修正申告などで十分対応することが可能です。
しかし、査察調査や刑事事件に発展する可能性がある場合には、より慎重な対応が必要です。
告発をされないために、修正申告を行い未納の税額を早急に収めたり、聴き取り調査に対してきちんと対応したりできるかが重要となってきます。
また、刑事事件となって捜査を受けることになった場合には、逮捕されないための活動や不起訴獲得に向けた活動、さらには刑事裁判に対する準備なども早い段階から行っていくことが必要です。
特に査察調査が入った場合には、告発率は70%程度と言われていますので、刑事事件化を見据えて刑事事件に強い弁護士にも相談し、どのように対処していくべきか確認していくべきでしょう。
金密輸の場合には、悪質性が高いとして、比較的長期の懲役刑が科される可能性もありますし、併せて利益の3割程度の罰金刑も科される可能性があります。
刑罰とは別に、本来納めるべきであった税額に重加算税などの追徴課税も課せられることになるため、金銭的なペナルティが非常に重いものになります。
早期に弁護士や税理士などの専門家に相談して対応していきましょう。