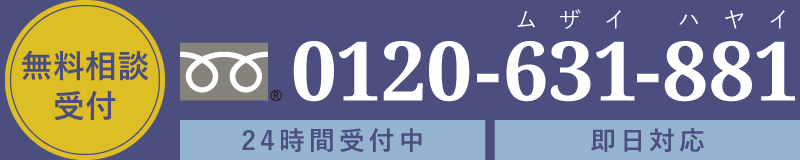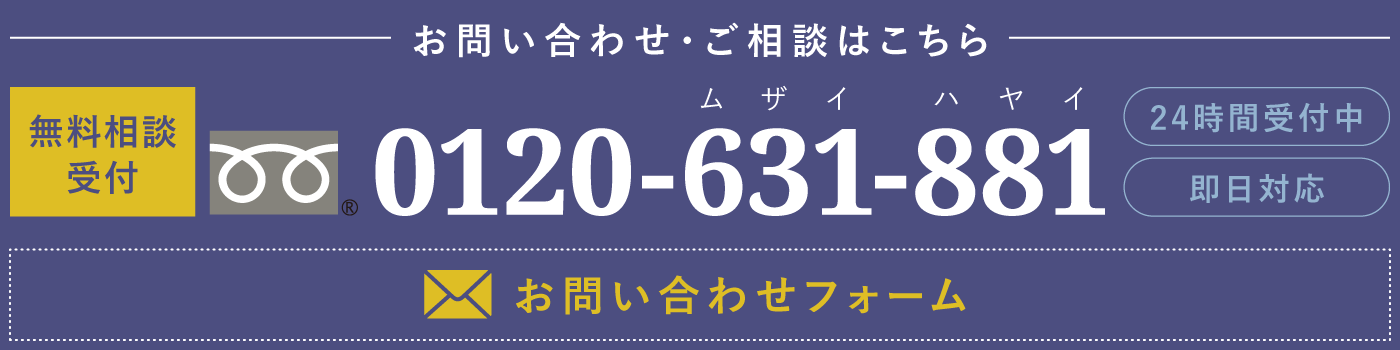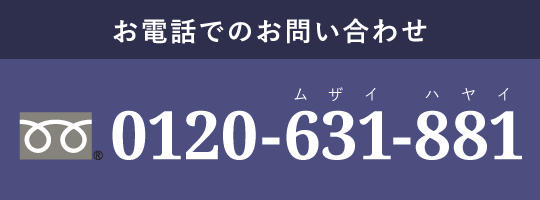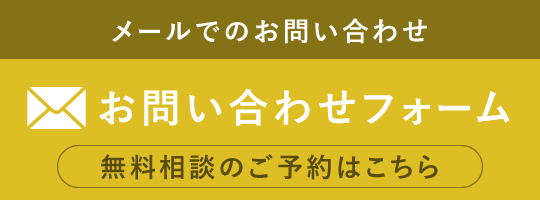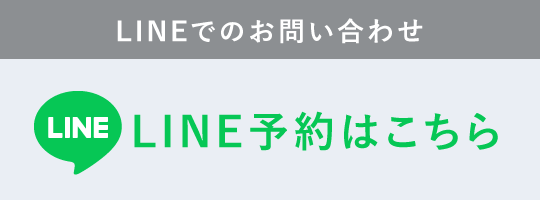このページの目次
奈良県香芝市の道路舗装会社と同会社の会長、同会社の経理責任者を大阪国税局が告発した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要
架空の外注費を計上する方法で、法人税を脱税したとして、大阪国税局が、奈良県香芝市の道路舗装会社(A建設)と同会社の会長B、同会社の経理責任者C(Bの妻)を奈良地検に告発しました。告発容疑は、Bら2人が、2023年8月期までの3年間に、約1億8600万円の所得を隠し、法人税約4700万円を脱税した疑いであり、関係者によると、A建設は、高速道路の舗装など公共工事を数多く受注し業績を上げていましたが、Bら2人は、複数の取引先に協力を依頼し、仕事を発注したように装っていたほか、実在しない企業名を書いた虚偽の領収書を作成し、外注費として計上していたとのことです。不正に得た資金は、土地の購入などに充てていました。
Bら2人は、取材に対して「修正申告をし、納税も済ませた。今後は適切に申告納税する。」と語っています。
(2025年4月28日、ニュース、毎日新聞より。一部改変)
https://home.kingsoft.jp/news/news/mainichi/20250427k0000m040081000c.html?from=content
建設業者による脱税事件は後を絶たない。
本件は、建設会社の会長及び経理責任者が敢行した脱税事件です。
建設業は、国税庁が毎年6月に公表する査察の概要の業種別告発件数のランキングで常にトップか上位にランクインされており、国税局も目を光らせて監視しています。
査察調査は、通常の税務調査の後、実施される場合もありますが、建設業は、そもそも税務調査が入りやすい業種とも言われています。
建設業に税務調査が入りやすい理由としては、長期間の工事が多く、工事期間が決算期をまたいで長期に渡ることもあるため、工事の振り分けによる売り上げのごまかしなどが行われやすいこと、1件当たりの工事金額が大きいため、売上金額が大きい分納税額も大きくなるという傾向があり、納税額が大きくなると申告内容にミスがあった場合に納税額への影響が大きくなるため、特に厳しく税務調査が実施される傾向があること、人件費と外注費が十分に線引きされておらず、社会保険料や労働保険料の支払いを免れるために、本来ならば人件費として計上すべき費用を外注費として計上する悪質な業者もいること、などが挙げられます。
刑事手続
Bら2人は、法人税法違反の疑いで刑事告発を受けています。
刑事告発を受けた検察庁は、Bらを被疑者として取調べ、その後起訴するか否かを決めることになります。
最近では、刑事告発されると約8割から9割の高率で起訴されるに至っています。
また、起訴された場合には、刑事裁判が始まります。
国税局が令和7年6月に発表した資料によると、査察事件の第1審判決の状況は、令和6年度中の判決件数99件全てが有罪であり、有罪率は100%となっています。このことから一旦起訴されると有罪となる可能性は極めて高いのが実情です。
建設業者による脱税は、建設業許可が取り消されるリスクもある。
建設業者による脱税では、刑事処罰を受けることとは別に建設業許可の取り消しのリスクもあることに注意が必要です。問題となるのは建設業許可の取り消し事由のなかの欠落要件についてです。建設業者の場合、廃業や営業をやめる場合を除くと、欠落要件に該当して許可が取り消されるケースが最も多くなっています。
法人税法違反の場合,Bら個人の法定刑は、10年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金、又はこれを併科する、となっています。
建設業法によると、建設業者が脱税を敢行した場合、欠落要件のなかの、(個人の場合)個人事業主本人、支配人、支店長や営業所長などの政令で定められた使用人、(法人の場合)代表取締役などの取締役、顧問や相談役、議決権を5%以上有する株主、支店長や営業所長などの政令で定められた使用人が、拘禁刑に処せられて、その刑の執行の終了日又は執行を受けることがなくなった日から5年以上経過していない者に該当する場合があります。
この場合には、建設業法によって、建設業の許可が必ず取り消さることになるため、例えば、建設会社の代表取締役が脱税を敢行した場合、起訴されて拘禁刑に処せられる可能性が高い場合には、判決が出る以前から、代表者の変更について検討する必要があることになります。
なお、執行猶予自体は、欠落要件に該当するため、執行猶予期間中の者(脱税した者が起訴され拘禁刑に処せられる場合には、このケースが多いと考えられます。)が、建設業の代表者やその他重要な役職に就いていることは建設業許可の取り消し事由の対象となります。その一方で、執行猶予期間が満了すれば、その時点で刑の言い渡しは消滅するので、執行猶予期間が満了していれば欠落要件には該当しないことになります。その期間が終了した日から5年間の経過を待つ必要はありません。
最後に 既にお話しましたように、ひとたび刑事告発をされてしまうと、極めて高い確率で起訴され、かつ、有罪となるという実情があります。ですから、脱税に関与してしまったという場合には、早急に弁護士に相談して刑事告発を避けるための活動をしていくのが極めて重要と考えられます。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、脱税に関する相談を無料で行っていますので、気軽に早急にお問合せください。