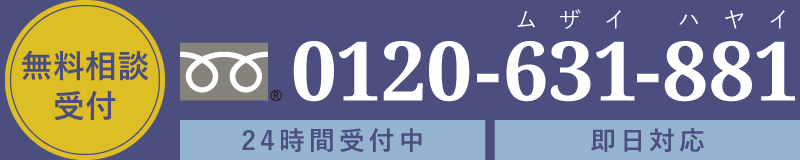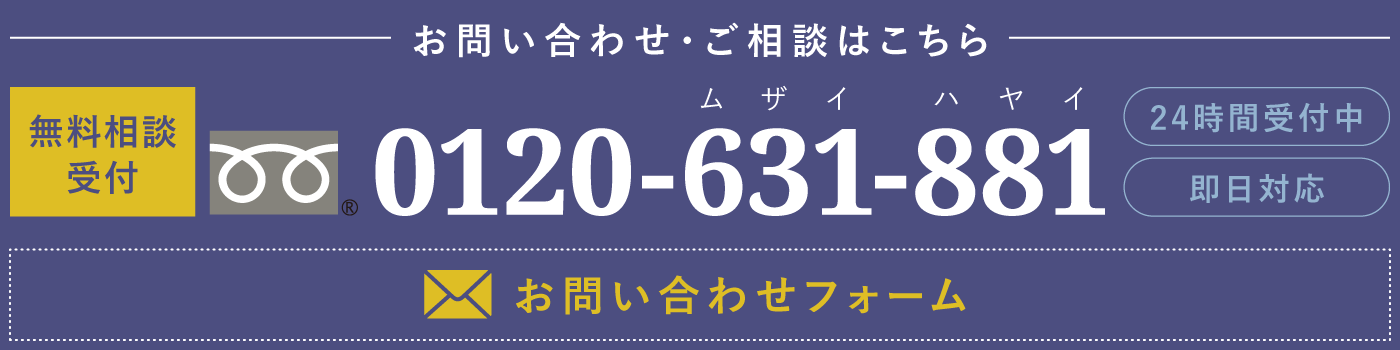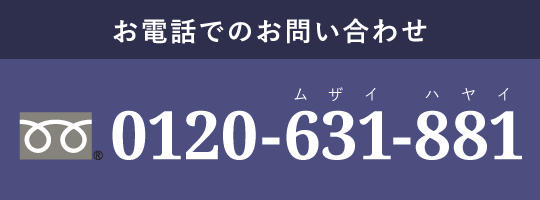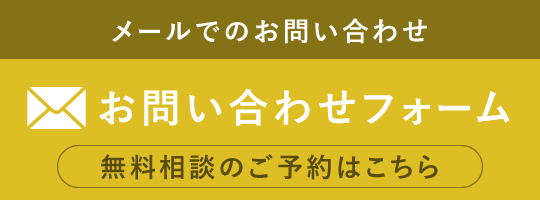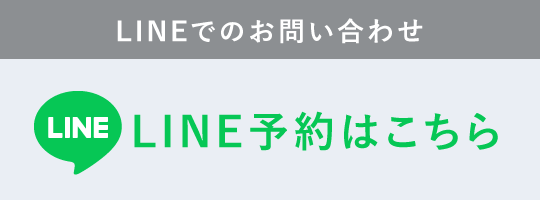このページの目次
相続した財産のうち現金を除外する方法で相続税約2億7千万円を免れた疑いで名古屋国税局から名古屋地方検察庁に告発を受けたという報道をもとに、相続税の計算などについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
報道の内容
相続財産から現金を除外して相続税約2億7千万円を脱税したとして、名古屋国税局は6日、相続税法違反の疑いで、いずれも名古屋市の会社役員、A氏と長男のB氏、次男のC氏を名古屋地検に告発したと発表した。昨年12月13日付。
国税局によると、3人は令和3年1月に死亡した男性の妻子として財産を相続。財産のうち、現金5億5300万円を除外する方法で、相続税約2億7千万円を免れた疑いがあるとしている。
関係者によると、現金の一部を除いた金額を税理士に伝え、申告していたという。
(産経新聞産経WEST令和7年2月6日の記事https://www.sankei.com/article/20250206-PJHUOXYWXJNATEO4LOSFT2JVNU/より一部改変)
相続税とは
人が亡くなると、その亡くなった人の配偶者や子供などに相続が発生します。
相続は亡くなった人の財産や負債(債務)などを、配偶者や子供などに引き継ぐことを言います。
そして、この相続した財産については、相続税が課せられる場合があります。
相続税の課税対象となるのは、亡くなった人から各相続人等が相続や遺贈などにより取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える財産です。
この相続税の課税対象となる金額を「課税遺産総額」といいます。
課税遺産総額を算出するには、相続や遺贈などにより取得した遺産総額から葬式費用や債務などを差し引いた遺産額に贈与を受けていた財産を加味した金額(「正味の遺産額」といいます)を算出し、そこから「基礎控除額」を差し引いて算出します。
基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」という計算式で導かれます。
たとえば、亡くなった人に配偶者と子供が2人いた場合、配偶者と子ども2人の合計3人が法定相続人となるため、3000+600×3=4800となり、4800万円が基礎控除額となります。
相続税の計算
課税遺産総額を算出したら、いよいよ具体的に誰がどれくらいの相続税を納めないといけないのかを計算していきます。
各相続人の相続税を計算するには以下の方法によります。
①課税遺産総額を法定相続分通りに取得したものと仮定して、それに税率を適用して各法定相続人別に税額を計算します。ここで計算された税額の合計額が相続税の総額です。
※法定相続分とは、民法が定めている相続人ごとの相続する割合のことで、たとえば、先ほどの配偶者と子ども2人がいる場合であれば、法定相続分は配偶者が2分の1、子どもがそれぞれ4分の1ずつ相続することになります。
②相続税の総額を、各相続人等が実際に取得した正味の遺産額の割合に応じて按分します。
③②から配偶者の税額軽減のほか、各種の税額控除を差し引いて、実際に収める税額を計算します。
※配偶者の税額軽減とは、配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が1億6000万円までか、配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者には相続税はかからないという制度です。 なお、配偶者控除を受けるためには、相続税の申告書の提出が必要です。また、正味の遺産額のうち仮装又は隠蔽されていた部分は、配偶者の税額軽減の対象とはならないため、注意が必要です。
報道をもとに実際に計算してみる
それでは、これまでの話を前提として、報道にある現金5億5300万円を妻と子ども2人が相続したと仮定して実際に相続税を計算してみましょう。ここでは、5憶5300万円を課税遺産総額とし、それぞれ法定相続分にしたがって相続したとして計算していきます。
①相続税の総額の計算
法定相続分は、妻が2分の1、子どもがそれぞれ4分の1ということになるため、課税遺産総額の5億5300万円を法定相続分にしたがって按分すると、妻が2億7650万円、子どもがそれぞれ1億3825万円となります。
法定相続分に応じた取得金額にそれぞれの税率をかけていくと、妻については2億円を超え3億円以下となっているので、税率は45%です。そのため、2億7650万円×0.45(45%)=1億2442万5000円となります。そして、ここから控除額(累進課税なので控除額が発生)2700万円を控除して、妻は9742万5000円が法定相続分にしたがった税額となります。
子供については、1億円を超え2億円以内なので、税率は40%です。そのため、1億3825万円×0.4(40%)=5530万円となります。そしてここから控除額1700万円を控除して、3830万円が税額となります。
そのため、相続税の総額は1億7402万5000円となります。
②実際に取得した正味の遺産額の割合で按分
今回は、法定相続分で実際にも相続したと仮定するので、①で計算した通り、妻は9742万5000円、子どもはそれぞれ3830万円が税額となります。
③配偶者税額軽減の適用
そして、妻については配偶者なので配偶者税額軽減の適用を受けることができ、今回は法定相続分で相続しているため、妻については法定相続分相当額である9742万5000円が軽減される結果、妻は納めるべき税金額は0円となります。
したがって、今回の場合には、子ども2人がそれぞれ3830万円を納めることで相続税の納付は完了するということになります。
もっとも、配偶者税額軽減を適用するには妻も相続税の申告書を提出する必要がありますので、納めるべき税金が0円であったとしても、妻も子供たちと一緒に確定申告をしておく必要があります。
報道の事例との比較
ここで、報道によれば、免れたと疑われている相続税の額は総額約2億7000万円とされており、先ほど計算した相続税の総額よりも多くなっています。
これは、相続税の税率が法定相続分に応じた取得金額によって変動するため、もし現金を除外していなければ50%や55%といった高い税率がかけられる財産を取得していたと考えられます。
そのため、除外した現金を入れて計算をし直した場合には、より多くの相続税を払う必要があり、報道と先ほど計算した税額に開きがあると考えられます。
また、妻については、現金除外をしている部分について仮想又は隠ぺいしていたといえるため、配偶者税額軽減の適用を受けることができなくなってしまいます。
相続が発生した場合には
相続が発生した場合、お葬式などでバタバタすることになり、なかなか相続税の申告まで気が回らないこともあると思います。
しかし、相続税の申告については、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10か月以内に被相続人の住所地の所轄税務署に申告・納税をする必要があります。
また、今回紹介した相続税の計算はあくまでも基本的なものであり、様々な軽減制度などもありますので、相続税を計算したり申告する場合には、専門家である税理士や弁護士に相談して、計算や申告を代わりに行ってもらうのがよいでしょう。
相続税の計算については、国税庁のホームページでも紹介されていますので、詳しくはこちらhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_5.htm#haigushakojoもご覧ください。