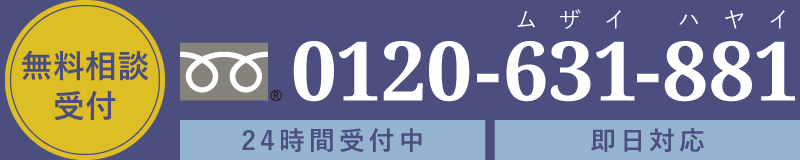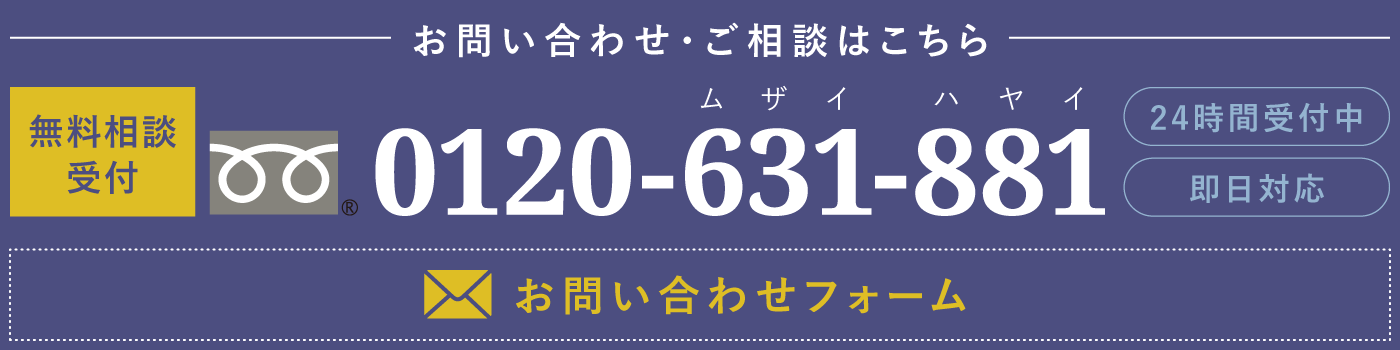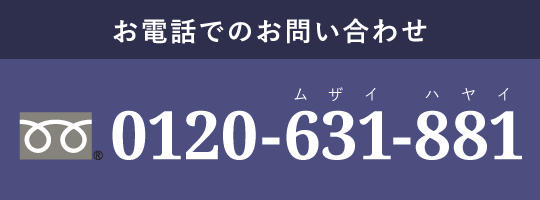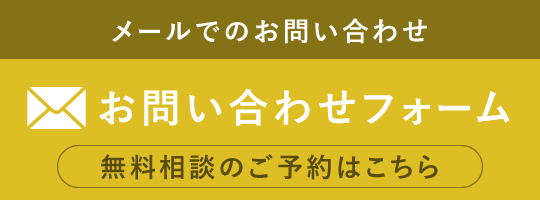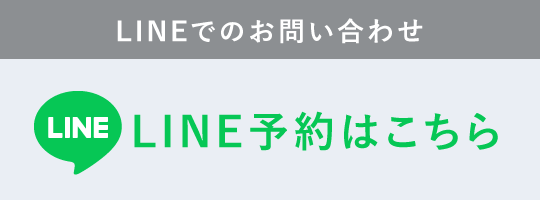このページの目次
輸出事業における消費税還付について、その仕組みや還付を受けるための条件、業種ごとの特殊性や告発事例などを弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
消費税還付の仕組み
日本の消費税は「仕入れに係る消費税額」を「売上に係る消費税額」から差し引いて納付額を計算する仕組みです。
輸出取引は消費税法上 輸出免税(税率0%)の対象となるため、海外への商品販売や国外向けサービス提供には消費税が課税されません。
したがって輸出売上には消費税が発生しない一方、国内で仕入れや経費に支払った消費税(入力税額)は控除可能であり、売上に係る消費税額より仕入れに係る消費税額の方が大きい場合、その差額が還付されます。
例えば、輸出売上200万円(税抜)に対する消費税0円と、仕入150万円(税抜)に対する消費税15万円では、15万円の還付を受けられます。
消費税還付を受けるための条件
消費税還付を受けるにはいくつかの条件があります。
①課税事業者であること
課税事業者であることが必要です。
前々年度の課税売上高が1000万円以下の事業者(免税事業者)は原則として消費税の納税義務がなく、消費税申告を行わないため還付も受けられません。ただし、免税事業者でも「課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になる選択をすれば還付申請が可能です。
新設法人も原則初年度は免税事業者ですが、資本金1000万円以上など一定の場合は最初から課税事業者となります。
②原則課税で申告計算していること
原則課税で申告計算(課税期間中の課税売上げに係る消費税額-課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額=消費税額)していることも条件です。消費税の簡易課税制度を適用(課税期間中の課税売上げに係る消費税額に、事業区分に応じた一定の「みなし仕入率」を掛けた金額を課税仕入れ等に係る消費税額とみなして、納付する消費税額を計算)している場合、実額に基づく仕入税額控除が行えず還付を受けられないためです。
③確定申告で還付申告を行うこと
還付を受けるためには該当期間について確定申告で還付申告を行うことが前提となります。
④輸出免税に該当する売上であること
取引面では、輸出免税に該当する売上であることが必要です。
輸出免税の適用範囲には、例えば「日本国内から海外への商品の輸出」「国際運送や国際通信」「非居住者への特許や著作権など無形財産権の提供」「非居住者への役務提供」などが含まれます。
これら輸出取引に該当する売上であれば税率0%となり、対応する仕入税額の還付を受けられます。
ただし非居住者相手のサービスでも、日本国内で直接便益を受けるもの(例:国内での宿泊・飲食提供など)は輸出取引とみなされず課税対象です。
なお、輸出免税の適用を受けるにはその取引が輸出であることを証明する書類を備えることが求められます。
申請手続きや必要書類
消費税の還付は所轄税務署への消費税確定申告を通じて申請します。法人の場合、事業年度終了日の翌日から2か月以内(個人事業主は翌年3月31日まで)に確定申告書を提出する必要があります。
還付申告の際には、以下の書類を提出します。
・消費税及び地方消費税の確定申告書(主たる申告用紙)
・付表2「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算書」(売上高に占める課税売上割合や控除仕入税額を計算する明細)
・消費税の還付申告に関する明細書(還付となる理由や取引ごとの売上・仕入明細を記載した書類)
確定申告書に還付額を計算の上で提出すると、税務署による内容確認を経て還付金の支払い決定がなされます。
輸出取引による還付を申告する場合、輸出売上に対応する還付額と国内売上に対する納付額をまとめて申告することになるため、輸出事業と国内事業の両方がある場合は申告書上で相殺計算する点に注意が必要です。
還付申告の証拠書類の用意
還付申告の証拠書類として、輸出取引であることを示す資料を準備・保管する必要があります。
輸出する商品のケースでは税関の輸出許可書(税関長の証明付き)を用意しなければなりません。
20万円以下の少額輸出で通常郵便物を使う場合は、日本郵便が発行する引受証明書(品名・数量・価額の記載されたもの)が証拠書類となります。
サービス提供や無形資産の提供など物品以外の輸出取引では、契約書など取引内容と国外提供であることを示す書面が必要です。
これらの書類は申告時に提出を求められる場合もあるため、輸出許可証や契約書類の原本を手元に保管しておくことが重要です。
特に輸出代行業者が輸出手続きを代行した場合でも、自社が還付を受けるには輸出許可書等の原本保管と所定の通知手続きを行う必要があります。
なお、輸出免税の証拠書類や帳簿は7年間の保存義務があります。
消費税の還付申告を行うと、原則として税務署による税務調査や審査の対象となります。
還付申告額が大きい場合や内容に不明点がある場合には、書面照会や実地調査によって輸出の実態や仕入控除の妥当性が確認されます。不備や誤りがあれば還付は認められません。
そのため、日頃から取引証憑の整備や正確な帳簿記録を行い、還付申告に備えることが大切です。
対象となる事業者の要件
①課税事業者であること
消費税還付を受けられる事業者は、課税事業者に限られます。
免税事業者の場合、消費税の申告義務がないため、たとえ輸出取引があっても仕入税額の還付を受けることはできません。
輸出を行う企業・事業者であれば、規模が小さく基準売上高1000万円以下でも、必要に応じて課税事業者選択届出を提出し課税事業者となることで還付申請が可能となります。
これは、輸出で仕入税額が多額になる場合、還付を受けられるよう自主的に課税事業者になる選択が有利となるためです(届出を適用する課税期間開始前日までに提出)。
②仕入税額控除の適用要件を満たすこと
還付を受けるには課税売上に対する仕入税額控除の適用要件を満たす必要があります。具体的には、帳簿及び適格請求書(インボイス)等の保存要件を満たし、課税仕入れについて適法に税額控除できる状態であることが重要です(2023年10月以降インボイス制度開始により、適格請求書等の保存が仕入税額控除の要件)。
輸出免税となる売上であっても、帳簿・証憑不備で仕入税額控除が否認されると結果的に還付も受けられなくなるため注意が必要です。
対象となる取引
輸出取引の種類については、前述したように商品の国外輸送による販売だけでなく、国外向けの役務提供や無形資産の譲渡も含まれます。
例えばメーカーが製品を海外顧客に直接販売するケース、商社が国内商品を買い付けて海外に輸出するケース、ソフトウェア企業が海外法人にソフトを提供するケースなどが該当します。これらはいずれも法律上は課税取引扱いで免税となるため、それに要した仕入や経費の消費税は全額控除・還付対象となります。
一方、非課税取引(例:国内の医療、教育、住宅の賃貸、金融など)や不課税取引(給与支払い、寄附など)はそもそも課税対象外であり、対応する仕入税額は控除できません。
輸出取引は非課税ではなく「課税対象だが税率0%」という位置付けのため、国内課税取引と同様に仕入税額控除が可能である点が大きな特徴です。
したがって、輸出売上を有する事業者は、たとえ売上に消費税がかからなくても課税事業者でありさえすれば仕入税額の還付を受けられます。
ただし事業者によっては、課税売上と非課税売上が混在する場合もあります。例えば国内で医薬品販売(社会保険診療は非課税)と輸出販売を併営するようなケースでは、非課税売上に対応する部分の仕入税額は控除できないため、その部分は還付対象外となります。
このように、還付を受けられる仕入税額はあくまで課税売上(輸出を含む)に紐づく部分のみである点に留意が必要です。
還付の受け取りの方法や期間
①還付金の受け取り方法
還付金の受け取り方法は、申告時に指定した銀行口座への振込か、ゆうちょ銀行・郵便局窓口での受領の2通りがあります。
一般には口座振込が利用されますが、口座名義は申告者本人または納税管理人名義である必要があります。
②還付金が振り込まれるまでの期間
消費税還付が振り込まれるまでの期間は、申告から概ね1~2か月程度が一般的な目安です。
税務署による申告内容の確認や書類チェックにある程度時間を要するため、還付金の入金完了まで数週間から数ヶ月かかるのが通常です。
ただし、電子申告(e-Tax)を利用した場合は処理が迅速化される傾向があり、早ければ提出後2~3週間で還付されるケースもあります。
実際、繁忙期でない時期にe-Taxで申告書を送信すれば1か月以内に振り込まれる例も報告されています。
一方、2月~3月の確定申告シーズンは事務処理が立て込むため、通常より時間がかかる可能性があります。
資金繰り上、還付金を早めに受け取りたい場合は、できるだけ早期に申告手続きを行い、e-Taxを活用するのが望ましいでしょう。
還付額が継続的に発生する輸出業者では、資金繰りの観点から還付を迅速に受けるための制度活用も有効です。例えば課税期間の短縮特例を利用すると、通常1年ごとの課税期間を四半期毎や月毎に区切って申告できるため、還付発生時期を早めることができます(適用には事前に「課税期間特例選択届出書」を提出し2年間の継続適用が必要です)。
申告期限を徒過した場合の不利益
申告期限は厳守する必要があります。法人の場合、課税期間(事業年度)終了日の翌日から2ヶ月以内が確定申告の法定期限であり、これを過ぎると期限後申告となります。期限後申告でも還付自体は受けられますが、その場合税務上いくつかの不利益があります。
①還付加算金の計算起点の繰り下がり
還付加算金(税務署から支払われる利息相当額)の計算起点が繰り下がります。
通常、適法な期限内申告で還付となった場合、申告期限の翌日から還付される日までの期間について年利により算出した還付加算金が支払われます(国税通則法第58条)。
税務署側の処理遅延については、法律上、還付申告に対する還付金は速やかに支払うものとされています。万一、税務署の事情で大幅に還付が遅れる場合には、その期間に応じた還付加算金が付されます。
実務上は申告から1~2ヶ月程度で還付されることがほとんどですが、仮に調査が長引く等で還付が遅れた場合でも、納税者には一定の利息補填がなされる仕組みです。
しかし期限後申告で還付を受ける場合、加算金の起算日は本来の期限ではなく、課税期間終了後2ヶ月経過日や申告書提出日の属する月末などに修正されます。
その結果、期限内申告に比べて遅延した期間分の利息が付かなくなる(事実上、還付が遅れるだけ損をする)ことになります。
②ペナルティ
また、期限後申告そのものに対して無申告加算税などのペナルティが課される可能性もあります。
以上から、還付を確実かつ有利に受けるためには申告期限内に正確な申告を行うことが重要です。
業種による消費税還付の状況
①製造業の場合
メーカーの場合、製品を海外に輸出すれば売上に対する消費税は0%ですが、生産に必要な原材料費や設備投資には国内で消費税を支払います。輸出比率が高い製造業者ほど、支払った消費税額が預かった消費税額を上回りやすく、多額の還付を受ける傾向があります。
実際、日本を代表する自動車メーカー等の大企業は毎年巨額の消費税還付を受けており、2022年度には輸出大企業上位20社で合計約1兆9千億円もの消費税が国から還付されたとの推計もあります。
②貿易会社の場合
貿易会社でも、例えば、国内メーカーから商品を税込仕入して輸出すれば、仕入時の消費税分が丸ごと還付対象となります。貿易業者にとって消費税還付は重要な資金源とも言え、適切な手続きによりキャッシュフローを確保することができます。
③サービス業の場合
サービス業においても、提供先が海外(非居住者)でサービスの消費が国外で完結する場合は輸出免税が適用されます。
国際通信サービス、国際輸送サービス、海外法人向けのコンサルティングやエンジニアリング、ソフトウェア・デザインの提供、特許やライセンス供与などは非居住者に対する役務提供として消費税が免税になります。
その結果、国内で要した人件費以外の経費(オフィス賃料や機器購入費用など)に含まれる消費税の還付を受けられます。例えば日本のIT企業が海外企業と契約して開発サービスを提供する場合、売上に消費税は発生しませんが、国内で購入したパソコンやソフトウェア、通信費等の消費税は全て控除・還付されます。
一方、旅行業やホテル業など訪日外国人相手のサービスは、そのサービス提供が日本国内で行われ直接便益を享受させるもののため免税にならず、通常通り課税となります。
このようにサービス業でも取引の性質によって消費税の扱いが異なり、国外向けサービスを主とする事業者は輸出産業同様に還付を受けるケースがあります。
特別なケース
特別なケースや過去の事例としては、事業構造や取引形態に起因する消費税還付があります。例えば、設立初年度に巨額の設備投資を行った場合です。工場建設や大型機械の購入などで一時的に多額の消費税を支払うと、売上が立つ前でもその分の消費税は還付申告により取り戻すことができます。実際、赤字や経費過多の場合、預かった消費税より支払った消費税が多くなり還付を受けられます。
また、不動産業でオフィスビル等を購入したケースでは、購入時に支払った消費税がテナントへの課税賃貸料収入より大きければ還付となります。不動産の用途によっては課税売上が見込めず本来控除できないケースもあるため、一部では還付を得る目的で物件の用途変更を行うようなスキームが問題視されたこともあります。この分野について税制改正で調整措置が講じられ、意図的な還付取得を防ぐルールが整備されています。
日本の国税局の告発事例
消費税還付制度を悪用した不正行為に対しては、国税庁が厳しい姿勢で臨んでいます。国税庁によれば、不正は年々巧妙化しており、国税局は消費税還付申告に対する調査を強化しています。
近年明らかになった大規模不正の一例に、調剤薬局チェーンによる架空取引を利用した消費税不正還付事件があります。
このケースでは、処方箋医薬品販売が主で本来は非課税売上(社会保険診療)となる薬局グループが、グループ内で実態のない医薬品売買をでっち上げ、課税売上割合を意図的に引き上げていました。
課税売上割合を水増しすることで、本来控除できないはずの非課税売上対応仕入に係る消費税まで控除し、結果として約16億円もの消費税を不正に還付申告していたのです。
この不正は札幌国税局が関連会社の調査で疑いを掴み、大阪国税局や東京国税局と連携した広域調査によって発覚しました。
グループ企業は追徴課税として重加算税を含む約23億円を修正申告し、国税当局から告発される事態となっています。
国税庁全体で見ても、この大阪国税局管内の事例は規模が突出しており、当局が不正還付に警鐘を鳴らす契機となりました。
他にも架空の輸出取引を装った不正還付の事例があります。例えば2019年津地方裁判所の判決では、ある企業が存在しない輸出免税売上と架空の課税仕入を計上し、不正に消費税還付を受けていた事実が認定されています。
このように、実際には輸出していないにもかかわらず書類を偽装して還付金を騙し取る手口は過去にも発生しており、国税当局は偽装された輸出許可証や取引請求書の発見に努めています。
不正還付が発覚した場合、消費税法違反(偽りその他不正行為による還付受領)として告発され、裁判で有罪となれば重い罰則が科されます。加えて、追徴税として重加算税が付されるなど経済的不利益も非常に大きくなります。
国税局は近年、還付申告に対する審査を一層厳格化しています。特に高額還付が継続する輸出企業や、不自然な取引を含む申告には重点的に実地調査を実施し、不正の摘発に力を入れています。
国税庁の統計でも還付申告に対する調査件数や追徴事例が報告されており、不正抑止の効果もあってか年々不正件数自体は横這いから微減傾向にあります。
いずれにせよ、正当な輸出取引に基づく還付は適法に受けられますが、虚偽の還付申請は高確率で発覚し告発リスクを伴うことに留意すべきです。適切な範囲で消費税還付制度を利用しつつ、法令遵守のもと健全な資金繰りに役立てることが重要です。