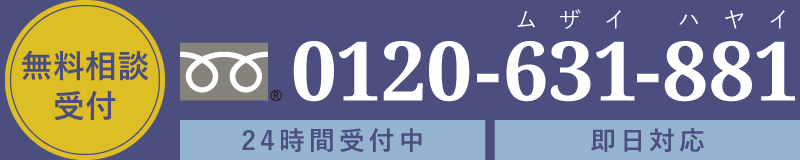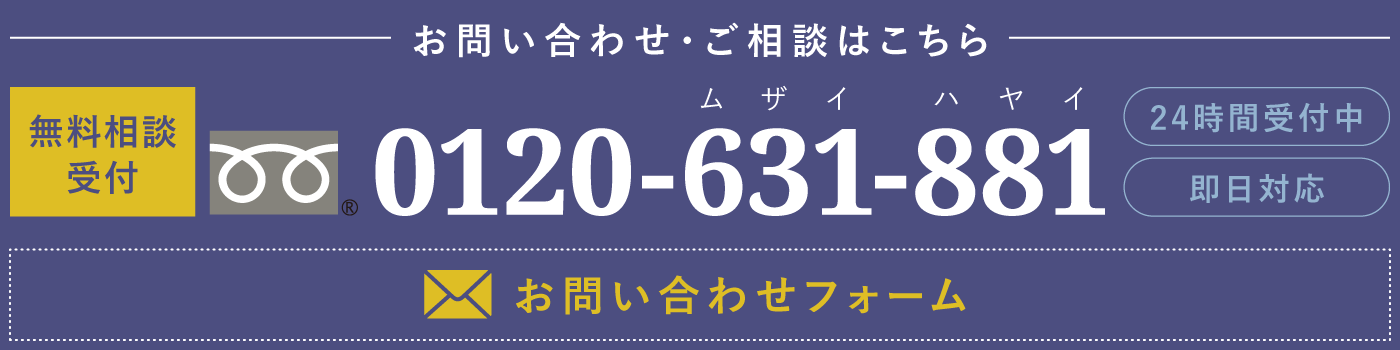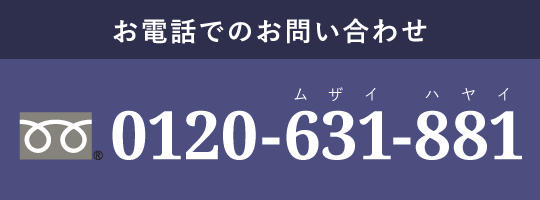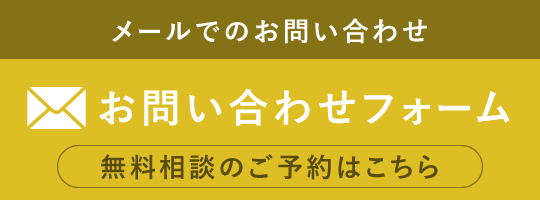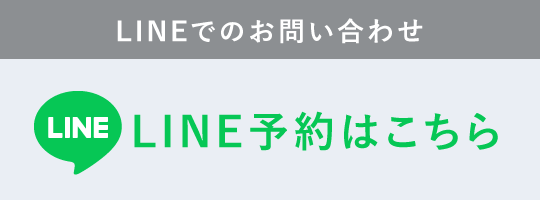このページの目次
輸出事業における消費税還付について、その仕組みなどを複数回にわたって紹介します。初回は消費税還付の仕組みや消費税還付を受けるための要件、申請の手続などについて紹介します。
消費税還付の仕組み
日本の消費税は「仕入れに係る消費税額」を「売上に係る消費税額」から差し引いて納付額を計算する仕組みです。
輸出取引は消費税法上 輸出免税(税率0%)の対象となるため、海外への商品販売や国外向けサービス提供には消費税が課税されません。
したがって輸出売上には消費税が発生しない一方、国内で仕入れや経費に支払った消費税(入力税額)は控除可能であり、売上に係る消費税額より仕入れに係る消費税額の方が大きい場合、その差額が還付されます。
例えば、輸出売上200万円(税抜)に対する消費税0円と、仕入150万円(税抜)に対する消費税15万円では、15万円の還付を受けられます。
消費税還付を受けるための条件
消費税還付を受けるにはいくつかの条件があります。
①課税事業者であること
課税事業者であることが必要です。
前々年度の課税売上高が1000万円以下の事業者(免税事業者)は原則として消費税の納税義務がなく、消費税申告を行わないため還付も受けられません。ただし、免税事業者でも「課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になる選択をすれば還付申請が可能です。
新設法人も原則初年度は免税事業者ですが、資本金1000万円以上など一定の場合は最初から課税事業者となります。
②原則課税で申告計算していること
原則課税で申告計算(課税期間中の課税売上げに係る消費税額-課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額=消費税額)していることも条件です。消費税の簡易課税制度を適用(課税期間中の課税売上げに係る消費税額に、事業区分に応じた一定の「みなし仕入率」を掛けた金額を課税仕入れ等に係る消費税額とみなして、納付する消費税額を計算)している場合、実額に基づく仕入税額控除が行えず還付を受けられないためです。
③確定申告で還付申告を行うこと
還付を受けるためには該当期間について確定申告で還付申告を行うことが前提となります。
④輸出免税に該当する売上であること
取引面では、輸出免税に該当する売上であることが必要です。
輸出免税の適用範囲には、例えば「日本国内から海外への商品の輸出」「国際運送や国際通信」「非居住者への特許や著作権など無形財産権の提供」「非居住者への役務提供」などが含まれます。
これら輸出取引に該当する売上であれば税率0%となり、対応する仕入税額の還付を受けられます。
ただし非居住者相手のサービスでも、日本国内で直接便益を受けるもの(例:国内での宿泊・飲食提供など)は輸出取引とみなされず課税対象です。
なお、輸出免税の適用を受けるにはその取引が輸出であることを証明する書類を備えることが求められます。
申請手続きや必要書類
消費税の還付は所轄税務署への消費税確定申告を通じて申請します。法人の場合、事業年度終了日の翌日から2か月以内(個人事業主は翌年3月31日まで)に確定申告書を提出する必要があります。
還付申告の際には、以下の書類を提出します。
・消費税及び地方消費税の確定申告書(主たる申告用紙)
・付表2「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算書」(売上高に占める課税売上割合や控除仕入税額を計算する明細)
・消費税の還付申告に関する明細書(還付となる理由や取引ごとの売上・仕入明細を記載した書類)
確定申告書に還付額を計算の上で提出すると、税務署による内容確認を経て還付金の支払い決定がなされます。
輸出取引による還付を申告する場合、輸出売上に対応する還付額と国内売上に対する納付額をまとめて申告することになるため、輸出事業と国内事業の両方がある場合は申告書上で相殺計算する点に注意が必要です。
還付申告の証拠書類の用意
還付申告の証拠書類として、輸出取引であることを示す資料を準備・保管する必要があります。
輸出する商品のケースでは税関の輸出許可書(税関長の証明付き)を用意しなければなりません。
20万円以下の少額輸出で通常郵便物を使う場合は、日本郵便が発行する引受証明書(品名・数量・価額の記載されたもの)が証拠書類となります。
サービス提供や無形資産の提供など物品以外の輸出取引では、契約書など取引内容と国外提供であることを示す書面が必要です。
これらの書類は申告時に提出を求められる場合もあるため、輸出許可証や契約書類の原本を手元に保管しておくことが重要です。
特に輸出代行業者が輸出手続きを代行した場合でも、自社が還付を受けるには輸出許可書等の原本保管と所定の通知手続きを行う必要があります。
なお、輸出免税の証拠書類や帳簿は7年間の保存義務があります。
消費税の還付申告を行うと、原則として税務署による税務調査や審査の対象となります。
還付申告額が大きい場合や内容に不明点がある場合には、書面照会や実地調査によって輸出の実態や仕入控除の妥当性が確認されます。不備や誤りがあれば還付は認められません。
そのため、日頃から取引証憑の整備や正確な帳簿記録を行い、還付申告に備えることが大切です。