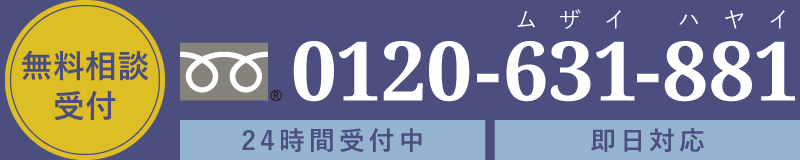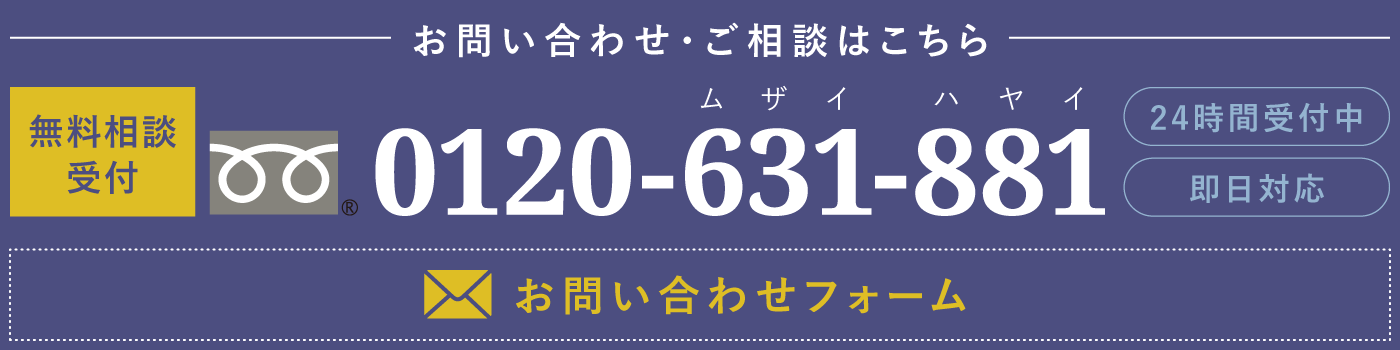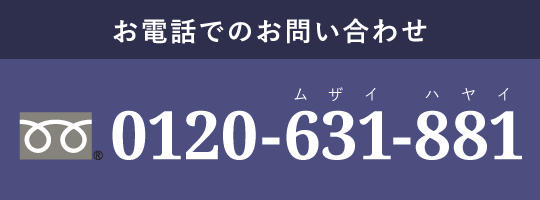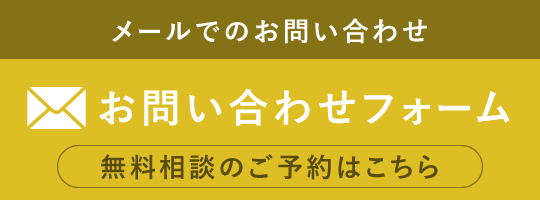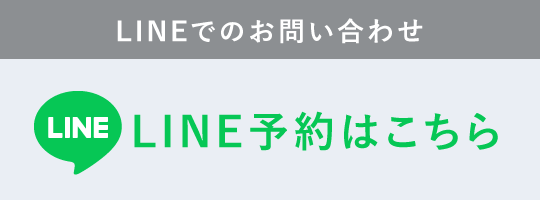このページの目次
消費税の不正還付事案について、手口や告発事例、不正が発覚した場合の対応などについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所がシリーズで解説します。
最終回、第4回目の今回は、税務調査の流れと不正が疑われた際の対応について解説します。
税務調査の流れ
税務調査は、納税申告内容の正確性を確認するために税務署等が行う検査です。消費税の還付申告を行う事業者は特に注意が必要で、申告内容に不審な点があれば調査の対象となる可能性があります。調査は大きく分けて2段階あります。
①任意調査(通常の税務調査)
まずは税務署による任意の調査が行われます。調査官から帳簿や請求書の提出を求められたり、ヒアリングを受けたりする形で進みます。還付申告の場合、特に仕入れや輸出の記録について詳細に確認されるでしょう。
ここで事実と異なる申告が見つかった場合、修正申告を求められ追徴課税(加算税を含む)を受けることになります。
重要なのは、この段階ではまだ刑事手続きではないため、調査官の質問等には可能な限り誠実に対応し、不審を持たれる行為(記録の廃棄、改ざんなど)は絶対にしないことです。
仮に申告ミスや誤りに気付いた場合は、調査が本格化する前に自主的に修正申告を行い不足税額を納付することで、重加算税の免除や告発の回避につながる場合もあります。「うっかりミス」と「悪質な仮装・隠蔽」では当局の対応も大きく異なりますので、意図的な不正でなくとも迅速に正す姿勢が肝心です。
②強制調査(査察調査)
調査の結果、悪質な仮装・隠蔽が疑われ、金額も大きい場合には、税務署レベルから国税局査察部(マルサ)に案件が引き継がれ、刑事告発を見据えた強制調査が行われます。
査察調査では裁判所の令状に基づき家宅捜索や帳簿・PCの押収などの強制力をもった調査が実施され、関係者に対する取り調べも行われます。
この段階に至った場合、基本的に事件は刑事告発→起訴へ進む前提で調査が行われます。一年間にわたる内偵・強制調査の末に告発となるケースもあり、調査期間中は関係者は長期間に及ぶプレッシャーに晒されることになります。
不正が疑われたときに取るべき対応
まず第一に「証拠隠しや虚偽説明は厳禁」です。
不正の事実をごまかそうとして帳簿を改ざん・廃棄したり、関係者に口裏合わせを指示したりすれば、かえって仮装・隠蔽の意図を明白に示すこととなり、情状は悪化します。調査官からの質問には事実関係を確認しつつ慎重に答える必要がありますが、自身で判断が難しい場合はその場で無理に断定せず、「後日資料を提出させてください」など柔軟に対応しましょう。
任意調査の段階で専門家の助言を受けることも検討すべきです。税理士や弁護士は、調査官とのやり取りに同席したり資料提出の代理をしたりといったサポートが可能で、適切な対応によって調査官の心証を害さず誤解を解く助けとなります。
もし既に査察部による強制調査に入ってしまった場合は、速やかに弁護士に連絡することが肝要です。強制調査では逮捕・起訴の可能性が現実味を帯びるため、以降は刑事弁護の視点で戦略を立てる必要があります。自宅や事務所への家宅捜索が入った時点で、「これは単なる税務調査ではなく刑事事件になるかもしれない」と覚悟し、すぐに刑事弁護に明るい弁護士に相談してください。
弁護士の役割と早期相談の重要性
消費税の不正還付に関する疑いをかけられた場合、早期に弁護士に相談することが極めて重要です。不正還付は単なる税務上の違反にとどまらず、刑事事件へと発展する可能性が高い性質を持ちます。特に査察(マルサ)の強制調査が入った段階では、もはや専門家の助力なしに適切に対応することは困難です。
何より大切なのは早めの段階で相談することです。査察が入った段階から弁護士に相談し今後の対応を協議・準備しておけば、逮捕や起訴を避けたいという要望に沿って適切な対策を打つことができます。
逆に対応が後手に回ると、取り調べで不利な供述をしてしまったり、押収された証拠に適切な反論ができなかったりと、防御が難しくなります。「もしかするとまずいことをしてしまったかもしれない」「税務署から問い合わせが来ている」「周囲で同様の調査が入った」という段階でも、疑いがあるなら一刻も早く専門家に相談するのが得策です。
弁護士は依頼者の権利と利益を守るプロフェッショナルです。不正還付の疑いをかけられた場合、事実関係の如何にかかわらず、独断で動くのではなく必ず専門家の力を借りてください。それが、最終的にリスクを最小限に抑え、企業経営や人生を立て直すための第一歩となります。
まとめ
以上、消費税の不正還付の典型的手口から具体例、処罰の内容、そして発覚時の対応まで詳しく説明しました。不正還付は一時的に資金繰りを潤すように見えても、発覚すれば取り返しのつかない損失とリスクを招きます。適正な申告と納税が企業経営の大前提であり、万が一にも疑わしいスキームに手を出さないことが肝要です。万一、「これはもしかして…」と後になって気付いた場合や、税務署から問い合わせや調査の連絡が来た場合には、できるだけ早く信頼できる専門家(税理士・弁護士)に相談し、適切な対応をとってください。それが自身と会社を守る最善の策と言えるでしょう。