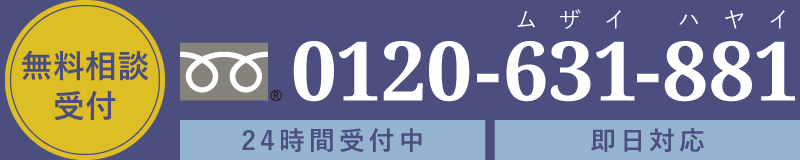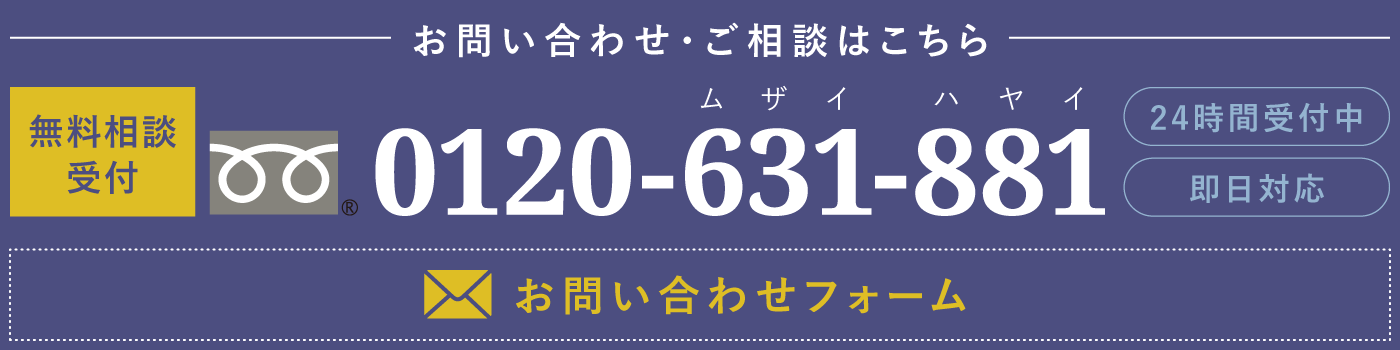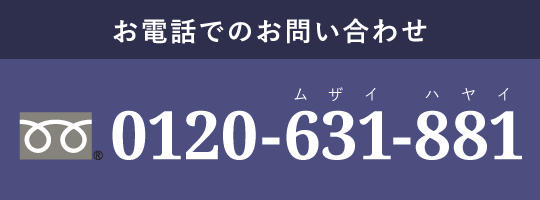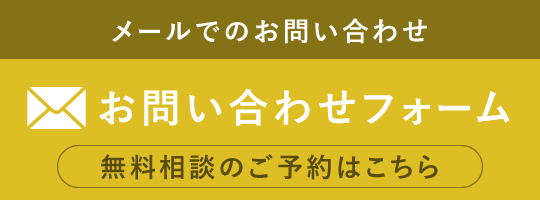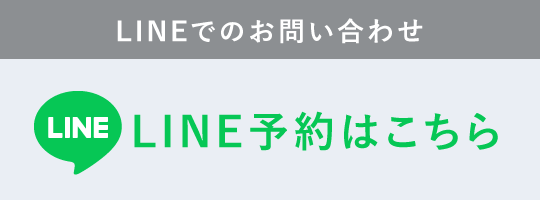このページの目次
税務署から税務調査を実施するとの連絡が来た事例を参考に、税務調査の事前通知に関して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
1 参考事例
東京で飲食業を営むXさんのもとに、新宿税務署から、8月1日午前9時頃より、所得税に関する調査を行う旨の連絡が来ました。
突然の連絡に不安に思い、知り合いから弁護士に相談してみてはどうかと言われ、法律相談に訪れました(事例はフィクションです。)。
2 税務調査における事前通知
税務調査とは、たとえば、確定申告した内容に誤りがないのか、誤りがあるのであれば本来納めるべき税金を納めるようにするために、納税義務者等に対し、質問をしたり、資料の提示・提出を求めたりすることをいいます(国税通則法[以下、「法」といいます。]74条の2以下)。
税務調査を行うにあたって、税務署長等は、税務署職員等に税務調査を行わせる場合には、原則として、あらかじめ、対象となる納税義務者に対し、一定の事項(税務調査を開始する日時や場所、調査の目的や調査の対象となる税目など)を通知するものとされています(法74条の9第1項)。
これは、事前に通知をし、抜き打ち的な調査をさせないことで、税務調査までに準備させる機会を与えようという考え方に基づくものです。
事前通知につきましては、国税庁のホームページも参照してください。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h24/nozeikankyo/ippan02.htm
3 事前通知が来てから税務調査までにできること
管轄の税務署から通知が来た場合、通知を受けた側としては、次のようなことをすることが考えられます。
まず、通知において日時が指定されるわけですので、業務や私生活に支障が出ないように、スケジュールを調整することが考えられます。
場合によっては、税務署に対し、日程を別の日に変更してもらうように相談することも考えられます。
また、帳簿等の準備をすることも重要です。
当たり前かもしれませんが、仮に、脱税をしており、事前通知があったからといって隠蔽工作をする機会をもらったわけではありません。
しかし、調査がスムーズに実施されるように、提示が求められそうな資料をまとめておいたり、こちらから説明する際に必要な資料を準備しておくことは重要です。
さらに、そうした準備とも関係しますが、税理士などの税務代理人がいない場合には、税務代理人を就けたり、税務調査に立ち会わせたりすることも考えられます。
税務調査の事前通知は、一定の場合には、納税義務者ではなく、税務代理人に対して行えば足りるとされています(法74条の9第5項)ところ、参考事例においては、Xさん本人に通知があり、まだ税理士などがいないことが想定されます。
税務調査において、税務署側に、適切な説明を行うことで、あらぬ疑いをかけられることを防ぐことができます。
このとき、より法律的な説明が必要になる場合には、税理士ではなく弁護士(あるいは両方)をつけ、税務調査に対応していくということが考えられます。
4 最後に
ここまで説明してきたように、税理士や弁護士を税務調査に関与させていくということが考えられます。
しかし、そもそも、仮に脱税をしてしまっていた場合において、今後、どのような手続が予想されるのか、税務調査で終わらず刑事裁判となる可能性があるのか、そうした可能性があるとしてもどのような対応をしていくか、早い段階でアドバイスを受けておくというのも重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、脱税事件に強い弁護士が所属し、多数の脱税事件を取り扱っています。税務調査の事前通知が来た、脱税をしたかもしれない、国税庁から告発され刑事事件化するかもしれないと不安に感じていらっしゃる方は、初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。