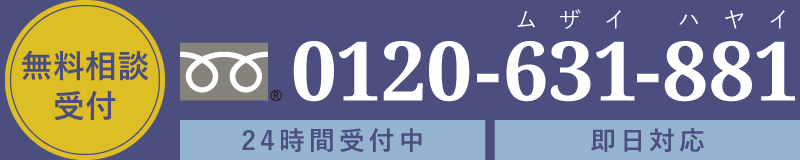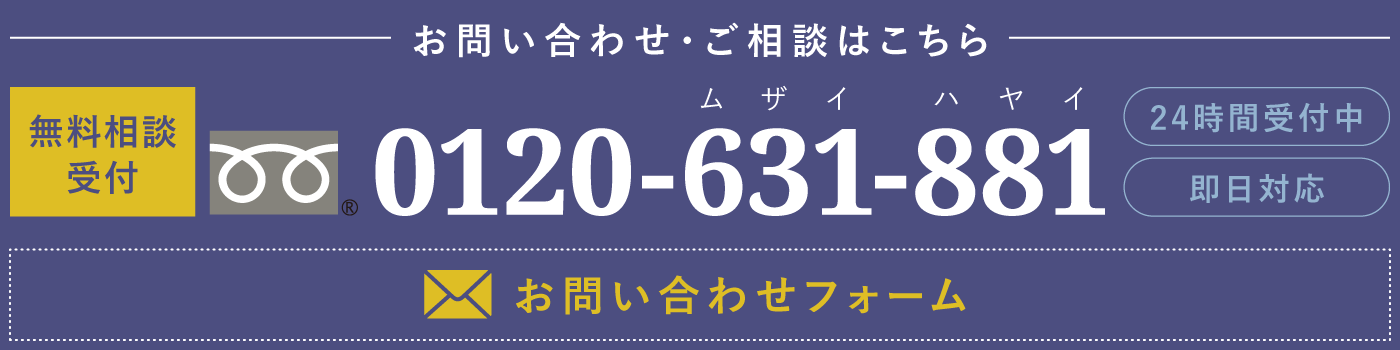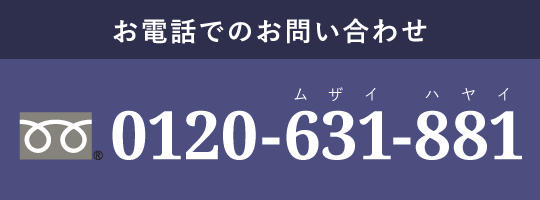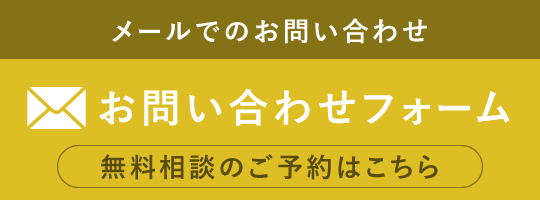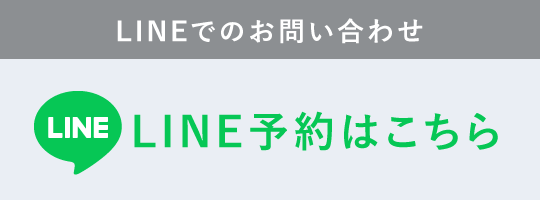このページの目次
飲食店において源泉徴収漏れが発覚した場合のリスクについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
源泉徴収とは
源泉徴収とは、企業が従業員の給与から所得税に当たる部分を差し引いて、企業が従業員の代わりに所得税を国に収める制度のことを言います。
源泉徴収制度の目的は、従業員の所得税の申告漏れを防ぐことにあります。
企業に勤めている従業員の方は、この源泉徴収制度により所得税が納められているため、基本的には自分で確定申告をして所得税を納める必要がありません。
源泉徴収の仕組み
源泉徴収制度は、企業が従業員の代わりに従業員の所得税の計算や申告をするものです。
そのため、納税義務者は企業ということになります。
源泉徴収の対象となるのは、基本的に企業から支払われる給与所得です。
その他には、退職金や株の配当金なども源泉徴収の対象になります。
源泉徴収されているかどうかは、企業から交付される給与明細をご覧いただくと、所得税などが差し引きされていると思いますので、給与から差し引きされている場合には源泉徴収が行われていると判断することができます。
この源泉徴収された税金部分(源泉所得税)は、企業が毎月国に納税しています。
飲食業は、税務調査が入りやすい業種であり、しかも調査は突然行われることが多い。
飲食業は、税務調査が入りやすい業種の一つです。その理由としては、現金商売が多いため、売上の除外や過少申告のリスクが高いこと、日々の仕入れが頻繁に発生し、食材や備品の購入を現金で行うことも多いため、仕入れの計上漏れが起こりやすいことなどが挙げられます。
また、飲食業に対する税務調査は、無予告で突然行われることが多いといえます。税務調査が行われる場合、課税庁は、納税義務者に対し、あらかじめ、調査を開始する日時・場所、調査の目的、調査の対象となる税目、調査の対象となる期間等を通知しなければならないとされています(国税通則法74条の9・1項)。このように、税務調査が行われる場合には、課税庁から事前連絡があるのが原則です。
しかし、飲食業の場合、現金商売が多いため、事前連絡なしで、いきなり店舗に調査官が訪れるケースもあり得ます。現金商売の場合、事前に通知をすることで、その時だけ現金の調整をされてしまうと、税務調査に出向く意味がなくなってしまうからです。
このような無予告調査は、法律で認められている調査であり、課税庁は、被調査者である納税義務者の申告や過去の調査実績、事業内容などから、違法または不当な行為を容易にし、正確な所得や税額などの把握を困難にするおそれ、その他調査の遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、事前通知を要しない、とされています(国税通則法74条の10)。
飲食店において源泉徴収漏れが発覚した場合のリスクについて
飲食店の経営者にとっても、従業員の給与等から所得税を天引きして納税する源泉徴収は日常業務の一環です。
しかし、源泉徴収義務は法律上の徴収義務であるだけに、源泉徴収漏れが生じた場合、その影響はかなり深刻です。飲食店業は、そもそも税務調査が入りやすい業種であることは既にお話しましたが、飲食店に税務調査が入り、源泉徴収漏れが発覚した場合、単なる経理処理上のミスでは済まされず、追徴課税や延滞税はもちろん、悪質な場合には刑事責任まで問われるリスクもあります。
飲食店で頻発する源泉徴収漏れとは
飲食店では、アルバイト従業員に対する給与等の支払いについて源泉所得税の徴収漏れが生じやすいと言われています。
多くの飲食店がアルバイトやパートを雇用していますが、毎月継続して給与を支払っている以上、源泉徴収を行わなければならないことは正規の従業員と変わりありません。しかるに、アルバイトやパートの場合、源泉徴収をする必要はないと誤解して源泉所得税が徴収漏れとなっているケースが多々見受けられます。
また、家族経営等の小規模飲食店の場合、アルバイト従業員に対する給与を手渡ししており、源泉所得税の天引きを失念していたケース等もあります。
税務調査で源泉徴収漏れを指摘された場合の一般的な流れ
源泉徴収漏れというのは、本来納付すべき税額に不足が生じている事態ですので、その不足分については延滞税及び加算税(不納付加算税)が課されます。また、税務調査の結果、隠蔽又は仮装工作によるものと判断された場合には、通常の加算税に代えて重加算税が賦課されます。重加算税は、不納付加算税を賦課する代わりに、本来納めるべき税額の35%もの高率で賦課される税金です。
刑事手続
源泉徴収漏れが発覚した場合、一般的な納付税額の過少の場合には、本来の納税額の納付に加えて、各種加算税等の納付の手続きを経て終結します。
しかしながら、源泉徴収漏れが単なる偶発的なミスではなく、意図的なもので、不納付額も多額に上るなど悪質な脱税行為と判断された場合には、税務当局は、検察庁に刑事告発を行うことになります。
刑事告発を受けた検察庁は、飲食店の経営者、経理関係者等を被疑者として取調べ、その後起訴するか否かを決めることになります。
最近では、刑事告発されると約8割から9割の高率で起訴されるに至っています。
また、起訴された場合には、刑事裁判が始まります。
国税局が令和7年6月に発表した資料によると、査察事件の第1審判決の状況は、令和6年度中の判決件数99件全てが有罪であり、有罪率は100%となっています。このことから一旦起訴されると有罪となる可能性は極めて高いのが実情です。
最後に 既にお話しましたように、ひとたび刑事告発をされてしまうと、極めて高い確率で起訴され、かつ、有罪となるという実情があります。ですから、税務調査を受け、源泉徴収漏れが発覚するかもしれない、あるいは、発覚したという場合には、早急に弁護士に相談して刑事告発を避けるための活動をしていくのが極めて重要と考えられます。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、脱税に関する相談を無料で行っていますので、気軽に早急にお問合せください。