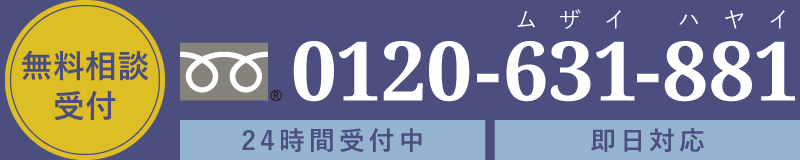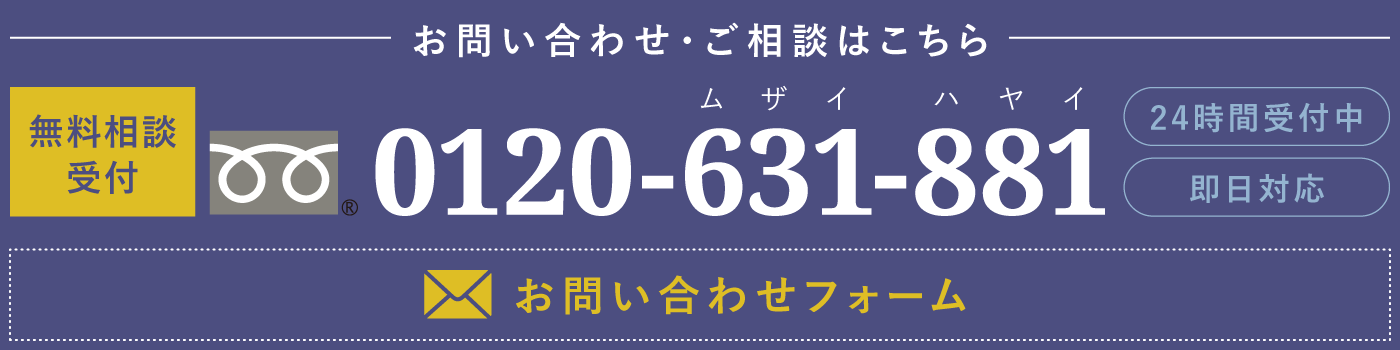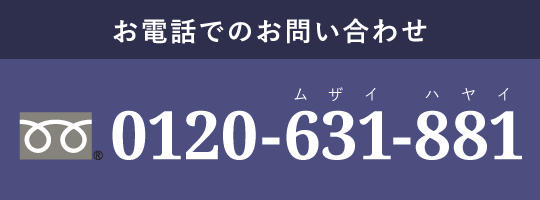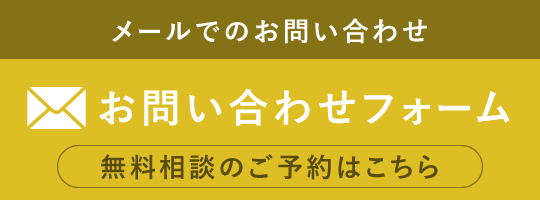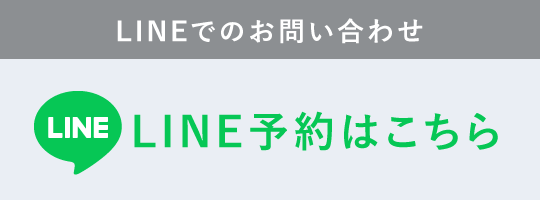このページの目次
国税局の元職員が脱税スキームを指南したとして東京地検特捜部に逮捕された事件報道について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
報道内容
知人の会社の法人税など約5100万円を脱税したとして、東京地検特捜部は6日、法人税法違反容疑で、大阪国税局元職員の会社役員を逮捕した。特捜部は認否を明らかにしていない。
関係者によると、容疑者は脱税スキームを指南していたとみられる。他の企業に対しても同様の手口を伝えていた可能性があるという。
逮捕容疑は、東京都内の不動産会社代表取締役の知人男性と共謀し、有価証券売却によって同社に損失が出たように装うなどして、2020年4月期の所得約2億1100万円を隠し、法人税など計約5100万円を免れた疑い。
(時事通信 令和7年2月6日付記事https://www.jiji.com/jc/article?k=2025020600897&g=socより一部改変)
脱税事件の捜査
刑事事件で捜査というと、警察が行うものという印象が強いと思います。
通常の刑事事件の場合、警察が捜査を行い、捜査を遂げた上で警察から検察庁に書類送検などを行って、検察庁にいる検察官が容疑者を裁判にかけるのかいなか(起訴か不起訴か)を決定していくという流れをたどります。
もっとも、検察官が捜査をできないわけではなく、通常の刑事事件でも検察官が独自に捜査をする場合もあります。
一方、脱税事件では、警察ではなく検察官が最初から捜査を行います。
脱税事件では、国税局が査察調査を行い、刑罰を与えるのが相当であると判断した場合には、検察庁と協議の上で、国税局が検察庁に告発を行います。
告発先は、警察ではなく検察庁という点で通常の事件とは大きく異なります。
告発を受けた検察庁では、特別捜査部(いわゆる特捜部)や特別刑事部(いわゆる特刑)などが捜査を担当します。
地方検察庁は各都道府県に設置されていますが、特別捜査部を設置しているのは東京、大阪、名古屋の3つだけとなっており、特別刑事部を設置しているのは札幌、仙台、さいたま、千葉、横浜、京都、神戸、広島、高松、福岡の10地方検察庁のみとなっています。その他の地方検察庁では一般の刑事事件を担当する検察官が脱税事件も担当することになります。
脱税事件は、国の財源に対する犯罪といえるため、地方公務員である警察ではなく、国家公務員である検察官が捜査を担当することになっており、専門性も高いことから専門部署で捜査を行っていくことになっています。
今回の報道でも、東京地検特捜部が捜査を担当しています。
脱税事件での逮捕
脱税事件に限らず、刑事事件では捜査の手法として逮捕をして身体拘束する場合と逮捕せず捜査をする場合(在宅捜査)の2パターンがあります。
逮捕をするかどうかについては、証拠隠滅の可能性、逃亡の可能性、身体拘束の必要性などから判断されます。
脱税事件の場合には、検察庁が捜査を開始する前に、国税局から査察調査を受けており、査察調査では身体拘束を伴う調査ができないため、査察調査にきちんと対応していれば身体拘束をしなくとも捜査にも協力してくれるだろうと思われることで、逮捕されることはそこまで多くありません。
もっとも、告発を受けた対象者が多数おり共犯者間で主張内容が食い違っていたり、証拠資料を査察調査前に破棄していたりといった場合には、逮捕される可能性が高まります。
今回の報道では、逮捕された理由は明確ではありませんが、容疑者が多数の企業へ指南をしている疑いがあり、関係者多数といえ、口裏合わせなどで証拠を隠滅する可能性が高いと判断されたと考えられます。
元国税局員であることの影響
今回の報道によれば、容疑者は大阪国税局の元職員とのことですので、税金についてはその知識も十分にあり、納税を十全に履行させるために尽力していた職業人であったといえます。
そのため、節税のレベルを超えて脱税を指南したということであれば、職業人として得た知識などを悪用し、国税局員という職に対する信頼もゆるがせたと判断され、一般の方が同じような事件を起こしてしまった場合と比べて、下される処分がより重くなる可能性があります。
当然、現職の国税局職員であった場合には、より重くなると思われます。
脱税事件で捜査を受けたら
脱税事件で捜査を受けることになった場合、起訴されるのは7~8割ほどとなっています。
そのため、裁判を見据えた活動をしていくことが重要です。
たとえば、取調べにおいてどのように供述していくのがよいのか、裁判で有利に働く証拠を作成できないかなど、弁護士に相談しながら準備しておくべきです。
また、逮捕をされている場合には、釈放を目指す活動も弁護士を通じて行っていきましょう。
早めに活動を開始することにより、最終的な結果も納得のできるものとなる可能性が高くなります。