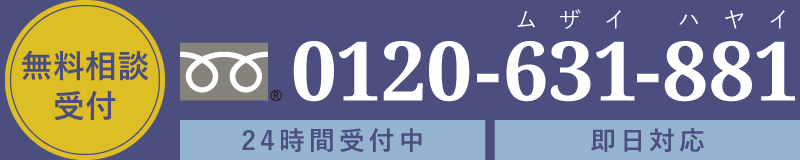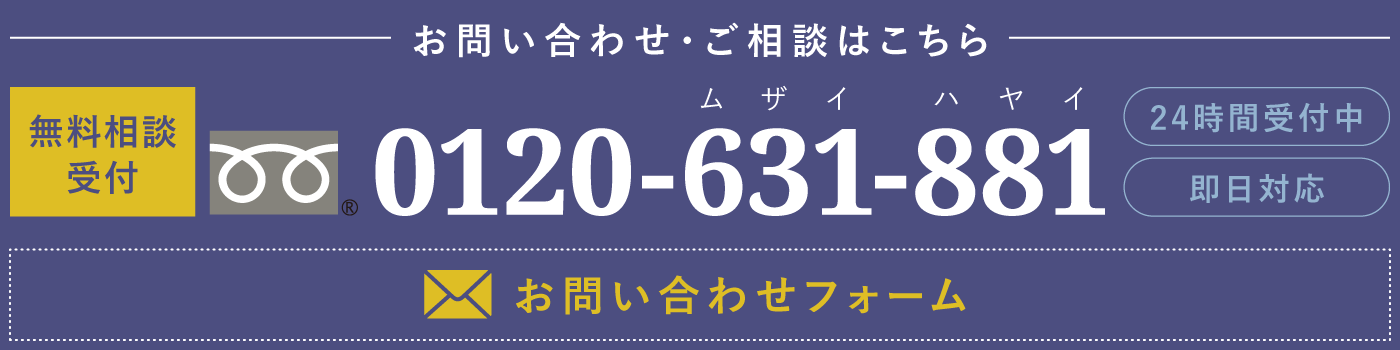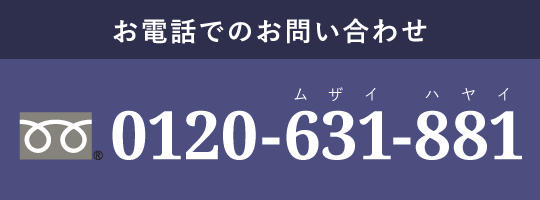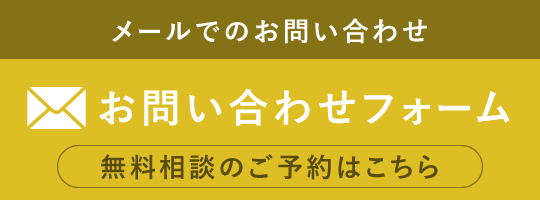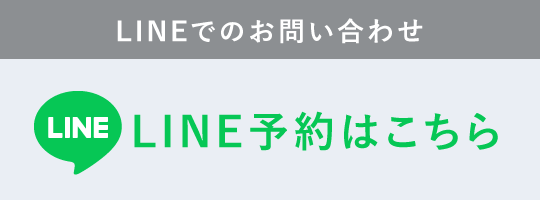このページの目次
前回まで東京国税局が法人税法違反で告発した事例を過去10年間分見てきましたが、今回はそこから見えてくる脱税の手口と傾向について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
脱税の手口
過去10年の告発事例を通じて、脱税の手口は概ね「売上の除外(収入隠し)」と「架空経費・架空原価の計上」に大別できます。建設業や不動産業では下請代金の循環取引や架空発注による原価水増し、IT・サービス業では架空外注費の計上による利益圧縮が典型です。現金商売の業種(クラブ、飲食店など)では売上の一部を現金でプールして申告しない手口も根強く、実際「鬼滅の刃」制作会社の事件ではカフェ売上を金庫に隠匿する古典的手法で多額の所得を隠していました。
告発が多い業種
業種的には、不正が発覚・告発された件数が多いのは不動産業、建設業、クラブ・バー経営などで、2015年度の全国データでも「建設業15件」「不動産業12件」「クラブ・バー7件」が上位を占めました。東京国税局管内でも不動産・建設関連の告発が目立ち、土地取引や受注工事を巡る所得隠しが後を絶たない状況です。一方で近年はIT企業やコンテンツ産業(アニメ制作会社など)も告発事例が散見され、脱税の摘発対象が新分野にも広がっていることがわかります。
脱税額の規模
脱税額の規模について見ると、1件あたりの脱税額は平均で数千万円から1億円程度です。平成27年度には全国平均で約9,700万円(告発分)でしたが、その後若干減少しつつも、おおむね1件あたり1億円前後で推移しています。東京国税局管内では令和4年度の告発事案1件あたり脱税額が9,100万円と全国平均(8,800万円)よりやや高く、首都圏ゆえに金額の大きな悪質事例が多いことを示唆します。実際にここ数年でも脱税額1億円超の案件が複数摘発されており、金額規模の大きな脱税への査察強化がうかがえます。
処分の状況
処分の状況については、東京国税局査察部が告発に踏み切るのは悪質かつ多額の事案に限られるため、告発後は原則起訴(刑事裁判)されています。令和元年度のデータでは告発案件の起訴率は約85%に達し、起訴された場合の有罪率はほぼ100%(執行猶予付き判決を含め、全件有罪)となっています。実刑判決が出るケースもあり、例えば平成27年度に一審判決があった133件のうち2件では実刑判決(懲役刑)が科されています。悪質な法人税ほ脱に厳しい姿勢です。不起訴となるケースは極めて珍しく、東京国税局では1991年以降ほとんど例がありません。
総括
総じて、この10年間で東京国税局管内の法人税法違反による告発事例は「伝統的な手口による脱税の摘発」が中心ですが、告発件数は景気動向や社会状況で増減しつつも概ね毎年数十件規模で推移しています。不動産・建設業等の常連業種に加え、新興業種にもメスが入る傾向が見られ、脱税手口もより巧妙化・多様化していると言えます。しかし、国税当局も近年は消費税の不正還付や国際的租税回避スキームなど時流に即した重点分野に対して調査を強化しており、悪質なほ脱には継続して刑事告発を行う方針が示されています。その抑止効果もあってか、直近では脱税総額自体は一時期より低水準に抑えられています。いずれにせよ、「申告納税制度を揺るがす悪質な脱税者には一罰百戒をもって臨む」という東京国税局査察部の姿勢は一貫しており、今後も様々な業種・手口の脱税事案が告発される可能性があります。適正な申告納税の重要性を再認識させるこれらの事例は、経営者にとって他山の石と言えるでしょう。