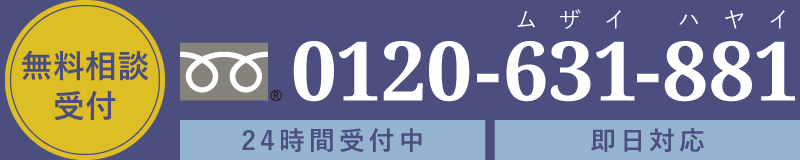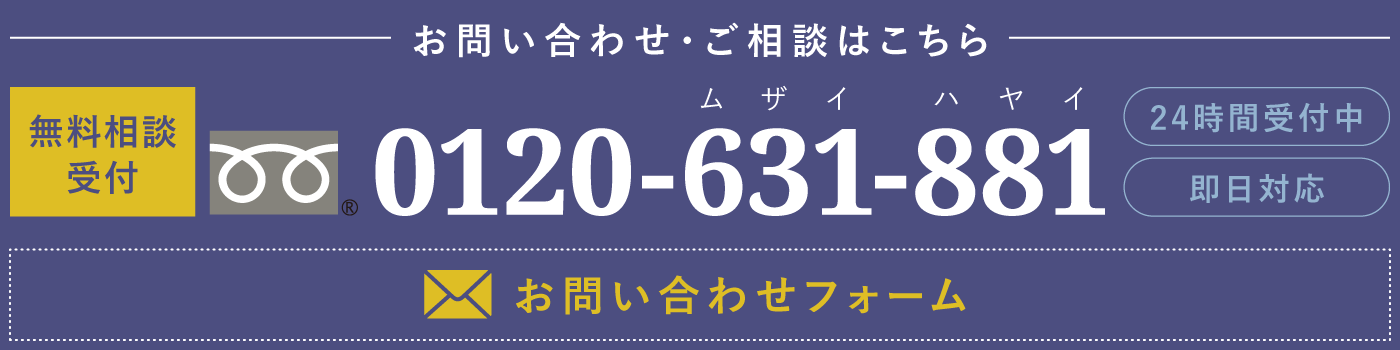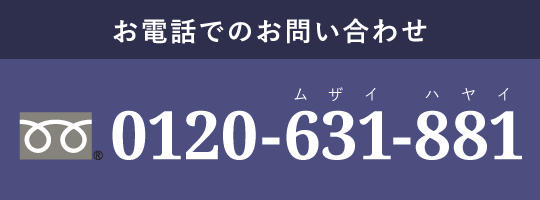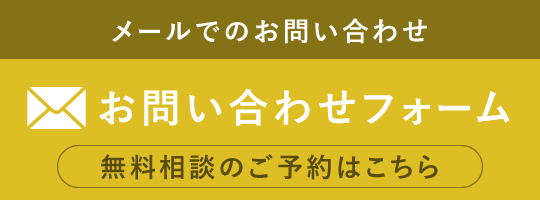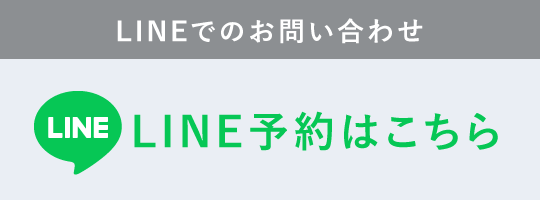このページの目次
所得税法違反で実刑判決を受けた事例を紹介するとともに、実刑判決を避けるためにはどうしたらよいかを弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説していきます。3回に分けて解説していきますので、第1回の今回は所得税法違反の概要と実刑判決に至るポイントを解説します。
所得税法違反の概要
所得税の申告を意図的にせず税金を免れる行為(無申告ほ脱)や、虚偽の申告で所得を少なく見せる行為(過少申告ほ脱)は犯罪であり、悪質な場合には懲役刑(実刑)が科されることがあります。
近年は、自営業者や副業収入を得る個人による所得隠しも増えており、「自分は大丈夫」と油断していると刑事告発・起訴されるケースも少なくありません。
実際、令和5年度(2023年)には脱税事件の有罪判決83件中9件で実刑判決が言い渡されており、実刑となった場合の懲役期間は平均1年3か月(15.6か月)、中には懲役4年の重い判決が下った例もあります。
以下、無申告または過少申告による脱税で実刑に至った主な事例を、判決年月日・裁判所、脱税額、手口の悪質性、判決内容、被告人の属性、反省状況などに着目して紹介します。
脱税で実刑判決に至るポイント(悪質性と量刑の傾向)
脱税事件の量刑は、単純な申告漏れ(過失)か意図的な所得隠し(故意犯)かで大きく異なります。
意図的な脱税が明らかになると、国税局査察部(マルサ)による強制調査を経て検察庁に告発され、刑事裁判で懲役刑・罰金刑が科されることになります。
所得税法では、偽の領収証を用いるなど不正行為による脱税(ほ脱罪)に「10年以下の懲役または1000万円以下の罰金(併科も可)」を、単なる無申告でも故意に納税を免れた場合(単純無申告ほ脱)に「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」を科すと規定しています。
初犯か再犯か、脱税額や手口の巧妙さ、犯行期間、さらには犯行後の対応(修正申告や納税、反省の態度など)によって、執行猶予付き判決になるか実刑(猶予なし)となるかが左右されます。
一般に、脱税額が巨額であったり、長年にわたる計画的な犯行、偽装工作(架空経費の計上や名義口座の利用など)が認められると「悪質性が高い」と判断され、起訴後の対応によっては実刑判決が選択されます。
特に過去に税務指摘を受けても改善せず繰り返した場合や、税理士など専門家ぐるみの組織的犯行では厳罰が下りやすい傾向があります。
一方で、起訴後に速やかに修正申告を行い、脱税分の納税(本税や重加算税)を完納または一部納付した場合や、犯行を認め深く反省している場合には、裁判所が情状を考慮し執行猶予を付すケースも少なくありません。
以下の事例でも、各被告人の悪質性と情状が量刑に大きく影響している点に注目してください。
事例①: FX取引利益を無申告 – 前科執行猶予中の再犯で懲役刑
近年話題となったのが、FX(外国為替証拠金取引)による利益を無申告のまま隠し続け、実刑判決に至ったケースです。
令和4年度の国税庁「査察の概要」にも掲載された事例で、被告人は過去に所得税法違反で有罪(執行猶予付き)となったにもかかわらず、執行猶予期間中に再び多数の他人名義口座でFX取引を行い、その利益について一度も確定申告書を提出しませんでした。
こうした悪質な常習犯である点が重視され、国税当局は告発を決断。裁判所も「所得税の申告納税制度を軽視し、極めて悪質」と判断し、懲役1年4か月の実刑判決を言い渡しました(※罰金刑も併科)。
判決年月日や管轄裁判所は公表資料では明示されていませんが、本件は令和4年中に地裁レベルで言い渡されたものです。
被告人は個人投資家(副業的にFX取引を行っていた者)と思われ、前科がありながら犯行を繰り返した点に強い非難が集まりました。
なお、犯行態様も極めて巧妙で、数十もの口座を使った所得秘匿工作は「偽りその他不正の行為」にあたる悪質性が高い事案といえます。判決においては、被告人に有利な情状はほとんど認められず、執行猶予は付与されませんでした。
~次回は実刑判決になった事例などを紹介します~