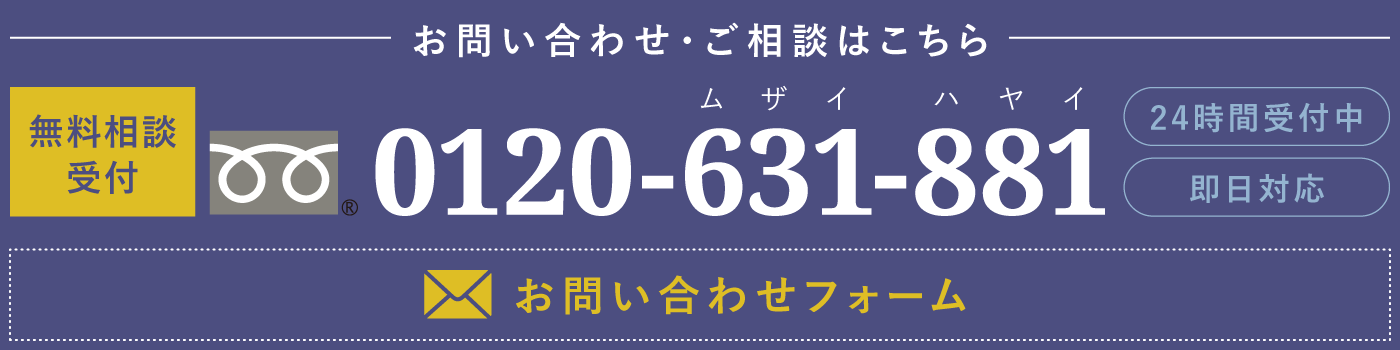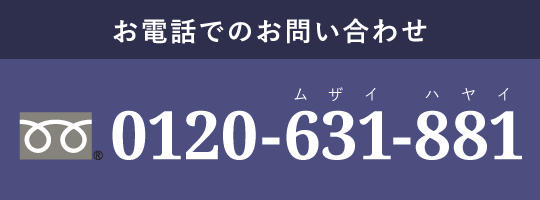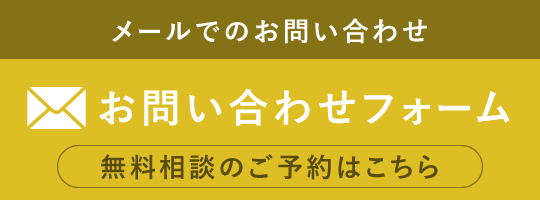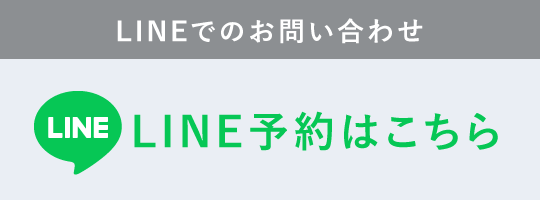Archive for the ‘税法全般’ Category
税務調査の事前通知

税務署から税務調査を実施するとの連絡が来た事例を参考に、税務調査の事前通知に関して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
1 参考事例
東京で飲食業を営むXさんのもとに、新宿税務署から、8月1日午前9時頃より、所得税に関する調査を行う旨の連絡が来ました。
突然の連絡に不安に思い、知り合いから弁護士に相談してみてはどうかと言われ、法律相談に訪れました(事例はフィクションです。)。
2 税務調査における事前通知
税務調査とは、たとえば、確定申告した内容に誤りがないのか、誤りがあるのであれば本来納めるべき税金を納めるようにするために、納税義務者等に対し、質問をしたり、資料の提示・提出を求めたりすることをいいます(国税通則法[以下、「法」といいます。]74条の2以下)。
税務調査を行うにあたって、税務署長等は、税務署職員等に税務調査を行わせる場合には、原則として、あらかじめ、対象となる納税義務者に対し、一定の事項(税務調査を開始する日時や場所、調査の目的や調査の対象となる税目など)を通知するものとされています(法74条の9第1項)。
これは、事前に通知をし、抜き打ち的な調査をさせないことで、税務調査までに準備させる機会を与えようという考え方に基づくものです。
事前通知につきましては、国税庁のホームページも参照してください。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h24/nozeikankyo/ippan02.htm
3 事前通知が来てから税務調査までにできること
管轄の税務署から通知が来た場合、通知を受けた側としては、次のようなことをすることが考えられます。
まず、通知において日時が指定されるわけですので、業務や私生活に支障が出ないように、スケジュールを調整することが考えられます。
場合によっては、税務署に対し、日程を別の日に変更してもらうように相談することも考えられます。
また、帳簿等の準備をすることも重要です。
当たり前かもしれませんが、仮に、脱税をしており、事前通知があったからといって隠蔽工作をする機会をもらったわけではありません。
しかし、調査がスムーズに実施されるように、提示が求められそうな資料をまとめておいたり、こちらから説明する際に必要な資料を準備しておくことは重要です。
さらに、そうした準備とも関係しますが、税理士などの税務代理人がいない場合には、税務代理人を就けたり、税務調査に立ち会わせたりすることも考えられます。
税務調査の事前通知は、一定の場合には、納税義務者ではなく、税務代理人に対して行えば足りるとされています(法74条の9第5項)ところ、参考事例においては、Xさん本人に通知があり、まだ税理士などがいないことが想定されます。
税務調査において、税務署側に、適切な説明を行うことで、あらぬ疑いをかけられることを防ぐことができます。
このとき、より法律的な説明が必要になる場合には、税理士ではなく弁護士(あるいは両方)をつけ、税務調査に対応していくということが考えられます。
4 最後に
ここまで説明してきたように、税理士や弁護士を税務調査に関与させていくということが考えられます。
しかし、そもそも、仮に脱税をしてしまっていた場合において、今後、どのような手続が予想されるのか、税務調査で終わらず刑事裁判となる可能性があるのか、そうした可能性があるとしてもどのような対応をしていくか、早い段階でアドバイスを受けておくというのも重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、脱税事件に強い弁護士が所属し、多数の脱税事件を取り扱っています。税務調査の事前通知が来た、脱税をしたかもしれない、国税庁から告発され刑事事件化するかもしれないと不安に感じていらっしゃる方は、初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
税務調査と予納制度

税務署による税務調査を受けている際に使うことのできる予納制度について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
税務調査と修正申告
所得税や法人税の確定申告内容に誤りがないかどうかを確かめるために、税務署は数年に1回ほどの頻度で税務調査を行います。調査の結果、申告内容に不備があることが発覚した場合は、本来納めるべきはずの税金を納付しなければいけません。
既に確定申告期限が過ぎている場合は、修正申告を行うことになります。本税の他にも、期限までに税金を納付しなかったことへのペナルティとして、附帯税も課せられます。附帯税には加算税(過少申告加算税や重加算税など)や延滞税といったものがあります。
延滞税とは
延滞税とは、期限までに税金を納めていなかった場合に、法定納期限の翌日から実際に納付を行った日までの日数に応じて課せられる附帯税の一種です。延滞税の割合は、法定納期限の翌日から2ヶ月を経過しているか否かで変わってきます。
延滞税は、本税を基準に納付が行われるまで課せられるため、納税者にとって大きな負担となる場合があり得ます。
予納制度とは
先ほども述べたとおり、通常は修正申告を行ってから本税や附帯税を納めることになります。もっとも、修正申告までに時間を要してしまえば、その分だけ延滞税の負担も大きくなっていきます。また、既に国税局による査察調査に移行している場合は、強制調査によって関係資料が押収されてしまい、修正申告をしようにもできないこともあり得ます。
このような場合に役に立つのが予納の制度です。予納とは、納付すべき税額の見込額を税務署長に申し出て、あらかじめ納付することを指します。予納は修正申告を行う前にも可能なため、修正申告を行うまでに時間を要する場合や、手元資料の関係で修正申告が困難な場合にも行うことができます。
予納を行う際は、国税の予納申出書に必要事項を記載して所轄税務署に提出し、納付を行うことになります。予納申出書については、国税庁のホームページでも紹介してありますので、そちらもご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/zeirishi/annai/pdf/0019011-087_03.pdf
予納による延滞税の負担軽減
延滞税は税金を納めるまで課せられるため、予納制度により早期に納付を行えば、延滞税の負担を最小限に抑えることができます。税務調査官の方から予納を促されることもありますが、延滞税の負担を軽減する大きなメリットがあるため、納付できる現金が手元にある場合は、積極的に予納制度を用いて早期の納付を行っていくことが重要です。
予納制度と刑事事件の関係
予納制度を利用するもう1つのメリットに、刑事事件化を抑止する事情の1つになることが挙げられます。刑事事件化とは、税務署による税務調査や国税局による査察調査だけでは済まず、国税局によって検察庁に刑事告発をされた場合を指します。
刑事告発をされてしまうと、脱税事件という刑事事件として扱われることになるため、逮捕や勾留によって身体拘束がされるおそれもあります。検察庁によって起訴された場合は、刑事裁判を受けることになります。脱税事件が起訴された場合の有罪率は100%なため、起訴をされてしまうと、懲役刑や多額の罰金が科せられることになってしまいます。
予納制度を利用して税金の納付を行うことは、刑事事件化を回避するうえで有利な事情の1つとなりえます。国税局による告発や検察庁の起訴を行うか否かは、主として脱税額や脱税スキームの悪質性で判断されますが、納税者の姿勢も考慮されます。実際に、脱税事件の刑事裁判の量刑理由においても、修正申告の有無や本税、附帯税の納付が済んでいるかは考慮されています。
予納により早期の納付を行うことは、好ましい納税者の姿勢として、有利な情状として考慮されます。ケースによっては、告発や起訴そのものを回避できることもありますし、起訴されるにしても、その範囲が縮小されることもあります。
早期に弁護士へ相談を
ここまで述べたとおり、予納制度は延滞税の負担軽減や刑事事件化の回避を目指すうえで重要な手段の一つといえます。
もっとも、予納によってどの程度まで刑事事件化を回避できるかを自力で正確に判断するのは困難です。そのため、予納制度の利用を検討している場合は、税理士だけでなく弁護士にも相談をしておくことが肝要です。
【制度解説】企業会計と税務会計(法人税法22条)

公正処理基準について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説
1 はじめに
法人税法22条は、法人の所得計算に関する基本的な規定であり、4項には、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」によって計算されるものと規定されています。この公正処理基準の意義、制度趣旨、問題点、裁判例についてみていきましょう。
2 意義と制度趣旨
法人税は、国の税収のうち、所得税、消費税とともに国の財政収入の根幹を担うことから、当然のように公明正大な処理がなされなければなりません。
具体的には、企業会計と税務処理が連動して円滑な処理がなされるよう両者の連携が図られること、明確な一定の基準に従った企業会計の処理により、税務調査、税務査察の際に国税当局との間に生じるおそれのある争いをできるだけ少なくし、税務行政の効率化を最大限に引き出すこと、社会のグローバル化に従い企業会計の国際化に資することで、企業の海外取引や海外への展開を促進し企業自体のグローバル化を円滑に実現すること、といった要請があります。
これらはいずれも税金の計算を目的とする税務会計と、企業の資産状況を報告する企業会計とのズレを可能な限り少なくし、税と資産をその金額面において正確かつ明朗に計算できるようにするのが目的であり制度の趣旨です。
3 公正処理基準の問題点
公正処理基準には抽象性から次のような問題性があります。
多種多様な企業の会計処理に普遍的に妥当させようとすることから、いきおい基準自体が「一般に公正妥当」(法人税法22条4項)という定め方をせざるを得ないことから、規定自体の抽象性や具体的な判断基準が不明確なため、会計処理の具体的金額の特定に関し、解釈の余地が生じることとなります。当然、企業は税額の少なくなるような会計処理をし、税務当局はこれに反する立場をとることから解決困難なアポリアを生じることも少なくなく、その解決のために最終的には訴訟による決着を待つことになります。
4 裁判例
公正処理基準に関する裁判例は数多く存在し、次のような例があります。
交際費に関し、①支出の相手方が、事業に関係ある者等であり、②支出の目的が親睦の度を密にして取引関係を円滑な進行を図るものであることとともに、③接待、供応、慰安、贈答に類する行為であることの三要件が必要であるとした例(平成15年東京高等裁判所判決、萬有製薬事件)
株式償却により、償却株式が譲渡されたその評価額を収益として計上することは、当然の帰結であり、払戻限度超過額を収受することが、旧商法上許されないとしても直ちにその収益性を否定することはできないとした例(平成26年東京高等裁判所判決、日産自動車事件)
以上は企業と税務当局とのし烈な争いの結果出された判決です。いずれも今後の税務会計の具体的基準として先例拘束性があると考えられるため、同種の会計処理に当たっては留意が必要となります。
5 まとめ
企業会計における公正処理基準は、法人税法における重要な概念であり企業会計と税務会計の連携を図る上で不可欠な役割を果たしています。
税務処理に当たっては、先例の有無に留意するとともに、公正を旨とし疑義を生じたときには税務査察の任意手続段階おいてなど、税務当局との折衝により妥当な解決を得られる場合があります。これは、その時点で折り合わずに訴訟まで発展するなどの負担をコストの大幅削減にもなるなど迅速な解決に向かわせる方法として有効となりますし、税法上のペナルティも回避可能となるなどその機能が期待されるものといっていいでしょう。
中小企業と知的財産権の税務

知的財産権は、中小企業にとって、自社の技術やブランド力を保護し、競合他社との差別化を図る上で非常に重要な資産です。しかし、特許を取得したり、商標登録を行ったりする際には、様々な税務上の問題が伴います。このブログでは、中小企業の経営者が知っておくべき、知的財産権に関する税務の基礎知識を解説するとともに、より実践的な視点から、税金対策や経営戦略に役立つ情報を提供します。
特許を取得する際の税金
(1)研究開発費の税制優遇
研究開発税制の活用: 研究開発税制は、企業の研究開発活動を促進するために設けられた制度です。中小企業は、この制度を活用することで、法人税額から一定割合の控除を受けることができます。
優遇を受けるための要件: 研究開発費の定義や、控除を受けるための要件は複雑です。税理士と連携し、自社の研究開発活動が制度の対象となるか、どの程度の控除が受けられるかなどを事前に確認することが重要です。
その他の優遇措置: 研究開発費の損金算入の繰延べや、特許取得にかかる費用の一部を損金算入できる制度など、様々な優遇措置があります。
(2)特許取得費用
無形固定資産としての計上: 特許取得費用は、無形固定資産として計上され、その耐用年数に応じて償却していきます。
耐用年数の設定: 特許の存続期間だけでなく、その特許の経済的耐用年数を考慮して、適切な耐用年数を設定することが重要です。
償却方法: 定額法や定率法など、様々な償却方法があります。自社の状況に合わせて最適な方法を選択しましょう。
(3)特許権の譲渡
譲渡所得の課税: 特許権を譲渡した場合、その対価は譲渡所得として課税されます。
譲渡所得の計算: 譲渡所得は、譲渡対価から取得費を控除して計算されます。
特許権の評価: 特許権の評価は、専門的な知識が必要となります。税理士に相談し、適切な評価額を算定してもらいましょう。
商標登録にかかる税金
無形固定資産としての計上: 商標登録費用も、無形固定資産として計上され、特許権と同様に償却していきます。
商標権の評価: 商標権の評価は、特許権と同様に専門的な知識が必要となります。
商標権の利用による収入: 商標権を利用して、ライセンス料やロイヤリティ収入を得た場合は、その収入は事業所得として課税されます。
知的財産権の利用による収入と税金
事業所得としての課税: 特許権や商標権を利用して得られるライセンス料やロイヤリティ収入は、事業所得として課税されます。
事業所得の計算: 事業所得は、収入から必要経費を控除して計算されます。
必要経費の範囲: 必要経費には、人件費、賃借料、消耗品費など、事業を行うために直接的に必要となる経費が含まれます。
知的財産権に関する消費税
課税仕入れ: 知的財産権の譲渡や使用権の許諾は、原則として課税仕入れに該当し、消費税が課税されます。
非課税取引: 一定の要件を満たす場合は、非課税取引として消費税が課税されないことがあります。
免税取引: 小規模事業者など、一定の要件を満たす場合は、免税取引として消費税が課税されないことがあります。
中小企業が知っておくべきこと
税制の複雑性: 知的財産権に関する税制は複雑で、常に変更される可能性があります。
専門家への相談: 税務に関する専門家(税理士など)に相談することが大切です。
記録の保存: 経費に関する書類は、税務調査に備えて大切に保管しましょう。
税制優遇の活用: 研究開発税制などの税制優遇制度を積極的に活用しましょう。
国際的な税務: 海外で知的財産権を利用する場合、国際的な税務についても考慮する必要があります。
まとめ
中小企業が知的財産権を活用するためには、税務に関する知識をしっかりと理解しておくことが重要です。税制は複雑ですが、適切な手続きを行うことで、税負担を軽減し、事業の発展に繋げることができます。税理士などの専門家と連携し、自社の状況に合わせた最適な税務対策を検討しましょう。
【制度解説】定額減税について

定額減税について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
1制度の概要
定額減税は、一定額を所得税額から控除するという制度です。これは、物価高騰による国民生活への影響を緩和し、経済活動を活性化させることを目的としています。所得税法、地方税法が改正され、令和6年6月から実施されることとなりました。
2対象者、減税額
年間所得が、一定額(原則1805万円以下、給与収入のみの場合2000万円以下)以下の個人を対象としています。団体や法人は対象となりません。
減税額は、納税者及びその配偶者または扶養親族1人につき、原則として年間4万円(所得税3万円、住民税1万円)です。
3制度の趣旨はおおむね3つ
①物価高騰対策: 近年、世界的な物価高騰が続いており、家計への負担が増大していま
す。定額減税は、この物価高騰による家計への圧迫を軽減し、国民生活の安定に寄与
することを目的としています。
②経済活性化: 税負担を軽減することで、個人の消費意欲を高め、経済活動を活性化さ
せる効果が期待されています。
③所得格差の是正: 低所得層ほど、物価高騰の影響を強く受けやすいため、定額減税
は、所得格差の是正にも貢献すると考えられています。
4いつまで継続するのか
では、定額減税はいつまで続くのでしょうか。
現時点では、定額減税の制度がいつまで継続されるのかは明確にされていません。一般的に、このような税制上の優遇措置は、経済状況や社会情勢の変化に応じて、その期間や対象が変更されることがあります。
5家計への影響
定額減税は、一定の所得以下の個人に対して、所得税額が減額されるため、手取り額が増えることになります。これにより、消費意欲が高まり、経済活動が活性化することが期待されています。
国民経済の安定と好況の維持が期待されることから、家計へ潤いを与え生活への活力が生じやすくなります。
6今後の展望
経済的弱者(低所得者層)への支援を強化し、所得格差を是正することが実質的な社会生活上の平等実現にとり重要であり、国民への給付行政の円滑化を図ること、そのため、課税行政が一般に法律による必要があるところ、生き物といわれる国の経済情勢や社会状況の変化に応じて、迅速な立法等による税制の柔軟な運用の要請があることとを両立し、他方で税収減による財政面との均衡点を模索するといった国政上の現実的問題
をクリアする政策の実現が急務となります。
7一提言
国民一般にとり、減税は歓迎すべき制度といえるでしょう。他方、経済のグローバル化が急速に進み、一般家庭の家計においても、ドル円の為替レートの影響を受ける昨今において、今後は、国際経済の流れに乗り、税制をも踏まえた上手な所得の管理が必要となることでしょう。皆様の家庭に定額減税の恩恵がもたらされんことを。
節税、租税回避行為、脱税の違い

節税、租税回避行為、脱税の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
節税とは
節税とは、税法が予定している通常の契約形態ないし法形式等を使うことにより、したがって、法の趣旨・目的に反することなく税負担の軽減を図る行為です。たとえば、必要経費を適切に計上するなどして税金を減らすことは、税法によって認められた行為ですので節税にあたり問題ありません。むしろ、余分な税金を支払えば資金繰りに窮してしまうことにもなりかねず、節税は積極的に行っていくべきものです。
租税回避行為とは
租税回避行為とは、私法上有効な契約形態ないし法形式等を選択することによって、税法が定める課税要件を充足する事実を回避する行為をいいます。
後で説明する脱税が、課税される要件がありながらこれを隠す行為であるのに対して、租税回避行為は、課税要件となる事実の隠匿は行っていないが、法の趣旨・目的に反して税負担の軽減を図る行為です。
この点、税の世界はあくまで「租税法律主義」、すなわち法律に定められていないのに税を徴収されることはないというのが大前提です。
たとえば、かつては海外にある財産を海外居住者へ贈与する場合、贈与税がかかりませんでした。その時代に、受贈者を海外に住まわせた上で国外財産を贈与し、贈与罪を免れた事案において、最高裁は租税法律主義のもと、国の追徴課税処分を取り消しました(最高裁平成23年2月18日判決)。
憲法30条は、国民は法律の定めるところによってのみ納税の義務を負うと規定し、同法84条は、課税の要件は法律に定めなければならないことを規定しています。納税は国民に義務を課するものであるところからして、この租税法律主義の下で課税要件は明確なものでなければならず、これを規定する条文は厳格な解釈が要求されるのです。一般的な法感情の観点からしますと違和感もあるでしょうが、租税法律主義に則った最高裁のこの判決はやむを得ないものと言えるでしょう。もっとも、租税回避行為は、租税法律主義を形式的に適用する限りでは許容されるとしても、法の抜け穴を突いて、課税を免れようとする行為です。公平な課税の観点から問題とされるグレーゾーンに位置する行為とされ、お勧めできるものではありません。
脱税とは
脱税とは、課税される要件があるにも関わらず、これを故意に隠して、課税を免れようとする行為をいいます。
例えば、売上を意図的に除外したり、架空の経費を計上するなどにより、所得を圧縮する行為は脱税です。
この点、所得税法は「偽りその他不正の行為」により所得税を免れ、または所得税の還付を受けた者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると規定しています(所得税法238条1項)。その他の税目にも同様の規定があります(法人税法159条1項、相続税法68条1項、消費税法64条1項等)。
このように脱税は刑事罰の対象となり、国税局査察部が調査(犯則調査)を行います。脱税は違法行為なので完全にアウトの行為といえます。
脱税と重加算税の関係
納税者が「隠蔽又は仮装」を行った場合には重加算税が賦課されます(国税通則法68条)。この点、「偽りその他不正の行為」と「隠蔽又は仮装」とは大部分が重なり合うものと考えられています。したがって、脱税として刑事罰の対象となり処罰されるときには、重加算税を課された上で処罰されるのが通常です。
最後に
申告・納税しなければならないのにしていない方は、早めに税理士や弁護士といった専門家に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を中心として扱っていますが、税法についても知識のある弁護士がそろっています。 初回の相談は無料ですので、一度ご相談にお越しください。
【国税庁発表】令和5年度査察の概要

国税庁が発表した令和5年度査察の概要について、要点は以下のとおりです。
査察の概要とは
「査察の概要」は、毎年国税庁が前年度の査察調査に対する取り組みや実績を報道発表するための資料として作成されているものです。
査察調査の件数や検察庁に告発した件数、起訴された事件での有罪事案の紹介、不正資金の留保・費消状況及び隠匿場所、告発の多かった業種などがまとめられています。
また、査察調査を行った事案については、その一部について事例付きで紹介されています。
令和5年度査察調査の概要は令和6年6月21日に公表されました。
令和5年度査察の概要
令和5年度の査察調査の概要としては、
1 査察の処理件数は151件、検察庁に告発した件数は101件、脱税総額(告発分)は約89億円
悪質な脱税者に対して厳正な査察調査を実施、1件当たりの脱税額は8800万円。令和4年度と比較して、告発件数及び脱税総額ともに微減し、告発率66.9%で平成18年以来の高水準だった前年度より7.2ポイント減少したが、引き続き高水準
2 消費税事案、無申告事案、国際事案のほか、社会的波及効果が高い事案を告発
3 一審判決83件全てに有罪判決が言い渡され、9人に対して実刑判決
実刑判決のうち、査察事件単独で最も重いものは懲役4年、他の犯罪と併合されたものは懲役6年
という3項目が紹介されています。
重点事案への取り組み
重点事案への取り組みとして、以下の内容が紹介されています。
① 消費税事案
消費税に対する国民の関心が極めて高いことを踏まえ、27件を告発
消費税の仕入税額控除や輸出免税制度を悪用した不正受還付事案は、いわば国庫金の詐取ともいえる悪質性の高い事案であることから、16件を告発
② 無申告事案
納税者の自発的な申告・納税を前提とする申告納税制度の根幹を揺るがす無申告事案について16件を告発。
そのうち、不正行為はないものの、故意に申告書を提出しないで税を免れた単純無申告ほ脱事案は11件
③ 国際事案
経済社会のグローバル化の進展に伴い、国境を超える取引が恒常的に行われ、資産の保有、運用の形態も複雑・多様化しているところ、国際取引を利用した脱税への対策が求められている。このような状況の中、外国法人を利用して不正を行っていた事案や海外に不正資金を隠していた事案などの国際事案で23件を告発
④ その他の社会的波及的効果の高い事案
脱税のために虚偽の経費を計上するスキームを節税とうたって、広く納税者を勧誘し、納税者らが当該スキームを利用して法人税及び消費税を免れていた事案、インターネット上の物品の転売やそのノウハウの指南を業とする者が、架空の経費の計上や売上を除外することで、自身の所得税及び主宰法人の法人税を免れていた事案、半導体製造工場の建設が盛んな地域における工場内設備工事事業者が、架空の経費を計上することで、法人税及び消費税を免れていた事案などを告発
不正資金の留保・費消状況及び隠匿場所
脱税によって得た不正資金の多くは、現金や預貯金として留保されていたが、脱税者が数千万円規模の費消をしていた事例も見られ、その使途としては、高級車両の購入、有価証券等への投資、暗号資産の購入などが見られた。
脱税によって得た不正資金の隠匿場所としては、天井裏、階段下収納、蔵に置かれた木箱などに現金を隠していた事案があった。
その他参考計表
① 税目別の告発件数
所得税14件、法人税59件、相続税1件、消費税27件
② 告発の多かった業種
1位:不動産業 18業者、2位:建設業 16業者、3位:人材派遣業 6業者、4位:小売業 5業者
建設業、不動産業はここ数年1位、2位を占めており、取り扱う金銭の額が多いことからも査察調査で狙われやすい業者といえます。
申告・納付をしないと多くの税金を払わないといけなくなる

確定申告や税の納付をしない場合に、ペナルティとしてどのような税金を支払う必要があるのかについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
1 附帯税とは
確定申告や税の納付をしない場合、本来納めるべき税(これを本税といいます。)のほかに、ペナルティとして附帯税を納める必要があります。
附帯税とは、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税のことをいいます(国税通則法2条4号)。
なお、このうち、利子税は、ペナルティというよりは、利息のような性質をもつものですので、延滞税と各種加算税がペナルティに当たります。
2 加算税とは
加算税とは、法律で定められた期限内に適正な申告や納付がなされない場合に、本税に加えて賦課されるものです(申告や納付をしなかったことに対するペナルティ)。
法律で定められた期限内に申告はなされたものの税額が過少であった場合に過少申告加算税、申告しなければならない国税でありながら申告すらしなかった場合に無申告加算税、法律で定められた期限内に納付がなされなかった場合に不納付加算税が課されます。
また、そうした申告や納付をしなかった場合において、隠蔽や仮装がある場合に、それぞれの加算税に代えて、さらに重い税率となっている重加算税が課されることになります。
3 加算税が免除されたり減額されたりする場合がある
こうした加算税は、「正当な理由」があるときには、免除されます。
この「正当な理由」は、かなり限定されていて、単に、自身が申告や納付をすべき立場にあったことを知らなかったとしても、「正当な理由」があるわけではありませんが、申告や納付をしなかったことについて、何かしら理由がある場合には、手続の段階にもよりますが、税務署等に交渉していくことが考えられます。
また、そうした「正当な理由」がない場合であっても、調査による更正の予知なくして申告や納付をした場合には、免除されたり、納付すべき加算税が原則的な金額から減額されたりします。
調査による更正の予知なくして申告や納付をする場合とは、簡単にいえば、税務調査を受け、申告や納付をすべきであると指摘されそうな立場になる前に、自発的に申告(修正申告など)や納付をする場合です。
最終的には、事案ごとに個別に判断していくしかないですが、申告をすべきかどうかわからない、本来納付すべき税金を納付していないなど不安がある場合には、早い段階で、弁護士や税理士に相談することが必要になってきます。
また、ここで詳しく説明はしませんが、仮に、脱税をし、刑事事件化した場合においても、修正申告をしたかどうかなど一定の事情は、刑事事件においても考慮される対象になってきます。
4 延滞税とは
延滞税とは、法律で定められた期限を過ぎても国税を納付しない納税者に課されるもので、遅延損害金(遅れたことに対するペナルティ)としての性質を持っています。
延滞税にも、加算税とは内容が異なりますが、一定の場合に免除されることになっています。
また、延滞税については、本来納付すべき税金を納付することによって発生しなくなるものですので、こちらも加算税と同様、早い段階で、今後の対応を考える必要性が高いです。
5 最後に
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、脱税事件に強い弁護士が所属し、所得税法違反など多数の事件を取り扱っています。脱税をしたかもしれない、税務調査を受けることになった、国税庁から告発され刑事事件化するかもしれないなど不安に感じていらっしゃる方は、初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
税務調査において黙秘することは許されるのか

税務調査を受けた際の対応、特に、税務署職員等からの質問に対して何も話さないということが許されるのかどうかという点について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
1 税務調査とは
税務調査とは、国税庁、国税局若しくは税務署又は税関の当該職員が、所得税、法人税、地方法人税又は消費税に関する調査について必要があるときに、一定の者に質問したり、事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、その提示・提出を求めることをいいます(国税通則法74条の2)。
所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税の調査において、実際に税務調査を行うのは、基本的に税務署職員です。
税務調査の対象となる者については、たとえば、所得税に関する調査においては、納税義務がある者(あると認められる者等を含む。)だけではなく、取引関係者も含まれます。
納税義務がある本人に対する調査を本人調査といい、取引関係者など本人以外に対する調査を反面調査といいます。
2 黙秘することはできない
税務調査においては、納税義務がある本人やそれ以外の者に対し、調査に必要な質問がなされます。
たとえば、帳簿上、雑費として計上されているものの、それに対応する領収書がない場合、どのような取引なのか、領収書があるのかないのか…などです。
それに対して、経費として認められない、私的な費消だったとしても、領収書がない以上、話しをしなければ、難を逃れることができるのではないかという思いが、頭をよぎることもあると思います。
また、日本国憲法においては、「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」とされ、いわゆる黙秘権が保障されているので、自身に不利なことを話す必要はないのではないかという思いを抱く人もいると思います。
しかし、結論からいえば、税務調査において、自身に不利な事項だったとしても、黙秘することは許されません。
国税通則法128条2号においては、税務調査における、税務署職員などの「質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施を拒み、妨げ、若しくは忌避した者」は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するとされています。
3 税務調査は任意ではないのか、求められる対応とは
税務調査は、裁判所の令状が不要であることから、刑事手続における逮捕や捜索差押えなどの強制処分ではなく、任意として行われるものです。
もっとも、先ほど説明したように、税務署職員による質問に対し、答弁をしない、つまり黙秘することによって、別途刑罰を科されるおそれがあることから、事実上(間接的であれ)強制的な側面があることも否定できません。
ですので、税務調査の場面において、必要な説明は、適宜していく必要がありますし、それに伴う資料の提示なども必要になってきます。
税務調査においては、依頼している税理士に立ち会ってもらうこともありますが、弁護士を立ち会わせて、適切な説明をしていくということも有益となってきます。
また、税理士のみを立ち会わせるとしても、税理調査における対応に十分な経験がある方が、より適切な対応をすることができるともいえます。
さらに、仮に、脱税をしているということになった場合には、その先の対応まで必要になってきます。
4 最後に
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、脱税事件に強い弁護士が所属し、所得税法違反など多数の事件を取り扱っています。税務調査を受けることになり、税務調査での対応や、刑事事件化する可能性があるのかどうか、今後のことを不安に感じていらっしゃる方は、初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
税務調査において事前通知が行われない場合(無予告調査)

税務調査において、事前通知が行われない場合もあるのでしょうか、また、その場合、どう対処すべきでしょうか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
税務調査は断れない
納税者の中には、税金を払う必要があるのに全く納税申告をしていない人、あるいは申告はしているものの正しい申告をしていないおそれのある人がいます。課税庁には、こうしたケースの場合、必要に応じて、納税者などに対して質問をし、帳簿書類などを検査する権限が与えられています。このように課税に必要な質問や検査をすることを税務調査といいます。
国税通則法第74条の2~6は、このような質問検査権を定めており、また、同法128条は、質問に対する不答弁、検査の拒否・妨害等については、刑罰が科されることを定めています。したがって、税務調査自体を断ることはできません。
課税庁は、この権限に基づき企業における契約関係や資金の流れ等について詳細な調査を実施することから、本来は、法人税等の課税目的で行われる調査であるにもかかわらず、この調査の過程で、脱税事案のみならず、役職員による横領・背任・詐欺、贈賄等の他の不正行為が発覚することもあります。
事前調査なしの税務調査(無予告調査)
税務調査が行われる場合、課税庁は、納税義務者に対し、あらかじめ、調査を開始する日時・場所、調査の目的、調査の対象となる税目、調査の対象となる期間等を通知しなければならないとされています(国税通則法74条の9・1項)。このように、税務調査が行われる場合には、課税庁から事前連絡があるのが原則です。
しかし、事前連絡なしで、いきなり会社や店舗に調査官が訪れるケースもあり得ます。このような税務調査を無予告調査といいます。無予告調査は、一般的に現金商売の会社に入りやすいと言われています。たとえば現金商売の場合、事前に通知をすることで、その時だけ現金の調整をされてしまうと、税務調査に出向く意味がなくなってしまうからです。
この無予告調査は、法律で認められている調査であり(国税通則法74条の10)、国税庁が出している税務調査手続きに関するFAQ(一般納税者向け)には、「法令の規定に従い、申告内容、過去の調査結果、事業内容等から、事前通知をすると、違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれ、又は、その他、調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると判断した場合には、事前通知をしないこともあります。なお、事前通知が行われない場合でも、運用上、調査の対象となる税目、課税期間や調査の目的などについては、臨場後速やかに説明することとしています。」と記載されています。
このように、「事前通知なしの税務調査もあり得る。」ということは頭に入れておく必要があります。
無予告調査の日程変更は場合により可能である
税務調査自体を断ることはできませんが、法律上、やむを得ない事情があれば、日程の変更は可能です(国税通則法74条の9・2項、国税通則法第7章の2(国税の調査)等関係通達5-6)
ここでいう「やむを得ない事情」とは、典型的には、経営者や経理担当者の入院、家族の葬儀などが該当しますが、「顧問の税理士(あるいは、税法に精通した弁護士)に税務調査の立会を依頼しているが、その人の日程と会わないので今日はその人が立ち会えない。」「調査対応する税理士(あるいは、税法に精通した弁護士)を探す時間が欲しい。」などという事情もやむを得ない事情となり得ると考えられます。
調査のプロである調査官といえども、調査官が言うことが全て正しいとは限らず、事実認定や税法の解釈を誤っていることもあり得ます。このような場合、税務の専門家が立ち会っていれば、事実認定や税法の解釈について適切に反論してもらうことができるなどのメリットがあり、このような反論により税務調査の結果が大きく変わることもあります。
顧問税理士等と無予告で税務調査が入った場合の対処法をあらかじめ話し合っておくのもよいでしょう。
最後に
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を中心として扱っていますが、税法についても知識のある弁護士がそろっています。初回の相談は無料ですので、一度ご相談にお越しください。
« Older Entries