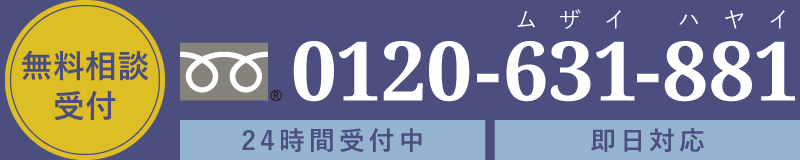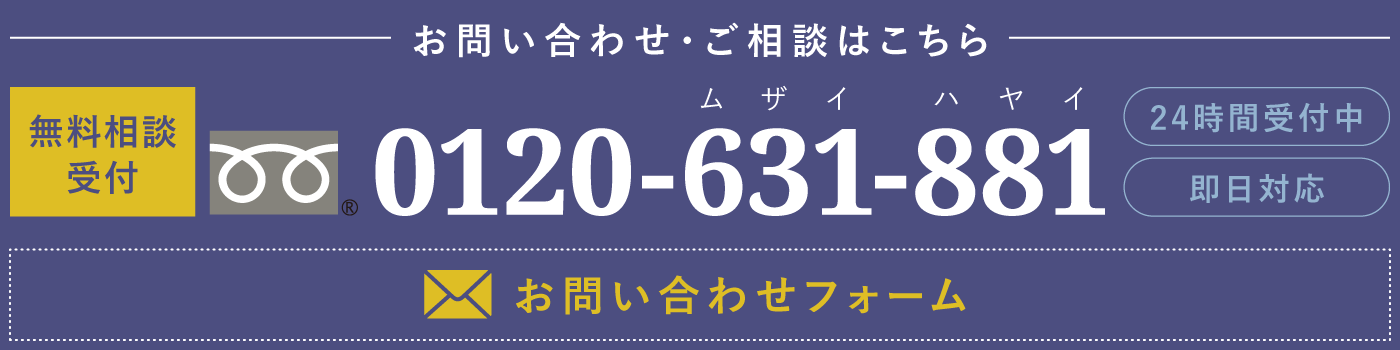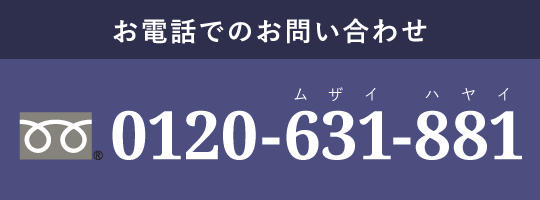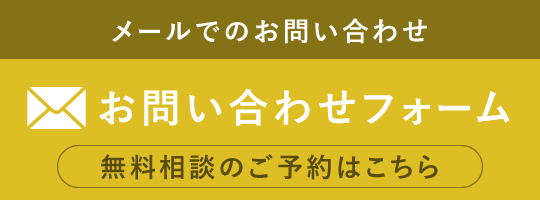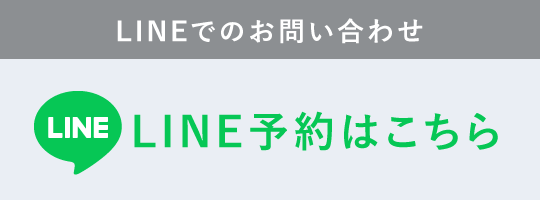Archive for the ‘所得税・法人税’ Category
飲食店における源泉徴収漏れ

飲食店において源泉徴収漏れが発覚した場合のリスクについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
源泉徴収とは
源泉徴収とは、企業が従業員の給与から所得税に当たる部分を差し引いて、企業が従業員の代わりに所得税を国に収める制度のことを言います。
源泉徴収制度の目的は、従業員の所得税の申告漏れを防ぐことにあります。
企業に勤めている従業員の方は、この源泉徴収制度により所得税が納められているため、基本的には自分で確定申告をして所得税を納める必要がありません。
源泉徴収の仕組み
源泉徴収制度は、企業が従業員の代わりに従業員の所得税の計算や申告をするものです。
そのため、納税義務者は企業ということになります。
源泉徴収の対象となるのは、基本的に企業から支払われる給与所得です。
その他には、退職金や株の配当金なども源泉徴収の対象になります。
源泉徴収されているかどうかは、企業から交付される給与明細をご覧いただくと、所得税などが差し引きされていると思いますので、給与から差し引きされている場合には源泉徴収が行われていると判断することができます。
この源泉徴収された税金部分(源泉所得税)は、企業が毎月国に納税しています。
飲食業は、税務調査が入りやすい業種であり、しかも調査は突然行われることが多い。
飲食業は、税務調査が入りやすい業種の一つです。その理由としては、現金商売が多いため、売上の除外や過少申告のリスクが高いこと、日々の仕入れが頻繁に発生し、食材や備品の購入を現金で行うことも多いため、仕入れの計上漏れが起こりやすいことなどが挙げられます。
また、飲食業に対する税務調査は、無予告で突然行われることが多いといえます。税務調査が行われる場合、課税庁は、納税義務者に対し、あらかじめ、調査を開始する日時・場所、調査の目的、調査の対象となる税目、調査の対象となる期間等を通知しなければならないとされています(国税通則法74条の9・1項)。このように、税務調査が行われる場合には、課税庁から事前連絡があるのが原則です。
しかし、飲食業の場合、現金商売が多いため、事前連絡なしで、いきなり店舗に調査官が訪れるケースもあり得ます。現金商売の場合、事前に通知をすることで、その時だけ現金の調整をされてしまうと、税務調査に出向く意味がなくなってしまうからです。
このような無予告調査は、法律で認められている調査であり、課税庁は、被調査者である納税義務者の申告や過去の調査実績、事業内容などから、違法または不当な行為を容易にし、正確な所得や税額などの把握を困難にするおそれ、その他調査の遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、事前通知を要しない、とされています(国税通則法74条の10)。
飲食店において源泉徴収漏れが発覚した場合のリスクについて
飲食店の経営者にとっても、従業員の給与等から所得税を天引きして納税する源泉徴収は日常業務の一環です。
しかし、源泉徴収義務は法律上の徴収義務であるだけに、源泉徴収漏れが生じた場合、その影響はかなり深刻です。飲食店業は、そもそも税務調査が入りやすい業種であることは既にお話しましたが、飲食店に税務調査が入り、源泉徴収漏れが発覚した場合、単なる経理処理上のミスでは済まされず、追徴課税や延滞税はもちろん、悪質な場合には刑事責任まで問われるリスクもあります。
飲食店で頻発する源泉徴収漏れとは
飲食店では、アルバイト従業員に対する給与等の支払いについて源泉所得税の徴収漏れが生じやすいと言われています。
多くの飲食店がアルバイトやパートを雇用していますが、毎月継続して給与を支払っている以上、源泉徴収を行わなければならないことは正規の従業員と変わりありません。しかるに、アルバイトやパートの場合、源泉徴収をする必要はないと誤解して源泉所得税が徴収漏れとなっているケースが多々見受けられます。
また、家族経営等の小規模飲食店の場合、アルバイト従業員に対する給与を手渡ししており、源泉所得税の天引きを失念していたケース等もあります。
税務調査で源泉徴収漏れを指摘された場合の一般的な流れ
源泉徴収漏れというのは、本来納付すべき税額に不足が生じている事態ですので、その不足分については延滞税及び加算税(不納付加算税)が課されます。また、税務調査の結果、隠蔽又は仮装工作によるものと判断された場合には、通常の加算税に代えて重加算税が賦課されます。重加算税は、不納付加算税を賦課する代わりに、本来納めるべき税額の35%もの高率で賦課される税金です。
刑事手続
源泉徴収漏れが発覚した場合、一般的な納付税額の過少の場合には、本来の納税額の納付に加えて、各種加算税等の納付の手続きを経て終結します。
しかしながら、源泉徴収漏れが単なる偶発的なミスではなく、意図的なもので、不納付額も多額に上るなど悪質な脱税行為と判断された場合には、税務当局は、検察庁に刑事告発を行うことになります。
刑事告発を受けた検察庁は、飲食店の経営者、経理関係者等を被疑者として取調べ、その後起訴するか否かを決めることになります。
最近では、刑事告発されると約8割から9割の高率で起訴されるに至っています。
また、起訴された場合には、刑事裁判が始まります。
国税局が令和7年6月に発表した資料によると、査察事件の第1審判決の状況は、令和6年度中の判決件数99件全てが有罪であり、有罪率は100%となっています。このことから一旦起訴されると有罪となる可能性は極めて高いのが実情です。
最後に 既にお話しましたように、ひとたび刑事告発をされてしまうと、極めて高い確率で起訴され、かつ、有罪となるという実情があります。ですから、税務調査を受け、源泉徴収漏れが発覚するかもしれない、あるいは、発覚したという場合には、早急に弁護士に相談して刑事告発を避けるための活動をしていくのが極めて重要と考えられます。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、脱税に関する相談を無料で行っていますので、気軽に早急にお問合せください。
投げ銭は贈与?税金は?

投げ銭(スーパーチャット)は贈与でしょうか?税金はかかるのでしょうか?その疑問に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所がお答えします。
投げ銭(スーパーチャット)とは
投げ銭という言葉は、もともと路上パフォーマーなどのパフォーマンスに対して、観客がパフォーマー側が準備した集金箱などに金銭を投げ入れる行為のことを指していました。
映画などで大道芸人が演技が終わった後にシルクハットなどを観客に差し出してそこに観客からお金を入れてもらう場面を見たことがあるのではないでしょうか?
しかし、インターネットが普及した現在においては、「投げ銭」の意味も変化しています。
今回取り上げる「投げ銭」とは、インターネットでの配信などに対して、視聴者やファンなどがオンラインで送金する行為を言います。
YouTubeではスーパーチャット(スパチャ)と言われていますが、これも代表的な「投げ銭」と言えるでしょう。
「投げ銭」のシステムは、オンライン上で金銭を送金する以外にも、有料ギフトを購入し送るなどの方法もあり様々ですが、いずれも配信者を金銭面で支援しているという面で共通しています。
投げ銭は贈与か?
投げ銭は贈与でしょうか?
贈与とは、無償で金銭等を譲渡する(譲り受ける)行為をいいます。
そのため、インターネット配信をしている人が何もパフォーマンスなどをしていないのに、投げ銭をされた場合には贈与に当たるといえるかもしれません。
しかし、ほとんどの場合、なにがしかのパフォーマンスを配信し、そのパフォーマンスに対して投げ銭が行われています。
そうすると、対価性が認められることになり、もはや「贈与」ということはできなくなります。
この場合、投げ銭で得た利益は「所得」として申告する必要があります。
贈与か所得かは納税の段階で非常に大きな違いが出てきます。
「贈与」の場合、贈与税の申告が必要となりますが、1年間に得た贈与の額が110万円を超えていなければ申告する必要がありません。
一方「所得」の場合には、基本的に20万円を超えている場合には確定申告が必要となります。
投げ銭の所得は何所得か?
投げ銭が「所得」になるとして、その所得の種類が問題となります。
すなわち「事業所得」か「雑所得」かです。
この点、基本的には「事業所得」となると考えられます。
たとえば、YouTuberの方などは動画配信を仕事として行っており、その動画配信を通じて「投げ銭」を得ていることになるので、仕事=事業によって得た収入と考えられます。
つまり、なにがしかの事業若しくは反復継続性のある行為によって得た利益は「事業所得」となると考えられます。
一方、一般の方が趣味でアップした動画などについては、「雑所得」となる可能性の方が高いと言えます。
反復継続性がなかったり、その行為によって利益を得ることを目的としているとはいえないからです。
投げ銭による所得の申告漏れが発覚したケース
ライブ配信者(ライバー)が投げ銭による所得を申告せず、国税局から多額の追徴課税を受けた実例について、以下の引用記事を基に解説します。
事件の概要
あるアプリでトークのライブ配信を行っていた女性が、大阪国税局から約2100万円の追徴課税を受けた。「ライバー」は、アイテムやギフトなどと呼ばれる視聴者からの投げ銭を主な収益源としているが、この投げ銭ももちろん課税の対象となる。しかし、女性は、4年分の投げ銭1億1900万円もの所得を一切申告していなかった。女性は「忙しくて確定申告をしていなかった」という趣旨の説明をしたという。
(令和6年12月10日付goo blog記事より抜粋。大元の記事(FNN)はリンク切れ)
https://blog.goo.ne.jp/kaikeinews/e/5615dce16ebd35a9daf30e832548790d
投げ銭(スーパーチャット)はYouTubeなどが有名ですが、引用記事のように各種トークアプリでも広く実装された機能といえます。投げ銭の額が大きくなるほど、無申告だった場合の加算税の負担も大きくなり、ケースによっては重加算税が課されたり、脱税事件として刑事処罰の対象となったりもします。
投げ銭の確定申告
事業所得に当たる場合、総収入から経費や控除額を引いたものが課税対象の金額となります。
ここで、青色申告か白色申告かによって、控除額が異なります。
たとえば、個人事業主で開業届を提出し青色申告承認申請をしている場合、青色申告をすることができます。
青色申告では最高55万円(令和元年以前は65万円)を控除することができます。
投げ銭は履歴が残るため、税務調査が入ると申告漏れが発覚しやすいといえます。
投げ銭が贈与になるのか事業所得になるのかわからない、所得になるのに贈与として申告していて心配という方は専門家に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では無料の法律相談を実施していますので、税務調査・査察調査が入ったという方は一度お問い合わせください。
YouTubeの収入は確定申告が必要?

YouTubeでの収入は確定申告が必要か、確定申告しないとバレるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
YouTubeでの収入
YouTubeに動画をアップして広告収入を得ているYouTuber(ユーチューバー)は、近年子供のなりたい職業ランキングに登場するなど一般的になりつつあります。
また、新型コロナの影響により、YouTubeで動画を配信して収入を得ている方も増えてきています。
そんなユーチューバーの方は、一部の有名な方々を除くと、ほとんどがYouTubeから広告収入を得ていると思います。
広告収入についても、所得税の申告が必要となるのは当然です。
もっとも、広告収入のすべてに所得税が課せられるのではなく、収入から必要経費や控除額を差し引いた残りが所得税の申告が必要となる「所得」となります。
そのため、収入の額が控除される額(基礎控除は48万円)以下の場合には「所得」がないということになり、申告は不要となります。
YouTubeでの収入は税務署にバレる?
YouTubeなどのインターネットを利用している取引については、国税庁が積極的に調査を実施しています。
国税庁が発表している「インターネット取引を行っている個人の調査状況」という資料によれば、平成29年度におけるインターネット取引の実地調査件数は2015件で、コンテンツ配信やネット広告に関する件数は274件を占めています。
また、国税庁は「電子商取引監視チーム」を配置し、インターネット取引を中心に扱う専門官が監視を強化しています。
このように、インターネット取引については、国税庁が常に目を光らせている分野といえます。
そして、YouTubeの収入については、
①再生回数が表示される
②広告収入は電子送金される
ということから税務署はユーチューバーが収入をどれくらい得ているのか把握しやすいといえます。
再生回数が多く、相当程度の広告収入を得ているはずなのに、確定申告がなされていないと税務署が調査に入ることになります。
確定申告を怠ったYouTuberが実際に追徴課税を受けたケース
確定申告を行なわなかったことが国税局に発覚し、多額の無申告加算税を支払うことになった実例について、以下の引用記事を基に解説します。
事件の概要
動画をユーチューブに投稿し、その報酬などとして約3600万円を得ていた男性が、確定申告をしていなかったとして、関東信越国税局の税務調査を受けた。重加算税を含む約700万円を追徴課税されたという。男性はかつて会社員だった。当初、国税局に対して「確定申告が必要なことを知らなかった」という趣旨の説明をしていたという。さらに追及を受けた男性は、意図的に申告をしなかったことを認めた。国税関係者は「確信的な無申告だったのに、それを隠そうとする。言い逃れの典型例だ」と指摘する。
(令和5年3月11日付朝日新聞オンラインの記事より抜粋)
https://www.asahi.com/articles/ASR3B3W07R36UTIL00P.html
引用記事によりますと、国税局は男性が税務調査への対応策を事前に調べていた事実も掴んでいたようです。先ほど述べたとおり、YouTuberの収入は国税局からすれば容易に捕捉することができるため、ごまかしは効きません。自分だけは大丈夫と思わずに、適切な確定申告を行うことが求められます。
YouTubeの収入を確定申告していないと
YouTubeの収入を確定申告していないと「無申告加算税」が課せられることになり、確定申告をしていた場合よりも多くの税金を支払わなければならなくなります。
また、意図的に確定申告をせず所得を隠していたということになれば、「重加算税」の対象となってしまう場合もあります。
さらに、無申告には刑罰も定められているため、金額や悪質性によっては、刑事裁判にかけられてしまう可能性もあります。
バレないから大丈夫と安易に考えていると、急に税務署が調査にうやって来て、多額の課税がなされる場合があります。
また、チャンネルの継続が難しくなる可能性もありますので、確定申告を忘れてしまっていたという方は、早めに専門家に相談して修正申告などをしていきましょう。
キャバ嬢が現金で受け取ったお金も申告が必要

キャバクラの従業員に対して税務調査が入る可能性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
1 お店に対する税務調査から発覚することが多い
キャバクラをはじめとする水商売と呼ばれる仕事については税務調査が入りやすい職種といえます。
そうした仕事では、大きなお金が動くため、きちんと税金を納めていないのではないかと国税局が注意をしていると考えられます。
では、仮に、キャバ嬢が脱税していた場合、どのようにして、それが発覚するのでしょうか。
税金に関する調査として、税務調査という言葉と聞いたことがあると思います。
その名のとおり、適切な税金が納められているのか、その前提として、どれくらいの売上や経費があったのかなどを調査するものです。
キャバ嬢本人に対する税務調査ではなくとも、お店に対する税務調査の中でキャバ嬢の申告漏れが発覚することも多いです。https://www.asahi.com/articles/ASND85W01ND8PTIL012.html
2 現金手渡しだから大丈夫というわけではない!
給料を現金手渡しで受け取っているから、その給料については大丈夫ではないかと思っている方もいると思いますが、実際にはそうではありません。
先ほど説明したように、お店に対する税務調査が行われることがありますが
仮に、キャバ嬢に対する給与を現金手渡しとしているお店であっても、
その調査の中で、お店からキャバ嬢に対し、いつ、いくらの給与を支払った記録が出てきた場合には
そのキャバ嬢がその給与を申告しているかどうかが調査されることになります。
また、仮に、お客さんから現金を受け取っていた場合においても
そのお客さんや他の従業員から、そのことを密告され、結果的に、そのキャバ嬢も調査の対象とされることに繋がります。
ですので、現金を手渡しで受け取っているから、税金については申告せずとも大丈夫だという認識は間違っているといえます。
3 現金で受け取ったお金を申告しないとどうなるの
仕事の対価として受け取ったお金については、所得として申告し、そこに所得税がかかってくると考えられます。
また、お客さんから、お店を通さず個人的に受け取っていた場合には、贈与として、贈与税がかかってくることが考えられます。https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2024/12/04/kiji/20241204s00041000295000c.html?page=1
ですので、それぞれ適切に、税金として申告する必要があり、そのようにしないことで余計に税金がかかり
最終的に自身にとって不利な結果になることがあります。
また、税金を納めるということだけで済まず、さらに刑事事件となる可能性もあります。
申告していない税金の額が高かったり、長期間に渡って申告をしていなかったりした場合には、
税務調査にとどまらず、国税局による査察、そして、検察官への刑事告発がなされ、最終的に刑事裁判にかけられるということもありえます。
刑事裁判となるのは悪質性が高いようなケースですので、すぐにそうなるわけではありませんが
やはりまずは適切な税金を納めていく必要があります。
4 適切な税金を納めていくためには
適切な税金を納めていくため、まずは、税理士に相談することが重要です。
お店でお願いしている税理士がいることもありますので、お店の人に相談してみるというのもいいと思います。
また、税務調査や査察など、さらに手続が進んでいった場合、税理士だけではなく、弁護士が介入していく必要があるかもしれません。
先ほど言及した刑事裁判は悪質性が高いようなケースですので、税金に関するトラブルとしては、どちらかというと少ないものですが
早めに対応することで、その後の手続きを回避できる場合があるかもしれません。
架空外注費で法人税脱税

法人税の脱税について、事例をもとに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
建設会社の代表者であるAさんは、下請けの個人事業主に虚偽の請求書を発行させ、架空の外注費を支払ったことにして経費を水増しして計上し、個人事業主からキックバックを受けていました。
この方法で1億円を超える所得を隠していたAさんは、大阪国税局の査察調査を受け、法人税3000万円を脱税したとして、法人税法違反の罪で大阪地方検察庁に告発されてしまいました。
(実際の事件をもとにしたフィクションです)
建設業(建設会社)で起こりやすい水増し請求
建設業でよくみられる不正に水増し請求があります。水増し請求は、下請けが元受けに対し、実際にかかった工事金額よりも多額の金額を請求するものです。工事金額を上乗せする方法としては、人工の数を増やしたり、材料費を上乗せする方法が多く見受けられます。
本事例における脱税の方法
事例のAさんは、下請けの個人事業主に実際にかかった費用よりも高額である虚偽の請求書を発行させ、水増しした外注費を支払って計上し、その後個人事業主からキックバックを受けています。
Aさんがキックバックを受けた金銭は、Aさんの収入(所得)となるため、Aさんにはキックバックを受けた金額に応じて所得税の確定申告をする必要があります。
Aさんが、所得税の確定申告をしていなかった場合には、Aさんが所得税の脱税をしていることになるのは、わかりやすいと思います。
しかし、今回の事例では、Aさんは法人税法違反の罪で告発されています。
法人税とは法人つまり会社が得た収益に対してかかる税金です。
キックバックをAさん個人ではなく、Aさんの建設会社が受けていた場合には、会社の収益といえるため、キックバックの部分は法人税の対象になり、確定申告をしなければ法人税の脱税になるでしょう。
では、キックバックはあくまでもAさん個人が受けていた場合はどうでしょうか。
この場合、問題となるのは、水増しした外注費を計上しているところとなります。
今回の事例では、外注費については、個人事業主に支払われています。
しかし、支払われている外注費のうち水増しされた外注費は本来であれば支払われない経費ということになります。
そうすると、水増しされた外注費の部分については、経費計上してはいけない部分ということになります。
そのため、会社が得た収入から架空の外注費を経費として差し引いて確定申告していた場合には、本来であればその架空経費の部分は差し引いてはいけない部分となるため、架空経費の部分も含めて課税対象金額に含まれることになります。
そして、架空経費の部分については、確定申告から漏れていることになるため、過少申告をしていたということになります。
架空外注費の計上はばれやすい。
架空外注費の計上は、企業の所得を意図的に減らし、納めるべき税金を少なくする目的で行われることが多いため、税務署は重大な不正行為とみなしています。そのため、外注費については特に注意深くチェックされます。
本事例の場合、キックバックの要求を受けた下請けの側としては、その水増しした金銭を出金する際の会計処理に困ってしまい、やむなく架空仕入れなどの架空の経費を計上したりします。
そのような状態のところに税務調査が入った場合、その架空の経費について追及されれば、簡単に不正加担が発覚してしまいます。このように、税務署が申告者本人だけでなく、その取引先にも調査の確認を行い、取引の事実を確認する方法を反面調査といいます。
法人税脱税のペナルティ
Aさん及びAさんの会社が受ける脱税のペナルティについては、大きく分けて①加算税、②刑事罰の二つが考えられます。
①加算税
Aさんの会社の場合には、過少申告をしていたことになるので、過少申告加算税が課せられることになります。
過少申告加算税は、新たに納めることになった税金の10%(新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円のいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%)が加算されます。
もっとも、Aさんの場合には、架空経費の計上という悪質性が高い方法によって過少申告をしているということが言えるので、過少申告加算税ではなく、重加算税が課せられる可能性が高いです。
重加算税は、過少申告加算税の基礎となる税額の35%に相当する金額が課されることになります。
②刑事罰
Aさんは告発を受けているので、今後は刑事事件としての捜査や裁判を受けていくことになります。
統計上、最近では告発された事件の約80から90%は起訴されています。
今回の事例では、偽りその他不正の行為により法人税を免れたといえるため、罰則は「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はその併科」となります(法人税法159条1項)。
ちなみに、罰金の額については、脱税額が1000万円を超える場合には、脱税額まで罰金の上限額を引き上げることができるとされています(同条2項)。
また、今回の事例では、会社代表者であるAさんが行っているので、会社に対しても罰金刑が科せられることになります(同法163条1項)。
そのため、起訴される場合にはAさんだけではなく、Aさんの会社も併せて起訴されることになります。
法人税脱税を疑われた場合の対応
法人税の脱税を疑われた場合には、まず実際に脱税といわれるような行為をしていたかどうかを自分たちでも調査しておく必要があります。
そして、税務調査などの調査では、脱税とはならないという根拠を示していくことが必要です。
もし、脱税に当たる行為をしていた場合には、それが意図的なものかどうかが重要なポイントとなります。
単なる申告漏れなどの場合には、脱税額が高額であったとしても査察や告発を免れることができる場合があります。
その場合でも、調査に対してどのように答えていくかが非常に大切になるので、早めに専門家に相談して方針を決めたうえで、調査に臨みましょう。
また、早めに修正申告をして納税義務を果たすことも、処分を軽くするために必要な行為です。
税理士や弁護士などに依頼して、修正申告をして、早めに納税をしましょう。
もっとも、脱税方法が悪質であるとか脱税期間が長かったり脱税額が高額であったりした場合には、告発までされる可能性が高くなります。
特に脱税額が3000万円を超える場合には、多くの事件が告発されていますので、刑事裁判を見据えて税理士だけではなく弁護士にも早めの段階から関与してもらっておくと安心です。 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を中心に扱っているので、刑事事件化を見据えた弁護活動も行えます。早めにご相談ください。
所得税法違反による脱税で実刑判決となった事例③

所得税法違反で実刑判決を受けた事例を紹介するとともに、実刑判決を避けるためにはどうしたらよいかを弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説していきます。全3回のうち、最終回の今回は、実刑判決を避けるためにはどうすればよいのかを中心に解説します。
実刑判決を避けるために重要な「反省」と「納税」
これまで紹介してきた事例から明らかなように、たとえ所得税の無申告・過少申告による脱税であっても、悪質性が高ければ実刑判決が現実のものとなります。
では、逮捕・起訴されてしまった後に実刑を避ける余地はあるのでしょうか。
絶対ではありませんが、裁判で情状が考慮され執行猶予付き判決(実刑回避)となるためには、以下の点が重視されます。
①速やかな納税措置
起訴後でも遅すぎることはありません。可能な限り早く修正申告を行い、免れた税額や加算税の納付に努めることが肝要です。
実際に、ある事件では被告人が脱税分と重加算税を既に納付済みであることが考慮され、懲役刑に執行猶予が付されたケースもあります。
納税義務の履行は反省の具体的な証左として評価されやすく、「社会復帰後も更生して納税を続ける意思あり」と裁判官に示す効果があります。
②深い反省と再発防止の誓約
被告人自身が犯行を認めているか、法廷でどれだけ真摯に謝罪・反省を述べるかも重要です。
脱税額が高額でも全額を納付し関与を認めて猛省していると裁判所が判断すれば、執行猶予を付して更生の機会を与えることがあります。
逆に「バレないと思った」「他にもやっている人がいる」などと言い訳したり反省が見られなかったりすれば、裁判官の心証は悪化し実刑可能性が高まります。
③初犯かつ社会的更生状況
前科がない初犯であること、家族や雇用主など周囲からの支援が期待でき、更生環境が整っていることも情状として有利に働きます。
一般的に前科がなく反省している初犯者は執行猶予となる場合が多い傾向です。
ただし再犯者や、過去に税務署の指摘で修正申告をしたのにまた隠ぺいを繰り返したようなケース(事例①のように前科猶予中の再犯)は極めて厳しく扱われ、執行猶予は期待しにくくなります。
また、脱税に関する前科ではなく、たとえば薬物に関する前科などであったとしても、初犯の方に比べると厳しい判断が出やすくなります。
さらに、すでに前科の執行猶予が満了しており、かつ、起訴をされた脱税の期間には含まれていなかったとしても、前科の執行猶予中から脱税行為に手を染めていたという内容が裁判で明らかになった場合には、かなり厳しく判断されることになります。
実際に、弊所で担当した脱税事件では、起訴されたのは直近3年間の脱税でしたが、薬物前科執行猶予中であった6年前にも脱税行為に手を染めていたということが考慮されて、実刑判決を受けた事案があります。この事案では、前科がなければ執行猶予が付けられてもおかしくはありませんでした。
弁護活動としては、上記の点を踏まえて被告人の反省文提出、税務当局との交渉による納税の実施、再発防止策の準備(税理士をつけ修正申告や納税をする誓約等)、家族の監督誓約書の提出などが考えられます。
実際、裁判例を見ても脱税額そのものだけでなく「犯行後にどう対応したか」が量刑に反映されています。巧妙な無申告による所得隠しであっても追徴税を完納したことで執行猶予となっている例もあります。
まとめ
無申告・過少申告による脱税は、「うっかりミス」では済まされない重大な犯罪です。
判決年月日や裁判所名は異なれど、紹介した事例はいずれも悪質な税逃れに対し裁判所が毅然とした態度で臨んだものです。
逮捕された被疑者本人やご家族にとっては大変な精神的負担でしょうが、まずは事実関係を認めた上で専門家(弁護士・税理士)の力を借り、一日も早く適正な納税と再発防止策を講じることが肝要です。
それが結果的に情状酌量につながり、執行猶予獲得や刑の減軽につながる可能性があります。
判決が出るまでのプロセスは苦難ですが、適切な対応次第でその後の人生を立て直す余地は残されています。
「逃れ得た税より失うものの方が大きい」――本記事の事例が示す教訓を胸に、真摯な反省と更生への努力を続けることが何より重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、所得税法違反で告発された方など、刑事裁判になりそうで不安な方の相談を随時受け付けています。
初回のご相談は無料ですので、不安な方は一度弊所までお電話下さい。
所得税法違反による脱税で実刑判決となった事例②

所得税法違反で実刑判決を受けた事例を紹介するとともに、実刑判決を避けるためにはどうしたらよいかを弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説していきます。全3回のうち、2回目の今回は、実刑判決になった事例や実刑と執行猶予を分ける基準となるような事例について紹介します。
事例②: ネット販売収入を無申告 – 虚偽の住民登録で所在隠し
大阪地方裁判所 令和2年9月14日判決(第6刑事部)は、インターネット上の物品販売業で得た事業所得を申告せず脱税した被告に対し、懲役1年および罰金800万円の判決を言い渡しました。
被告人は個人事業主(ネット通販業者)で、売上を無申告のまま所得税を免れただけでなく、居住地を偽装する目的で虚偽の住民登録まで行っていました。
確定申告を一切せず所在をくらますこの手口により、納税義務の追及を長期間逃れようとした悪質性が認定されています。
裁判所は「納税者としての規範意識が極めて低く、計画的かつ悪質」と断じていますが、被告人に前科がないこと、加算税を含めた全額の納税を終えていることを考慮され、執行猶予が付されています。
なお、判決では罰金不納の場合の労役場留置(罰金未納により労役場で服役する期間)についても言及されており、経済的にも厳しい姿勢が示されています。
被告人の職業はネット通販業で比較的若年の個人事業者と推測されますが、裁判所は「申告納税制度の根幹を揺るがす犯行」として強い非難を表明しています。
事例③: 巨額の所得隠し – 銀座ビルオーナーに懲役4年
脱税額が桁違いに大きい場合、初犯でも実刑が避けられないことがあります。
その典型例が、東京地方裁判所 平成30年11月20日判決で有罪となった東京・銀座のビルオーナーの事件です。
被告人(当時86歳)は繁華街ビルのオーナー収入などで約10億6000万円もの所得を隠し、法人税法違反の罪に問われました(※個人オーナーでしたが、ビル収入を管理する法人を通じて納税を免れた可能性があります)。
裁判所は「極めて巧妙かつ長期にわたる犯行で、悪質性が顕著」として、被告人に対し懲役4年および罰金2億4000万円の実刑判決を宣告しました(検察の求刑は懲役5年・罰金3億円)。
この量刑は近年の所得税・法人税ほ脱事案としては最長クラスであり、被告人が高齢であったにもかかわらず実刑が選択された点で注目されます。
判決理由では、「被告人はビル収益の大半を申告せず、架空の経費計上など巧みな手段で巨額の税負担を免れてきた。その犯情の悪質さは強い非難に値し、社会的影響も看過できない」と指摘されました。
被告人は高齢ゆえ体調面を酌む余地もあり得ましたが、それ以上に10億円超という脱税規模と納税義務軽視の態度が重視され、実刑は避けられませんでした。
なお、この事件では法人名義での犯行でしたが、実質的経営者である被告人個人に懲役刑が科されています。
被告人はビル経営以外にも資産家として多額の収入があったと見られますが、公判では明確な弁解はなく、最終的に追徴課税分も含め莫大な納税を迫られることになりました。
家族にとっても資産差押え等の経済的影響は免れず、社会的信用の失墜という代償も非常に大きい事例です。
事例④: 架空経費で所得圧縮 – ブリーダー親子に有罪判決(執行猶予付き)
実刑判決の例ではありませんが、悪質な所得隠し手口として参考になるのが、ペットブリーダー業を営む親子による脱税事件です。
こちらは新潟地方裁判所 令和4年10月7日判決(報道発表日ベース)で、親子それぞれに有罪判決が言い渡されています。
被告人は父(ブリーダー経営者)と娘(事業手伝い)で、コロナ禍のペットブームに乗って売上が急増したにもかかわらず、その所得約1億6000万円を意図的に申告せず、犬猫の餌代を架空計上するなどの方法で経費を水増しし、結果的に約6100万円もの所得税を免れたとされています。
国税当局の査察により告発され、両被告は逮捕・起訴されました。
その後の裁判で、新潟地裁は父親に懲役1年・執行猶予3年・罰金1500万円、娘に懲役10か月・執行猶予3年(罰金なし)という判決を言い渡しています。
判決理由では、親子が役割を分担し組織的に脱税の指示と実行を行った点、コロナ禍の特需による利益をほぼ丸ごと隠ぺいした点などから「刑事責任は重い」と指摘されています。
「餌代の架空計上」という手口は比較的単純ながら巧妙で、売上規模の拡大に比例して脱税額も巨額となった悪質な事案でした。
しかし本件では、執行猶予が付されています。
考えられる理由として、両被告人が起訴事実を大筋で認め反省の態度を示したこと、起訴後にある程度の修正申告や追納の意思を示した可能性、そして前科がなかった点が挙げられます。
実際、裁判官は「脱税額は甚大で強い非難に値する」としつつも、高齢の父親が初犯であること、娘も従属的立場だったこと、そして何より犯行を認めていることを考慮し、両名に対する実刑は避けました(いずれも執行猶予3年)。
このように、脱税額が1億円未満規模でも刑事告発・有罪判決に至ること、また執行猶予付きとはいえ経営者本人に懲役刑と高額の罰金が科され社会的制裁を受けることがお分かりいただけるでしょう。
被告人らの職業は中小規模のブリーダー経営者とその家族従業員であり、「自分たちは大企業ではないから大丈夫」という油断があったのかもしれません。
しかし結果的に信用を失い、多額の追徴課税(重加算税含む)や罰金支払いに追われることになりました。
~次回は、実刑判決を避けるためにはどうすればいいのかなどについて解説します~
所得税法違反による脱税で実刑判決となった事例①

所得税法違反で実刑判決を受けた事例を紹介するとともに、実刑判決を避けるためにはどうしたらよいかを弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説していきます。3回に分けて解説していきますので、第1回の今回は所得税法違反の概要と実刑判決に至るポイントを解説します。
所得税法違反の概要
所得税の申告を意図的にせず税金を免れる行為(無申告ほ脱)や、虚偽の申告で所得を少なく見せる行為(過少申告ほ脱)は犯罪であり、悪質な場合には懲役刑(実刑)が科されることがあります。
近年は、自営業者や副業収入を得る個人による所得隠しも増えており、「自分は大丈夫」と油断していると刑事告発・起訴されるケースも少なくありません。
実際、令和5年度(2023年)には脱税事件の有罪判決83件中9件で実刑判決が言い渡されており、実刑となった場合の懲役期間は平均1年3か月(15.6か月)、中には懲役4年の重い判決が下った例もあります。
以下、無申告または過少申告による脱税で実刑に至った主な事例を、判決年月日・裁判所、脱税額、手口の悪質性、判決内容、被告人の属性、反省状況などに着目して紹介します。
脱税で実刑判決に至るポイント(悪質性と量刑の傾向)
脱税事件の量刑は、単純な申告漏れ(過失)か意図的な所得隠し(故意犯)かで大きく異なります。
意図的な脱税が明らかになると、国税局査察部(マルサ)による強制調査を経て検察庁に告発され、刑事裁判で懲役刑・罰金刑が科されることになります。
所得税法では、偽の領収証を用いるなど不正行為による脱税(ほ脱罪)に「10年以下の懲役または1000万円以下の罰金(併科も可)」を、単なる無申告でも故意に納税を免れた場合(単純無申告ほ脱)に「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」を科すと規定しています。
初犯か再犯か、脱税額や手口の巧妙さ、犯行期間、さらには犯行後の対応(修正申告や納税、反省の態度など)によって、執行猶予付き判決になるか実刑(猶予なし)となるかが左右されます。
一般に、脱税額が巨額であったり、長年にわたる計画的な犯行、偽装工作(架空経費の計上や名義口座の利用など)が認められると「悪質性が高い」と判断され、起訴後の対応によっては実刑判決が選択されます。
特に過去に税務指摘を受けても改善せず繰り返した場合や、税理士など専門家ぐるみの組織的犯行では厳罰が下りやすい傾向があります。
一方で、起訴後に速やかに修正申告を行い、脱税分の納税(本税や重加算税)を完納または一部納付した場合や、犯行を認め深く反省している場合には、裁判所が情状を考慮し執行猶予を付すケースも少なくありません。
以下の事例でも、各被告人の悪質性と情状が量刑に大きく影響している点に注目してください。
事例①: FX取引利益を無申告 – 前科執行猶予中の再犯で懲役刑
近年話題となったのが、FX(外国為替証拠金取引)による利益を無申告のまま隠し続け、実刑判決に至ったケースです。
令和4年度の国税庁「査察の概要」にも掲載された事例で、被告人は過去に所得税法違反で有罪(執行猶予付き)となったにもかかわらず、執行猶予期間中に再び多数の他人名義口座でFX取引を行い、その利益について一度も確定申告書を提出しませんでした。
こうした悪質な常習犯である点が重視され、国税当局は告発を決断。裁判所も「所得税の申告納税制度を軽視し、極めて悪質」と判断し、懲役1年4か月の実刑判決を言い渡しました(※罰金刑も併科)。
判決年月日や管轄裁判所は公表資料では明示されていませんが、本件は令和4年中に地裁レベルで言い渡されたものです。
被告人は個人投資家(副業的にFX取引を行っていた者)と思われ、前科がありながら犯行を繰り返した点に強い非難が集まりました。
なお、犯行態様も極めて巧妙で、数十もの口座を使った所得秘匿工作は「偽りその他不正の行為」にあたる悪質性が高い事案といえます。判決においては、被告人に有利な情状はほとんど認められず、執行猶予は付与されませんでした。
~次回は実刑判決になった事例などを紹介します~
法人税脱税事件の実刑判決事例紹介

日本では脱税事件の有罪率は極めて高いものの、多くは執行猶予付き判決にとどまり、実刑(執行猶予なしの懲役刑)が言い渡されるのは脱税額が巨額であったり常習性がある場合です。法人税に関する脱税で実刑判決に至った代表的な事例を、概要と判決内容・量刑理由とともに紹介します。
銀座「丸源ビル」オーナーによる10億円超の法人税脱税事件(2018年)
事件概要: かつて「銀座の不動産王」と呼ばれた「丸源ビル」オーナーは、自身が社長を務めていたビル管理会社のテナント賃貸収入の一部を除外する手口で、2011~2013年の3年間に計約35億円の所得を隠し、法人税約10億6000万円を免れたとして起訴されました。被告人は初公判で全面否認し、公判中に弁護団を何度も交代するなど長期裁判となりました。
判決内容: 東京地方裁判所は被告人に対し懲役4年及び罰金2億4000万円の実刑判決を言い渡しました(求刑は懲役5年・罰金3億円)。判決理由で裁判長は、「脱税規模は極めて大きく、所得隠しの手口も巧妙。被告は売上や経費を自身の思うままに操作し、納税義務をないがしろにした」と被告人の犯行態度を厳しく非難しました。巨額かつ悪質な脱税であること、起訴後も反省や納税が見られなかったことが実刑・長期懲役の主因となりました。
税理士による法人税脱税ほう助事件(2020年)
事件概要: 税理士で会社社長の被告人は、首都圏の2社が所得隠しを行って法人税の納付を免れた際、その事実を知りながら自らの管理する会社名義の口座に架空名目の資金を入金させる方法で脱税を手助けしました。具体的には、2社が計上した架空の雑損失や不動産手数料の支払いを装って、被告人の会社口座に資金を迂回入金させることで、両社の所得隠しを容易にしていたとされます。被告人は過去にも同様の法人税法違反ほう助で有罪判決(執行猶予付き)を受けており、その執行猶予期間中に再び本件犯行に及んでいました。
判決内容: 東京地方裁判所で判決が言い渡され、被告人に懲役10か月および罰金800万円の刑が科されました。全国で初めて法人税法違反のほう助犯に対して実刑判決が出たケースでもあります。量刑理由としては、過去の前科があり執行猶予中の再犯だった悪質性が決定的でした。裁判所は「一度有罪判決を受けながら再び脱税ほう助に及んだ点は看過できない」として、再犯抑止の観点から実刑が相当と判断したものとみられます。
まとめ
国税庁の公表データによれば、近年の脱税事件で実刑判決にまで至るケースは毎年数件程度です。例えば令和5年度中に一審判決があった脱税事件83件では、うち9人(約11%)が実刑判決を受けています。実刑となる懲役期間の平均は約16ヶ月で、最長は前述の銀座ビルオーナー事件の懲役4年でした。一般に「ほ脱額が合計3億円を超える場合には、全額納付していても実刑判決となる場合が多い」とも言われており、巨額・悪質な脱税には厳罰が科される傾向があります。実刑判決が確定すればただちに服役が必要となり、執行猶予付き判決と比べて社会的制裁も一層深刻なものとなります。 脱税を疑われた場合には、早期に弁護士に相談し、実刑判決という重い判決を受けることがないように活動してもらいましょう。
法人税脱税手口の傾向と分析

前回まで東京国税局が法人税法違反で告発した事例を過去10年間分見てきましたが、今回はそこから見えてくる脱税の手口と傾向について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
脱税の手口
過去10年の告発事例を通じて、脱税の手口は概ね「売上の除外(収入隠し)」と「架空経費・架空原価の計上」に大別できます。建設業や不動産業では下請代金の循環取引や架空発注による原価水増し、IT・サービス業では架空外注費の計上による利益圧縮が典型です。現金商売の業種(クラブ、飲食店など)では売上の一部を現金でプールして申告しない手口も根強く、実際「鬼滅の刃」制作会社の事件ではカフェ売上を金庫に隠匿する古典的手法で多額の所得を隠していました。
告発が多い業種
業種的には、不正が発覚・告発された件数が多いのは不動産業、建設業、クラブ・バー経営などで、2015年度の全国データでも「建設業15件」「不動産業12件」「クラブ・バー7件」が上位を占めました。東京国税局管内でも不動産・建設関連の告発が目立ち、土地取引や受注工事を巡る所得隠しが後を絶たない状況です。一方で近年はIT企業やコンテンツ産業(アニメ制作会社など)も告発事例が散見され、脱税の摘発対象が新分野にも広がっていることがわかります。
脱税額の規模
脱税額の規模について見ると、1件あたりの脱税額は平均で数千万円から1億円程度です。平成27年度には全国平均で約9,700万円(告発分)でしたが、その後若干減少しつつも、おおむね1件あたり1億円前後で推移しています。東京国税局管内では令和4年度の告発事案1件あたり脱税額が9,100万円と全国平均(8,800万円)よりやや高く、首都圏ゆえに金額の大きな悪質事例が多いことを示唆します。実際にここ数年でも脱税額1億円超の案件が複数摘発されており、金額規模の大きな脱税への査察強化がうかがえます。
処分の状況
処分の状況については、東京国税局査察部が告発に踏み切るのは悪質かつ多額の事案に限られるため、告発後は原則起訴(刑事裁判)されています。令和元年度のデータでは告発案件の起訴率は約85%に達し、起訴された場合の有罪率はほぼ100%(執行猶予付き判決を含め、全件有罪)となっています。実刑判決が出るケースもあり、例えば平成27年度に一審判決があった133件のうち2件では実刑判決(懲役刑)が科されています。悪質な法人税ほ脱に厳しい姿勢です。不起訴となるケースは極めて珍しく、東京国税局では1991年以降ほとんど例がありません。
総括
総じて、この10年間で東京国税局管内の法人税法違反による告発事例は「伝統的な手口による脱税の摘発」が中心ですが、告発件数は景気動向や社会状況で増減しつつも概ね毎年数十件規模で推移しています。不動産・建設業等の常連業種に加え、新興業種にもメスが入る傾向が見られ、脱税手口もより巧妙化・多様化していると言えます。しかし、国税当局も近年は消費税の不正還付や国際的租税回避スキームなど時流に即した重点分野に対して調査を強化しており、悪質なほ脱には継続して刑事告発を行う方針が示されています。その抑止効果もあってか、直近では脱税総額自体は一時期より低水準に抑えられています。いずれにせよ、「申告納税制度を揺るがす悪質な脱税者には一罰百戒をもって臨む」という東京国税局査察部の姿勢は一貫しており、今後も様々な業種・手口の脱税事案が告発される可能性があります。適正な申告納税の重要性を再認識させるこれらの事例は、経営者にとって他山の石と言えるでしょう。
« Older Entries