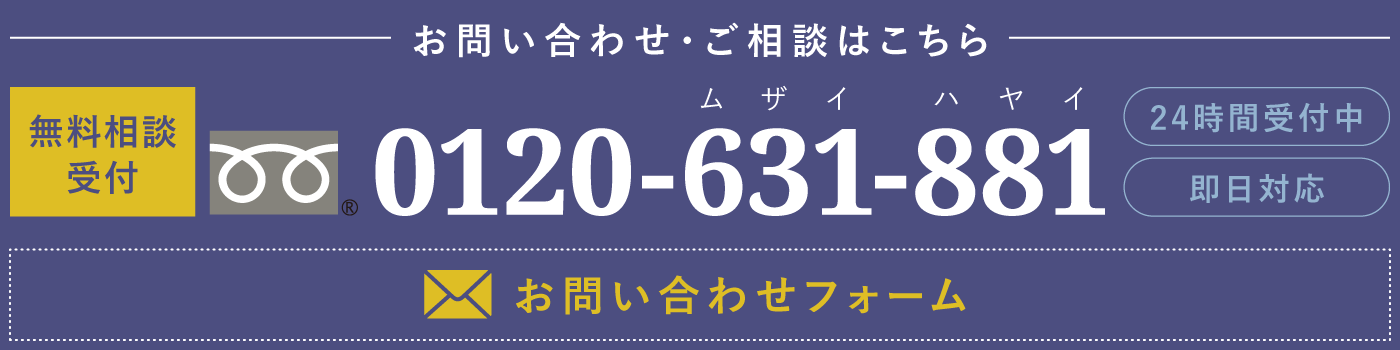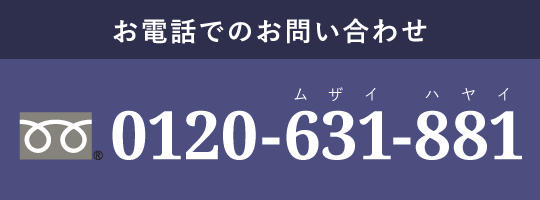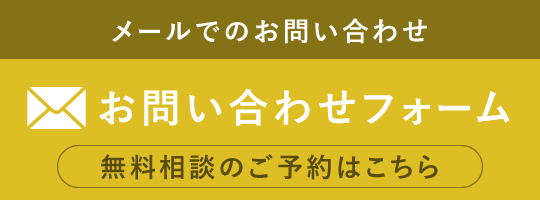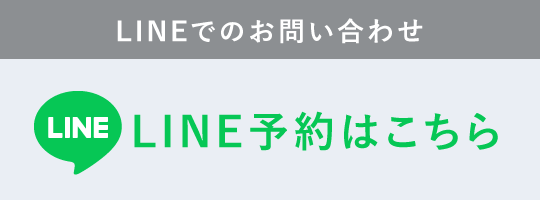このページの目次
無利息で貸付を行った際にも、利息相当額の収益を計上しなければならないかが争点となった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
1 事例
株式会社X(以下、「X社」といいます。)は、子会社である株式会社T(以下、「T社」といいます。)に対し、その事業達成を援助する目的で、期間を3か年に限り、4000万円を限度として、「無利息」で融資する契約を締結しました。
そして、X社は、この契約に基づき、T社に対して、○年度において、2000万円を融資しました。
これに対し、税務署長Yは、X社の融資について、通常当事者間で行われる融資における利率による利息相当額を収益として計上する旨の更正処分をしました。
(なお、事例につきましては、実際の裁判例を若干修正、簡略化しています。)
2 争点~法人税法22条2項
法人税法21条1項において、法人の「各事業年度の所得の金額」は、「当該事業年度の益金の額」-「当該事業年度の損金の額」とされています。
その上で、同条2項において、益金の額に算入すべき金額には、「無償による資産の譲渡又は役務の提供」により生じた収益を含むとしています。
こうした法律からすれば、X社のT社に対する融資は、無償による役務の提供として、利息相当額の収益が発生しているものとも考えることができることから問題となりました。
なお、現在、この点については、平成30年に法人税法が改正され、22条の2が設けられ、法律上の解決がなされていますが、この後紹介する裁判例は、またそのような規定がない頃の判断です。
3 裁判所の見解について
この点が問題となった大阪高裁昭和53年3月30日判決(判時925号51頁)は、X社が行ったのが無利息の融資であったとしても、X社には、通常、当事者間で行われる利息相当額の収益があり、その分を計上する必要があるとしました。
その上で、X社のそうした収益は、X社がT社に無償で給付(すなわち寄付)したであるとし、法人税法37条1、7項により、一定限度を超える寄付については損金計上できないとしました。
実際の判決文は、次のとおりです。
「資産の無償譲渡、役務の無償提供は、実質的にみた場合、資産の有償譲渡、役務の有償提供によって得た代償を無償で給付したのと同じである」とした上で、「営利法人が金銭(元本)を無利息の約定で他に貸付けた場合には、借主からこれと対価的意義を有するものと認められる経済的利益の供与を受けているか、あるいは、他に当該営利法人がこれを受けることなく右果実相当額の利益を手離すことを首肯するに足りる何らかの合理的な経済目的その他の事情が存する場合でないかぎり、当該貸付がなされる場合にその当事者間で通常ありうべき利率による金銭相当額の経済的利益が借主に移転したものとして顕在化したといいうるのであり、右利率による金銭相当額の経済的利益が無償で借主に提供されたものとしてこれが当該法人の収益として認識される」。
4 現在の法律―法人税法22条の2第4項
先ほども少し触れましたが、現在は、法人の資産の販売・譲渡、役務の提供において、原則として、その販売・譲渡をした資産の引渡時の価額、その提供した役務について通常得るべき対価の額に相当する金額を収益とするという法律が設けられています(法人税法22条の2第4項)。
5 予想される問題点・弁護活動
以上のような裁判例、法人税法22条の2第4項の規定からすれば、たとえば、無償で第三者に会社の資産を譲った場合においても、その資産の引渡時の価格を収益として計上する必要があることになり、これを怠ると、法人税法違反(場合によっては消費税法違反も)となります。
こうしたことは、税務調査の場面で問題になることが考えられますし、他にも脱税をしており、査察を受けている場面でも問題になることも考えられます。
もっとも、大阪高裁が指摘するように、①対価的意義を有する経済的利益の供与を受けていたり、②対価を受けることがなく利益を手離すことに合理的な経済目的がある場合には、収益として計上する必要がないという解釈も可能です。
そこで、こうした点が問題になった場合には、弁護士に的確なアドバイスを受け、仮に収益として計上する必要がある場合には、その旨の修正申告をするといったことが考えられます。
5 最後に
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、脱税事件に強い弁護士が所属し、法人税法違反など多数の事件を取り扱っています。法人税法違反の疑いがあるとして税務調査を受けた方は、初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。