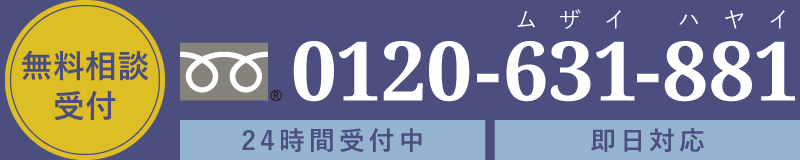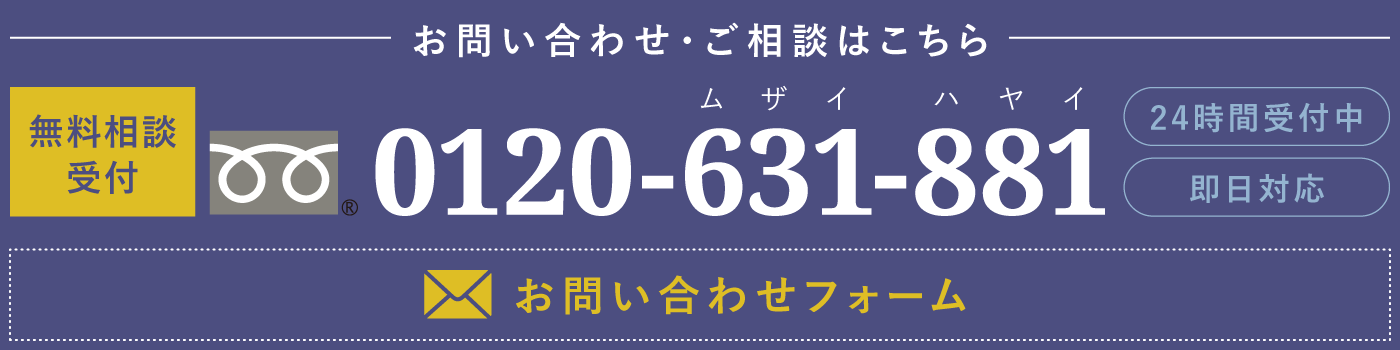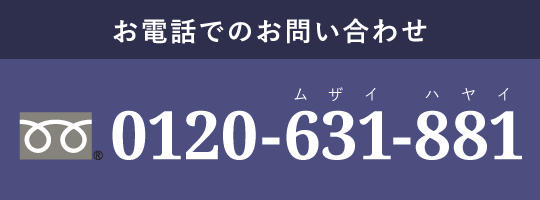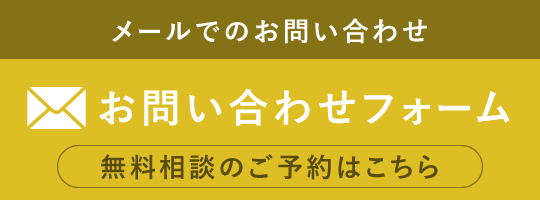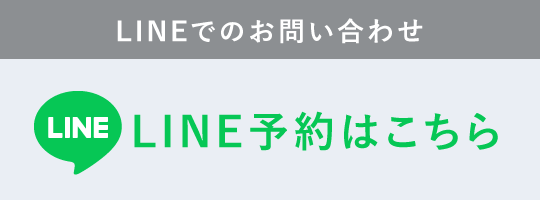Archive for the ‘消費税・相続税’ Category
輸出業における消費税還付の仕組みと告発事例解説~消費税還付制度の仕組みと不正還付事件について弁護士が解説します~
輸出業における消費税還付の仕組みと告発事例解説

日本の輸出業における消費税還付の仕組みや手続、各業種ごとの特徴や告発事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所がまとめて解説します。
還付の仕組みと条件
日本の消費税は「仕入れに係る消費税額(仮払消費税)」を「売上に係る消費税額(仮受消費税)」から差し引いて納付額を計算する仕組みです。
輸出取引は消費税法上 輸出免税(税率0%)の対象となるため、海外への商品販売や国外向けサービス提供には消費税が課税されません。
したがって輸出売上には消費税が発生しない一方、国内で仕入れや経費に支払った消費税は控除可能であり、仮受消費税より仮払消費税の方が大きい場合、その差額が還付されます。
例えば、輸出売上300万円(税抜)に対する消費税0円と、仕入200万円(税抜)に対する消費税20万円では、20万円の還付を受けられます。
消費税還付を受けるにはいくつかの条件があります。まず課税事業者であることが必要です。
前々年度の課税売上高が1,000万円以下の事業者(免税事業者)は原則として消費税の納税義務がなく、消費税申告を行わないため還付も受けられません。(ただし、免税事業者でも「課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になる選択をすれば還付申請が可能です)。
新設法人も原則初年度は免税事業者ですが、資本金1,000万円以上など一定の場合は最初から課税事業者となります。
次に原則課税で申告計算していることも条件です。消費税の簡易課税制度を適用している場合、実額に基づく仕入税額控除が行えず還付を受けられないためです。
また、還付を受けるためには該当期間について確定申告で還付申告を行うことが前提となります。
取引面では、輸出免税に該当する売上であることが必要です。
輸出免税の適用範囲には、例えば「日本国内から海外への商品の輸出」「国際運送や国際通信」「非居住者への特許や著作権など無形財産権の提供」「非居住者への役務提供」などが含まれます。
ただし非居住者相手のサービスでも、日本国内で直接便益を受けるもの(例:国内での宿泊・飲食提供など)は輸出取引とみなされず課税対象です。
これら輸出取引に該当する売上であれば税率0%となり、対応する仕入税額の還付を受けられます。なお、輸出免税の適用を受けるにはその取引が輸出であることを証明する書類を備えることが求められます(詳細は後述)。
申請手続きや必要書類
消費税の還付は所轄税務署への消費税確定申告を通じて申請します。法人の場合、事業年度終了日の翌日から2か月以内(個人事業主は翌年3月31日まで)に確定申告書を提出する必要があります。
還付申告の際には、以下の書類を提出します。
・消費税及び地方消費税の確定申告書(主たる申告用紙)
・付表2「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算書」(売上高に占める課税売上割合や控除仕入税額を計算する明細)
・消費税の還付申告に関する明細書(還付となる理由や取引ごとの売上・仕入明細を記載した書類)
確定申告書に還付額を計算の上で提出すると、税務署による内容確認を経て還付金の支払い決定がなされます。輸出取引による還付を申告する場合、輸出売上に対応する還付額と国内売上に対する納付額をまとめて申告することになるため、輸出事業と国内事業の両方がある場合は申告書上で相殺計算する点に注意が必要です。
還付金の受け取り方法は、申告時に指定した銀行口座への振込か、ゆうちょ銀行・郵便局窓口での受領の2通りがあります。
一般には口座振込が利用されますが、口座名義は申告者本人または納税管理人名義である必要があります。
還付申告の証拠書類として、輸出取引であることを示す資料を準備・保管する必要があります。輸出する商品のケースでは税関の輸出許可書(税関長の証明付き)を用意しなければなりません。
20万円以下の少額輸出で通常郵便物を使う場合は、日本郵便が発行する引受証明書(品名・数量・価額の記載されたもの)が証拠書類となります。
サービス提供や無形資産の提供など物品以外の輸出取引では、契約書など取引内容と国外提供であることを示す書面が必要です。
これらの書類は申告時に提出を求められる場合もあるため、輸出許可証や契約書類の原本を手元に保管しておくことが重要です。
特に輸出代行業者(商社やフォワーダー)が輸出手続きを代行した場合でも、自社が還付を受けるには輸出許可書等の原本保管と所定の通知手続きを行う必要があります(詳細は後述の特記事例参照)。
なお、輸出免税の証拠書類や帳簿は7年間の保存義務があります。
消費税の還付申告を行うと、原則として税務署による税務調査や審査の対象となります。
還付申告額が大きい場合や内容に不明点がある場合には、書面照会や実地調査によって輸出の実態や仕入控除の妥当性が確認されます。不備や誤りがあれば還付は認められません。
そのため、日頃から取引証憑の整備や正確な帳簿記録を行い、還付申告に備えることが大切です。還付額が継続的に発生する輸出業者では、資金繰りの観点から還付を迅速に受けるための制度活用も有効です。例えば課税期間の短縮特例を利用すると、通常1年ごとの課税期間を四半期毎や月毎に区切って申告できるため、還付発生時期を早めることができます(適用には事前に「課税期間特例選択届出書」を提出し2年間の継続適用が必要です)。
また電子申告(e-Tax)を活用すれば処理期間が短縮され、還付までの時間が大幅に早まる傾向があります。
実際、書面申告では還付まで1~2か月かかるケースでも、e-Taxなら3週間程度で振込まれる例もあります。
対象となる取引や事業者の要件
消費税還付を受けられる事業者は、前述の通り課税事業者に限られます。
免税事業者の場合、消費税の申告義務がないため、たとえ輸出取引があっても仕入税額の還付を受けることはできません。輸出を行う企業・事業者であれば、規模が小さく基準売上高1,000万円以下でも、必要に応じて課税事業者選択届出を提出し課税事業者となることで還付申請が可能となります。
これは、輸出で仕入税額が多額になる場合、還付を受けられるよう自主的に課税事業者になる選択が有利となるためです(届出を適用する課税期間開始前日までに提出)。 また、還付を受けるには課税売上に対する仕入税額控除の適用要件を満たす必要があります。具体的には、帳簿及び適格請求書(インボイス)等の保存要件を満たし、課税仕入れについて適法に税額控除できる状態であることが重要です(2023年10月以降インボイス制度開始により、適格請求書等の保存が仕入税額控除の要件)。輸出免税となる売上であっても、帳簿・証憑不備で仕入税額控除が否認されると結果的に還付も受けられなくなるため注意が必要です。 輸出取引の種類については、前述したように商品の国外輸送による販売だけでなく、国外向けの役務提供や無形資産の譲渡も含まれます。
例えばメーカーが製品を海外顧客に直接販売するケース、商社が国内商品を買い付けて海外に輸出するケース、ソフトウェア企業が海外法人にソフトを提供するケースなどが該当します。これらはいずれも法律上は課税取引扱いで税率0%(免税)となるため、それに要した仕入や経費の消費税は全額控除・還付対象となります。
一方、非課税取引(例:国内の医療、教育、住宅の賃貸、金融など)や不課税取引(給与支払い、寄附など)はそもそも課税対象外であり、対応する仕入税額は控除できません。
輸出取引は非課税ではなく「課税対象だが税率0%」という位置付けのため、国内課税取引と同様に仕入税額控除が可能である点が大きな特徴です。
したがって、輸出売上を有する事業者は、たとえ売上に消費税がかからなくても課税事業者でありさえすれば仕入税額の還付を受けられます。
ただし事業者によっては、課税売上と非課税売上が混在する場合もあります。例えば国内で医薬品販売(社会保険診療は非課税)と輸出販売を併営するようなケースでは、課税売上割合に応じて仕入税額控除額が按分計算されます。非課税売上に対応する部分の仕入税額は控除できないため、その部分は還付対象外となります。
このように、還付を受けられる仕入税額はあくまで課税売上(輸出を含む)に紐づく部分のみである点に留意が必要です。
特定の業種やケースに関する情報
輸出に携わる業種では消費税還付が日常的に発生します。典型的なのは製造業や商社(貿易業)です。メーカーの場合、製品を海外に輸出すれば売上に対する消費税は0%ですが、生産に必要な原材料費や設備投資には国内で消費税を支払います。輸出比率が高い製造業者ほど、支払った消費税額が預かった消費税額を上回りやすく、多額の還付を受ける傾向があります。
実際、日本を代表する自動車メーカー等の大企業は毎年巨額の消費税還付を受けており、2022年度(令和4年度)には輸出大企業上位20社で合計約1兆9千億円もの消費税が国から還付されたとの推計もあります。
上位にはトヨタ自動車(日用品・部品の輸出が多い)や日産自動車、本田技研工業といった自動車メーカーが名を連ね、単独で数千億円規模の還付を受けた企業もあります(例:トヨタは約5,300億円)。
これらは輸出取引に係る仕入税額が巨額になるためで、制度上当然の結果ではありますが、その規模の大きさからニュースになることもあります。
商社や専門の貿易会社でも、国内で商品を仕入れて海外に転売するビジネスモデルでは恒常的に還付超過(仕入時に支払う消費税の方が輸出売上の仮受消費税より多い)が発生します。例えば、国内メーカーから商品を税込仕入して輸出すれば、仕入時の10%消費税分が丸ごと還付対象となります。貿易業者にとって消費税還付は重要な資金源とも言え、適切な手続きによりキャッシュフローを確保することができます。
サービス業においても、提供先が海外(非居住者)でサービスの消費が国外で完結する場合は輸出免税が適用されます。
例えば国際通信サービス、国際輸送サービス、海外法人向けのコンサルティングやエンジニアリング、ソフトウェア・デザインの提供、特許やライセンス供与などは非居住者に対する役務提供として消費税が免税(0%)になります。
その結果、国内で要した人件費以外の経費(オフィス賃料や機器購入費用など)に含まれる消費税の還付を受けられます。例えば日本のIT企業が海外企業と契約して開発サービスを提供する場合、売上に消費税は発生しませんが、国内で購入したPCやソフトウェア、通信費等の消費税は全て控除・還付されます。一方、旅行業やホテル業など訪日外国人相手のサービスは、そのサービス提供が日本国内で行われ直接便益を享受させるもののため免税にならず、通常通り課税となります(つまり還付ではなく消費者から預かった消費税を納付する立場)。
このようにサービス業でも取引の性質によって消費税の扱いが異なり、国外向けサービスを主とする事業者は輸出産業同様に還付を受けるケースがあります。 特別なケースや過去の事例としては、事業構造や取引形態に起因する消費税還付があります。例えば、設立初年度に巨額の設備投資を行った場合です。工場建設や大型機械の購入などで一時的に多額の消費税を支払うと、売上が立つ前でもその分の消費税は還付申告により取り戻すことができます。実際、赤字や経費過多の場合、預かった消費税より支払った消費税が多くなり還付を受けられます。
また、不動産業でオフィスビル等を購入したケースでは、購入時に支払った消費税がテナントへの課税賃貸料収入より大きければ還付となります。不動産の用途によっては課税売上が見込めず本来控除できないケースもあるため、一部では還付を得る目的で物件の用途変更を行うようなスキームが問題視されたこともあります(住宅貸付は非課税のため、購入後に課税事業への転用を経て還付を受ける手法など)。この分野について税制改正で調整措置が講じられ、意図的な還付取得を防ぐルールが整備されています。【※注: 不動産に係る調整仕入税額制度(課税資産の譲渡等の割合が著しく変動した場合の調整)】 取引形態の特殊例として、輸出代行業者の利用があります。メーカー等が直接海外顧客に販売せず、国内の輸出代行業者(商社)に販売して輸出を委託する場合、税関への輸出申告は代行業者名義で行われます。このままではメーカーから見ると国内取引(課税売上)に留まり消費税を納める立場になってしまいかねません。
しかし、実務上は輸出代行を利用しても輸出免税適用を受ける手続きが用意されています。具体的には、メーカー(輸出者)が輸出許可書等の写しを入手して保管しつつ、代行業者に対し「当該取引は輸出免税の適用を受けない」旨の通知(国税庁様式「消費税輸出免税不適用連絡一覧表」)を送付します。
代行業者はその連絡一覧表のコピーを自社の申告時に添付し、当該取引について自社では輸出免税を請求しないことを税務署に明らかにします。
こうした措置により、実質的な輸出者であるメーカー側でその取引を免税売上として扱い、仕入税額の還付を受けることが可能となります。
このような対応は輸出代行を頻繁に利用する業種(中小メーカーなど)では重要で、適切に手続きをしないと消費税の二重計算や還付漏れが発生し得るので注意が必要です。
日本の国税局の告発事例
消費税還付制度を悪用した不正行為に対しては、国税当局が厳しい姿勢で臨んでおり、実際に告発(刑事訴追)された事例も報告されています。国税庁の発表によれば、2023年度だけで消費税の不正還付により16件の告発が行われており、不正還付額は総額約4億5,400万円に上りました。
こうした不正は年々巧妙化しており、国税局は消費税還付申告に対する調査を強化しています。
近年明らかになった大規模不正の一例に、調剤薬局チェーンによる架空取引を利用した消費税不正還付事件があります。
このケースでは、処方箋医薬品販売が主で本来は非課税売上(社会保険診療)となる薬局グループが、グループ内で実態のない医薬品売買をでっち上げ、課税売上割合を意図的に引き上げていました。
課税売上割合を水増しすることで、本来控除できないはずの非課税売上対応仕入に係る消費税まで控除し、結果として約16億円もの消費税を不正に還付申告していたのです。
この不正は札幌国税局が関連会社の調査で疑いを掴み、大阪国税局や東京国税局と連携した広域調査によって発覚しました。
グループ企業は追徴課税として重加算税を含む約23億円を修正申告し、国税当局から告発される事態となっています。
国税庁全体で見ても、この大阪国税局管内の事例は規模が突出しており、当局が不正還付に警鐘を鳴らす契機となりました。
他にも架空の輸出取引を装った不正還付の事例があります。例えば2019年12月23日の津地方裁判所の判決では、ある企業が存在しない輸出免税売上と架空の課税仕入を計上し、不正に消費税還付を受けていた事実が認定されています。
このように、実際には輸出していないにもかかわらず書類を偽装して還付金を騙し取る手口は過去にも発生しており、税務当局は偽装された輸出許可証や取引請求書の発見に努めています。不正還付が発覚した場合、消費税法違反(偽りその他不正行為による還付受領)として告発され、裁判で有罪となれば重い罰則が科されます。加えて、追徴税として本税に最大40%の重加算税が付されるなど経済的不利益も非常に大きくなります。
国税局は近年、還付申告に対する審査を一層厳格化しています。特に高額還付が継続する輸出企業や、不自然な取引を含む申告には重点的に実地調査を実施し、不正の摘発に力を入れています。国税庁の統計でも還付申告に対する調査件数や追徴事例が報告されており、不正抑止の効果もあってか年々不正件数自体は横這いから微減傾向にあります。
いずれにせよ、正当な輸出取引に基づく還付は適法に受けられますが、虚偽の還付申請は高確率で発覚し告発リスクを伴うことに留意すべきです。適切な範囲で消費税還付制度を利用しつつ、法令遵守のもと健全な資金繰りに役立てることが重要です。
日本の輸出事業における消費税還付

輸出事業における消費税還付について、その仕組みや還付を受けるための条件、業種ごとの特殊性や告発事例などを弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
消費税還付の仕組み
日本の消費税は「仕入れに係る消費税額」を「売上に係る消費税額」から差し引いて納付額を計算する仕組みです。
輸出取引は消費税法上 輸出免税(税率0%)の対象となるため、海外への商品販売や国外向けサービス提供には消費税が課税されません。
したがって輸出売上には消費税が発生しない一方、国内で仕入れや経費に支払った消費税(入力税額)は控除可能であり、売上に係る消費税額より仕入れに係る消費税額の方が大きい場合、その差額が還付されます。
例えば、輸出売上200万円(税抜)に対する消費税0円と、仕入150万円(税抜)に対する消費税15万円では、15万円の還付を受けられます。
消費税還付を受けるための条件
消費税還付を受けるにはいくつかの条件があります。
①課税事業者であること
課税事業者であることが必要です。
前々年度の課税売上高が1000万円以下の事業者(免税事業者)は原則として消費税の納税義務がなく、消費税申告を行わないため還付も受けられません。ただし、免税事業者でも「課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になる選択をすれば還付申請が可能です。
新設法人も原則初年度は免税事業者ですが、資本金1000万円以上など一定の場合は最初から課税事業者となります。
②原則課税で申告計算していること
原則課税で申告計算(課税期間中の課税売上げに係る消費税額-課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額=消費税額)していることも条件です。消費税の簡易課税制度を適用(課税期間中の課税売上げに係る消費税額に、事業区分に応じた一定の「みなし仕入率」を掛けた金額を課税仕入れ等に係る消費税額とみなして、納付する消費税額を計算)している場合、実額に基づく仕入税額控除が行えず還付を受けられないためです。
③確定申告で還付申告を行うこと
還付を受けるためには該当期間について確定申告で還付申告を行うことが前提となります。
④輸出免税に該当する売上であること
取引面では、輸出免税に該当する売上であることが必要です。
輸出免税の適用範囲には、例えば「日本国内から海外への商品の輸出」「国際運送や国際通信」「非居住者への特許や著作権など無形財産権の提供」「非居住者への役務提供」などが含まれます。
これら輸出取引に該当する売上であれば税率0%となり、対応する仕入税額の還付を受けられます。
ただし非居住者相手のサービスでも、日本国内で直接便益を受けるもの(例:国内での宿泊・飲食提供など)は輸出取引とみなされず課税対象です。
なお、輸出免税の適用を受けるにはその取引が輸出であることを証明する書類を備えることが求められます。
申請手続きや必要書類
消費税の還付は所轄税務署への消費税確定申告を通じて申請します。法人の場合、事業年度終了日の翌日から2か月以内(個人事業主は翌年3月31日まで)に確定申告書を提出する必要があります。
還付申告の際には、以下の書類を提出します。
・消費税及び地方消費税の確定申告書(主たる申告用紙)
・付表2「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算書」(売上高に占める課税売上割合や控除仕入税額を計算する明細)
・消費税の還付申告に関する明細書(還付となる理由や取引ごとの売上・仕入明細を記載した書類)
確定申告書に還付額を計算の上で提出すると、税務署による内容確認を経て還付金の支払い決定がなされます。
輸出取引による還付を申告する場合、輸出売上に対応する還付額と国内売上に対する納付額をまとめて申告することになるため、輸出事業と国内事業の両方がある場合は申告書上で相殺計算する点に注意が必要です。
還付申告の証拠書類の用意
還付申告の証拠書類として、輸出取引であることを示す資料を準備・保管する必要があります。
輸出する商品のケースでは税関の輸出許可書(税関長の証明付き)を用意しなければなりません。
20万円以下の少額輸出で通常郵便物を使う場合は、日本郵便が発行する引受証明書(品名・数量・価額の記載されたもの)が証拠書類となります。
サービス提供や無形資産の提供など物品以外の輸出取引では、契約書など取引内容と国外提供であることを示す書面が必要です。
これらの書類は申告時に提出を求められる場合もあるため、輸出許可証や契約書類の原本を手元に保管しておくことが重要です。
特に輸出代行業者が輸出手続きを代行した場合でも、自社が還付を受けるには輸出許可書等の原本保管と所定の通知手続きを行う必要があります。
なお、輸出免税の証拠書類や帳簿は7年間の保存義務があります。
消費税の還付申告を行うと、原則として税務署による税務調査や審査の対象となります。
還付申告額が大きい場合や内容に不明点がある場合には、書面照会や実地調査によって輸出の実態や仕入控除の妥当性が確認されます。不備や誤りがあれば還付は認められません。
そのため、日頃から取引証憑の整備や正確な帳簿記録を行い、還付申告に備えることが大切です。
対象となる事業者の要件
①課税事業者であること
消費税還付を受けられる事業者は、課税事業者に限られます。
免税事業者の場合、消費税の申告義務がないため、たとえ輸出取引があっても仕入税額の還付を受けることはできません。
輸出を行う企業・事業者であれば、規模が小さく基準売上高1000万円以下でも、必要に応じて課税事業者選択届出を提出し課税事業者となることで還付申請が可能となります。
これは、輸出で仕入税額が多額になる場合、還付を受けられるよう自主的に課税事業者になる選択が有利となるためです(届出を適用する課税期間開始前日までに提出)。
②仕入税額控除の適用要件を満たすこと
還付を受けるには課税売上に対する仕入税額控除の適用要件を満たす必要があります。具体的には、帳簿及び適格請求書(インボイス)等の保存要件を満たし、課税仕入れについて適法に税額控除できる状態であることが重要です(2023年10月以降インボイス制度開始により、適格請求書等の保存が仕入税額控除の要件)。
輸出免税となる売上であっても、帳簿・証憑不備で仕入税額控除が否認されると結果的に還付も受けられなくなるため注意が必要です。
対象となる取引
輸出取引の種類については、前述したように商品の国外輸送による販売だけでなく、国外向けの役務提供や無形資産の譲渡も含まれます。
例えばメーカーが製品を海外顧客に直接販売するケース、商社が国内商品を買い付けて海外に輸出するケース、ソフトウェア企業が海外法人にソフトを提供するケースなどが該当します。これらはいずれも法律上は課税取引扱いで免税となるため、それに要した仕入や経費の消費税は全額控除・還付対象となります。
一方、非課税取引(例:国内の医療、教育、住宅の賃貸、金融など)や不課税取引(給与支払い、寄附など)はそもそも課税対象外であり、対応する仕入税額は控除できません。
輸出取引は非課税ではなく「課税対象だが税率0%」という位置付けのため、国内課税取引と同様に仕入税額控除が可能である点が大きな特徴です。
したがって、輸出売上を有する事業者は、たとえ売上に消費税がかからなくても課税事業者でありさえすれば仕入税額の還付を受けられます。
ただし事業者によっては、課税売上と非課税売上が混在する場合もあります。例えば国内で医薬品販売(社会保険診療は非課税)と輸出販売を併営するようなケースでは、非課税売上に対応する部分の仕入税額は控除できないため、その部分は還付対象外となります。
このように、還付を受けられる仕入税額はあくまで課税売上(輸出を含む)に紐づく部分のみである点に留意が必要です。
還付の受け取りの方法や期間
①還付金の受け取り方法
還付金の受け取り方法は、申告時に指定した銀行口座への振込か、ゆうちょ銀行・郵便局窓口での受領の2通りがあります。
一般には口座振込が利用されますが、口座名義は申告者本人または納税管理人名義である必要があります。
②還付金が振り込まれるまでの期間
消費税還付が振り込まれるまでの期間は、申告から概ね1~2か月程度が一般的な目安です。
税務署による申告内容の確認や書類チェックにある程度時間を要するため、還付金の入金完了まで数週間から数ヶ月かかるのが通常です。
ただし、電子申告(e-Tax)を利用した場合は処理が迅速化される傾向があり、早ければ提出後2~3週間で還付されるケースもあります。
実際、繁忙期でない時期にe-Taxで申告書を送信すれば1か月以内に振り込まれる例も報告されています。
一方、2月~3月の確定申告シーズンは事務処理が立て込むため、通常より時間がかかる可能性があります。
資金繰り上、還付金を早めに受け取りたい場合は、できるだけ早期に申告手続きを行い、e-Taxを活用するのが望ましいでしょう。
還付額が継続的に発生する輸出業者では、資金繰りの観点から還付を迅速に受けるための制度活用も有効です。例えば課税期間の短縮特例を利用すると、通常1年ごとの課税期間を四半期毎や月毎に区切って申告できるため、還付発生時期を早めることができます(適用には事前に「課税期間特例選択届出書」を提出し2年間の継続適用が必要です)。
申告期限を徒過した場合の不利益
申告期限は厳守する必要があります。法人の場合、課税期間(事業年度)終了日の翌日から2ヶ月以内が確定申告の法定期限であり、これを過ぎると期限後申告となります。期限後申告でも還付自体は受けられますが、その場合税務上いくつかの不利益があります。
①還付加算金の計算起点の繰り下がり
還付加算金(税務署から支払われる利息相当額)の計算起点が繰り下がります。
通常、適法な期限内申告で還付となった場合、申告期限の翌日から還付される日までの期間について年利により算出した還付加算金が支払われます(国税通則法第58条)。
税務署側の処理遅延については、法律上、還付申告に対する還付金は速やかに支払うものとされています。万一、税務署の事情で大幅に還付が遅れる場合には、その期間に応じた還付加算金が付されます。
実務上は申告から1~2ヶ月程度で還付されることがほとんどですが、仮に調査が長引く等で還付が遅れた場合でも、納税者には一定の利息補填がなされる仕組みです。
しかし期限後申告で還付を受ける場合、加算金の起算日は本来の期限ではなく、課税期間終了後2ヶ月経過日や申告書提出日の属する月末などに修正されます。
その結果、期限内申告に比べて遅延した期間分の利息が付かなくなる(事実上、還付が遅れるだけ損をする)ことになります。
②ペナルティ
また、期限後申告そのものに対して無申告加算税などのペナルティが課される可能性もあります。
以上から、還付を確実かつ有利に受けるためには申告期限内に正確な申告を行うことが重要です。
業種による消費税還付の状況
①製造業の場合
メーカーの場合、製品を海外に輸出すれば売上に対する消費税は0%ですが、生産に必要な原材料費や設備投資には国内で消費税を支払います。輸出比率が高い製造業者ほど、支払った消費税額が預かった消費税額を上回りやすく、多額の還付を受ける傾向があります。
実際、日本を代表する自動車メーカー等の大企業は毎年巨額の消費税還付を受けており、2022年度には輸出大企業上位20社で合計約1兆9千億円もの消費税が国から還付されたとの推計もあります。
②貿易会社の場合
貿易会社でも、例えば、国内メーカーから商品を税込仕入して輸出すれば、仕入時の消費税分が丸ごと還付対象となります。貿易業者にとって消費税還付は重要な資金源とも言え、適切な手続きによりキャッシュフローを確保することができます。
③サービス業の場合
サービス業においても、提供先が海外(非居住者)でサービスの消費が国外で完結する場合は輸出免税が適用されます。
国際通信サービス、国際輸送サービス、海外法人向けのコンサルティングやエンジニアリング、ソフトウェア・デザインの提供、特許やライセンス供与などは非居住者に対する役務提供として消費税が免税になります。
その結果、国内で要した人件費以外の経費(オフィス賃料や機器購入費用など)に含まれる消費税の還付を受けられます。例えば日本のIT企業が海外企業と契約して開発サービスを提供する場合、売上に消費税は発生しませんが、国内で購入したパソコンやソフトウェア、通信費等の消費税は全て控除・還付されます。
一方、旅行業やホテル業など訪日外国人相手のサービスは、そのサービス提供が日本国内で行われ直接便益を享受させるもののため免税にならず、通常通り課税となります。
このようにサービス業でも取引の性質によって消費税の扱いが異なり、国外向けサービスを主とする事業者は輸出産業同様に還付を受けるケースがあります。
特別なケース
特別なケースや過去の事例としては、事業構造や取引形態に起因する消費税還付があります。例えば、設立初年度に巨額の設備投資を行った場合です。工場建設や大型機械の購入などで一時的に多額の消費税を支払うと、売上が立つ前でもその分の消費税は還付申告により取り戻すことができます。実際、赤字や経費過多の場合、預かった消費税より支払った消費税が多くなり還付を受けられます。
また、不動産業でオフィスビル等を購入したケースでは、購入時に支払った消費税がテナントへの課税賃貸料収入より大きければ還付となります。不動産の用途によっては課税売上が見込めず本来控除できないケースもあるため、一部では還付を得る目的で物件の用途変更を行うようなスキームが問題視されたこともあります。この分野について税制改正で調整措置が講じられ、意図的な還付取得を防ぐルールが整備されています。
日本の国税局の告発事例
消費税還付制度を悪用した不正行為に対しては、国税庁が厳しい姿勢で臨んでいます。国税庁によれば、不正は年々巧妙化しており、国税局は消費税還付申告に対する調査を強化しています。
近年明らかになった大規模不正の一例に、調剤薬局チェーンによる架空取引を利用した消費税不正還付事件があります。
このケースでは、処方箋医薬品販売が主で本来は非課税売上(社会保険診療)となる薬局グループが、グループ内で実態のない医薬品売買をでっち上げ、課税売上割合を意図的に引き上げていました。
課税売上割合を水増しすることで、本来控除できないはずの非課税売上対応仕入に係る消費税まで控除し、結果として約16億円もの消費税を不正に還付申告していたのです。
この不正は札幌国税局が関連会社の調査で疑いを掴み、大阪国税局や東京国税局と連携した広域調査によって発覚しました。
グループ企業は追徴課税として重加算税を含む約23億円を修正申告し、国税当局から告発される事態となっています。
国税庁全体で見ても、この大阪国税局管内の事例は規模が突出しており、当局が不正還付に警鐘を鳴らす契機となりました。
他にも架空の輸出取引を装った不正還付の事例があります。例えば2019年津地方裁判所の判決では、ある企業が存在しない輸出免税売上と架空の課税仕入を計上し、不正に消費税還付を受けていた事実が認定されています。
このように、実際には輸出していないにもかかわらず書類を偽装して還付金を騙し取る手口は過去にも発生しており、国税当局は偽装された輸出許可証や取引請求書の発見に努めています。
不正還付が発覚した場合、消費税法違反(偽りその他不正行為による還付受領)として告発され、裁判で有罪となれば重い罰則が科されます。加えて、追徴税として重加算税が付されるなど経済的不利益も非常に大きくなります。
国税局は近年、還付申告に対する審査を一層厳格化しています。特に高額還付が継続する輸出企業や、不自然な取引を含む申告には重点的に実地調査を実施し、不正の摘発に力を入れています。
国税庁の統計でも還付申告に対する調査件数や追徴事例が報告されており、不正抑止の効果もあってか年々不正件数自体は横這いから微減傾向にあります。
いずれにせよ、正当な輸出取引に基づく還付は適法に受けられますが、虚偽の還付申請は高確率で発覚し告発リスクを伴うことに留意すべきです。適切な範囲で消費税還付制度を利用しつつ、法令遵守のもと健全な資金繰りに役立てることが重要です。
消費税不正還付事案の紹介と対応④(4/4)

消費税の不正還付事案について、手口や告発事例、不正が発覚した場合の対応などについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所がシリーズで解説します。
最終回、第4回目の今回は、税務調査の流れと不正が疑われた際の対応について解説します。
税務調査の流れ
税務調査は、納税申告内容の正確性を確認するために税務署等が行う検査です。消費税の還付申告を行う事業者は特に注意が必要で、申告内容に不審な点があれば調査の対象となる可能性があります。調査は大きく分けて2段階あります。
①任意調査(通常の税務調査)
まずは税務署による任意の調査が行われます。調査官から帳簿や請求書の提出を求められたり、ヒアリングを受けたりする形で進みます。還付申告の場合、特に仕入れや輸出の記録について詳細に確認されるでしょう。
ここで事実と異なる申告が見つかった場合、修正申告を求められ追徴課税(加算税を含む)を受けることになります。
重要なのは、この段階ではまだ刑事手続きではないため、調査官の質問等には可能な限り誠実に対応し、不審を持たれる行為(記録の廃棄、改ざんなど)は絶対にしないことです。
仮に申告ミスや誤りに気付いた場合は、調査が本格化する前に自主的に修正申告を行い不足税額を納付することで、重加算税の免除や告発の回避につながる場合もあります。「うっかりミス」と「悪質な仮装・隠蔽」では当局の対応も大きく異なりますので、意図的な不正でなくとも迅速に正す姿勢が肝心です。
②強制調査(査察調査)
調査の結果、悪質な仮装・隠蔽が疑われ、金額も大きい場合には、税務署レベルから国税局査察部(マルサ)に案件が引き継がれ、刑事告発を見据えた強制調査が行われます。
査察調査では裁判所の令状に基づき家宅捜索や帳簿・PCの押収などの強制力をもった調査が実施され、関係者に対する取り調べも行われます。
この段階に至った場合、基本的に事件は刑事告発→起訴へ進む前提で調査が行われます。一年間にわたる内偵・強制調査の末に告発となるケースもあり、調査期間中は関係者は長期間に及ぶプレッシャーに晒されることになります。
不正が疑われたときに取るべき対応
まず第一に「証拠隠しや虚偽説明は厳禁」です。
不正の事実をごまかそうとして帳簿を改ざん・廃棄したり、関係者に口裏合わせを指示したりすれば、かえって仮装・隠蔽の意図を明白に示すこととなり、情状は悪化します。調査官からの質問には事実関係を確認しつつ慎重に答える必要がありますが、自身で判断が難しい場合はその場で無理に断定せず、「後日資料を提出させてください」など柔軟に対応しましょう。
任意調査の段階で専門家の助言を受けることも検討すべきです。税理士や弁護士は、調査官とのやり取りに同席したり資料提出の代理をしたりといったサポートが可能で、適切な対応によって調査官の心証を害さず誤解を解く助けとなります。
もし既に査察部による強制調査に入ってしまった場合は、速やかに弁護士に連絡することが肝要です。強制調査では逮捕・起訴の可能性が現実味を帯びるため、以降は刑事弁護の視点で戦略を立てる必要があります。自宅や事務所への家宅捜索が入った時点で、「これは単なる税務調査ではなく刑事事件になるかもしれない」と覚悟し、すぐに刑事弁護に明るい弁護士に相談してください。
弁護士の役割と早期相談の重要性
消費税の不正還付に関する疑いをかけられた場合、早期に弁護士に相談することが極めて重要です。不正還付は単なる税務上の違反にとどまらず、刑事事件へと発展する可能性が高い性質を持ちます。特に査察(マルサ)の強制調査が入った段階では、もはや専門家の助力なしに適切に対応することは困難です。
何より大切なのは早めの段階で相談することです。査察が入った段階から弁護士に相談し今後の対応を協議・準備しておけば、逮捕や起訴を避けたいという要望に沿って適切な対策を打つことができます。
逆に対応が後手に回ると、取り調べで不利な供述をしてしまったり、押収された証拠に適切な反論ができなかったりと、防御が難しくなります。「もしかするとまずいことをしてしまったかもしれない」「税務署から問い合わせが来ている」「周囲で同様の調査が入った」という段階でも、疑いがあるなら一刻も早く専門家に相談するのが得策です。
弁護士は依頼者の権利と利益を守るプロフェッショナルです。不正還付の疑いをかけられた場合、事実関係の如何にかかわらず、独断で動くのではなく必ず専門家の力を借りてください。それが、最終的にリスクを最小限に抑え、企業経営や人生を立て直すための第一歩となります。
まとめ
以上、消費税の不正還付の典型的手口から具体例、処罰の内容、そして発覚時の対応まで詳しく説明しました。不正還付は一時的に資金繰りを潤すように見えても、発覚すれば取り返しのつかない損失とリスクを招きます。適正な申告と納税が企業経営の大前提であり、万が一にも疑わしいスキームに手を出さないことが肝要です。万一、「これはもしかして…」と後になって気付いた場合や、税務署から問い合わせや調査の連絡が来た場合には、できるだけ早く信頼できる専門家(税理士・弁護士)に相談し、適切な対応をとってください。それが自身と会社を守る最善の策と言えるでしょう。
消費税不正還付事案の紹介と対応③(3/4)

消費税の不正還付事案について、手口や告発事例、不正が発覚した場合の対応などについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所がシリーズで解説します。
第3回目の今回は、不正還付が発覚した場合のペナルティ(刑事罰・行政処分)について解説します。
不正還付が発覚した場合のペナルティ①追徴課税
不正還付が明るみに出た場合、極めて厳しいペナルティが科されます。
まず、騙し取った還付金は全額返還させられるのは当然として、追徴課税として重加算税などの加算税が課されます。重加算税とは、納税者が仮装・隠ぺい(意図的な事実の偽装や記録の隠蔽)によって税金を免れようとした場合に科される最も重いペナルティ税で、本来納めるべき税額の35%(重加算税率は原則35%ですが、期限後申告や無申告の場合は40%とされる場合があります。また消費税の還付申告に係る特例措置として加算税率引上げが行われた時期もあります。具体的な適用税率は違反時期の法令によります。)が追加で課されます。
例えば実際にあった架空輸出事件では、不正還付額約3,300万円に対し重加算税を含む追徴税額が約4,400万円と公表されており、重加算税だけで約1,100万円(元の不正額の約33%)が上乗せされている計算になります。過少申告加算税(10~15%)などと異なり、重加算税は「仮装・隠蔽」という明確な不正行為があった場合に適用されるため、企業にとって大きな痛手となります。
不正還付が発覚した場合のペナルティ②刑事罰
次に、悪質なケースでは刑事罰が科される可能性があります。
国税局の査察調査によって「告発相当」と判断された事案では、検察庁に告発され、加害者(法人および経営者等)は刑事裁判にかけられます。
消費税法には脱税や不正受還付に対する罰則規定があり、「偽りその他不正の行為」により消費税を免れたり不正に還付を受けた者は「10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(もしくはその両方)」に処せられると定められています。これは他の税法違反(法人税法・所得税法等)と同等であり、刑法上の詐欺罪(10年以下の懲役)にも匹敵する非常に重い刑罰です。
実際に、不正還付事件で経営者が逮捕・起訴され、有罪判決を受けた例も数多くあります。多くの場合、初犯で追徴税も納付済みであれば執行猶予付き判決となるケースが見られますが、悪質度や金額によっては実刑判決が言い渡されます。
平成30年度には消費税不正還付事件で代表者に懲役4年6月の実刑が科された例が報告されており、令和4年度にも査察事案全体で3名が実刑判決、うち1件は他の犯罪と合わせ懲役6年の重い実刑判決となっています。
不正還付が発覚した場合のペナルティ③行政処分
さらに、行政上の処分も考えられます。
免税店(輸出物品販売場)の許可を受けている事業者がその制度を悪用した場合、免税販売許可の取消という処分を受ける可能性があります。
例えば前述の免税店不正に関する報道では、東京国税局が虚偽の免税販売をしていた約10店舗の免税店許可を一斉に取り消したことが伝えられています。
許可取消になれば免税販売(外国人向け消費税免税販売)業務は続けられなくなり、事業継続に大打撃となります。
また、不正行為が明るみに出ることで企業名の公表や報道により社会的信用を喪失し、取引先や顧客からの信頼も失うでしょう。場合によっては経営破綻に至るリスクもあります。
続きは第4回で
このように、不正還付が発覚すれば経済的制裁から刑事罰、営業上の許可取消、信用失墜に至るまで多方面の深刻なペナルティを受けることになります。不正は絶対に割に合わないばかりか、経営者自身の人生や会社の存続をも脅かしかねません。
次回第4回(最終回)では、税務調査などの調査の流れと、不正還付を疑われた場合の対応について解説します。
消費税不正還付事案の紹介と対応②(2/4)

消費税の不正還付事案について、手口や告発事例、不正が発覚した場合の対応などについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所がシリーズで解説します。
第2回目の今回は、国税庁による告発事例を紹介します。
国税庁や各国税局は、不正還付を行った事案について積極的に刑事告発(検察庁に告発)し、その内容を報道発表等で公表しています。以下に、実際に発覚した不正還付の事例をいくつか取り上げ、その手口等を紹介します。
架空の革製品輸出で消費税還付を詐取した事例
大阪国税局は2024年2月、輸出免税制度を悪用して消費税約3,300万円の還付金を不正受給したとして、神戸市の元貿易業の男性を消費税法違反などの疑いで神戸地方検察庁に告発しました。
この男性は、2020年1月〜2022年12月に国内で仕入れた革製品をあたかも海外に輸出したように装い、架空の輸出取引を申告して還付金を受け取っていた疑いがあります。追徴税額(本税と重加算税を含む)は約4,400万円に上り、不正還付額(約3,300万円)を大きく上回る額を徴収されています。
これは架空輸出を用いた典型的な不正還付事件であり、国税局査察部の調査により発覚・告発に至ったものです。
パワーストーン架空仕入れスキームによる還付未遂事件
大阪国税局は令和4年度に、複数企業が共謀したパワーストーン仕入れを装う不正還付未遂事件を告発しています。
この事件では、B社ほか数社が不正指南者の指示のもと、各社の代表者から高額なパワーストーンを購入したと偽り、架空の課税仕入れを計上して還付申告を行っていました。
還付が成功すれば国庫から多額の消費税が騙し取られるところでしたが、税務当局がスキームを解明し、法人および代表者、さらに黒幕である指南役までを含め刑事告発しています。
これは、複数の事業者とブローカー的存在が組んだ組織的脱税スキームの一例であり、国税庁が「重点事案」として対処したケースです。
偽装化粧品輸出(実態は飲料水)による巨額不正還付事件
東京国税局が調査したある事件では、東京都内の化粧品卸売会社が複数の輸出代行業者と結託し、実際には市販のミネラルウォーターを高級化粧品に偽装して巨額の輸出取引を装う手口が発覚しました。
この会社は「約2年間で総額370億円相当の高級化粧品を仕入れて輸出業者へ販売した」と虚偽申告し、輸出業者側は「その化粧品を香港に輸出した」として消費税の還付を受けていたのです。
しかし税務調査の結果、実際に取引されていたのは市価が僅かなボトル飲料水であり、売買記録や請求書類はすべて架空と判明しました。
東京国税局はこの会社に対し約35億円もの追徴課税(還付された消費税約30億円+重加算税等)を行い、共謀した輸出業者約10社にも合計9億円の追徴課税処分を下しました。
この事件は刑事告発に関する報道はありませんが、関与事業者は免税店の許可取消や厳しい行政処分も受けています。
実際、東京国税局は2023年2月までに同様の不正を行っていた都内の免税店約10店舗の免税販売許可を剥奪する処分を行っています。
その他の事例
上記以外にも、免税店で架空の外国人客に大量購入させたよう装うケース、輸出用の中古車台数を水増しして申告した中小企業の事件(2016~18年で約1.39億円の不正還付、2021年に名古屋地検が社長ら逮捕)など、不正還付の事例は全国で報告されています。
いずれも共通するのは、「実態のない取引」を作り出すことで消費税の計算構造を逆手に取り、還付という形で税金を不正に入手しようとする点です。
国税当局はこうした事案に対し、精密な取引追跡や帳簿類の押収・解析を駆使して実態解明を行い、悪質性が高いと判断すれば積極的に刑事告発しています。
続きは第3回で
今回は消費税不正還付に関して国税局が実際に告発した事例を紹介しました。
第3回では、不正還付が発覚した場合のペナルティについて解説します。
消費税不正還付事案の紹介と対応①(1/4)

消費税の不正還付事案について、手口や告発事例、不正が発覚した場合の対応などについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所がシリーズで解説します。
第1回目は、消費税不正還付の概要と、よくある不正還付の手口について、解説します。
消費税の不正還付とは?
消費税の不正還付とは、本来受け取る資格のない消費税の還付金を、虚偽の申告など不正な手段によってだまし取る行為です。
消費税は事業者が売上に係る消費税(預かった消費税)から仕入れに係る消費税(支払った消費税)を差し引いて納税し、不足があれば還付を受けられる仕組みです。
例えば、事業が赤字の場合や大きな設備投資をした場合、そして輸出取引を行う場合(輸出免税)には、支払った消費税が預かった消費税より多くなり、差額の還付を受けられます。
しかし、この制度を悪用して虚偽の取引をでっち上げ、本来は発生していない仕入税額控除(事業者が課税売上に係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額を控除できる制度のこと。仕入れや経費で支払った消費税を差し引けるため、輸出取引のように売上の消費税が少ない場合は還付(払いすぎた税の返還)を受けることができる。)を水増しすることで還付金を騙し取る事例が後を絶ちません。
国税庁もこのような不正受還付事案は「いわば国庫金の詐取ともいえる悪質性の高い事案」であると位置付けており、重点的に摘発しています。平成30年度(2018年度)には過去5年で最多の6件・総額14億円規模の消費税不正還付事案を告発し、消費税不正還付事件で懲役4年6月の実刑判決が言い渡された例もあります。
近年も摘発件数は増加傾向にあり、令和4年度(2022年度)は16件もの不正還付事案が刑事告発されるなど、国税当局は厳しい姿勢で臨んでいます。
よくある不正還付の手口
消費税の不正還付は、主に仕入税額控除制度や輸出免税制度といった仕組みの盲点を突いて行われます。典型的な手口をいくつか紹介します。
①架空の輸出取引をでっち上げる(輸出免税の悪用)
輸出取引は消費税が課税されないため(輸出免税制度)、輸出業者は国内で仕入れた商品の消費税分を国から還付してもらえます。
この仕組みを悪用し、実際には存在しない輸出を装って還付を受けるケースがあります。
例えば、事業者が架空の輸出売上を計上し、本当は国内で消費されている商品を「海外に販売した」ことにして消費税の免税を受ける手口です。実際に、大阪国税局が告発した事例では、日用品の輸出販売等を行うA社が、不正協力者と共謀し、存在しない化粧品の仕入れをでっち上げ(架空の課税仕入れ)た上で、それら化粧品を輸出物品販売場(免税店)で外国人観光客に販売したように見せかけることで架空の免税売上を計上し、不正に消費税の還付申告を行っていました。
近年では、偽造した書類や他人のパスポート情報まで利用し、同じ高級腕時計を何度も輸出したように偽装する、あるいはコンビニの商品について偽のパスポート情報で免税販売記録を作成するといった巧妙なケースも発覚しています。これらはいずれも存在しない輸出(または免税販売)を装って仕入税額控除を受け、還付金を騙し取ろうとする悪質な手口です。
②架空の仕入取引を計上する(仕入税額控除の水増し)
もう一つ多い手口は、架空の仕入をでっち上げて支払った消費税を水増しし、還付額を吊り上げる方法です。
消費税の仕入税額控除とは、仕入や経費にかかった消費税額を売上にかかる消費税額から控除できる制度のことです。
不正行為者は、この控除額を大きく見せるために実際には購入していない商品を購入したことにし、偽造請求書や架空の領収書を用いて虚偽の申告を行います。
例えば、不正指南役の人物が複数の法人に「パワーストーンを仕入れたことにせよ」と指示し、各社が代表者個人からパワーストーンを購入したかのように仮装取引を行って架空の課税仕入れを計上したケースがあります。このケースでは、還付を受けようとした複数法人とその代表者だけでなく、スキームを考案した指南役まで含めて国税庁に告発されました。
また、キャッシュレス決済端末の販売会社が、仕入れた端末の台数を水増しして申告することで約2,400万円もの不正還付を受けていた疑いが明らかになっています。
このように架空仕入れによる水増しは、単独の会社でも行われますが、時には複数の事業者がグルになって架空の売買ネットワークを作り上げ、大規模な不正還付スキームに発展することもあります。
続きは第2回で
今回は消費税不正還付の概要とよくある手口について解説しました。
第2回では、国税庁による消費税不正還付の告発事例を紹介します。
日本の輸出事業における消費税還付③

輸出事業における消費税還付について、その仕組みなどを複数回にわたって紹介します。3回目の今回は業種による消費税還付の状況や特別なケースの紹介、不正に消費税還付を受けたことにより告発を受けた事例の紹介などを行います。
業種による消費税還付の状況
①製造業の場合
メーカーの場合、製品を海外に輸出すれば売上に対する消費税は0%ですが、生産に必要な原材料費や設備投資には国内で消費税を支払います。輸出比率が高い製造業者ほど、支払った消費税額が預かった消費税額を上回りやすく、多額の還付を受ける傾向があります。
実際、日本を代表する自動車メーカー等の大企業は毎年巨額の消費税還付を受けており、2022年度には輸出大企業上位20社で合計約1兆9千億円もの消費税が国から還付されたとの推計もあります。
②貿易会社の場合
貿易会社でも、例えば、国内メーカーから商品を税込仕入して輸出すれば、仕入時の消費税分が丸ごと還付対象となります。貿易業者にとって消費税還付は重要な資金源とも言え、適切な手続きによりキャッシュフローを確保することができます。
③サービス業の場合
サービス業においても、提供先が海外(非居住者)でサービスの消費が国外で完結する場合は輸出免税が適用されます。
国際通信サービス、国際輸送サービス、海外法人向けのコンサルティングやエンジニアリング、ソフトウェア・デザインの提供、特許やライセンス供与などは非居住者に対する役務提供として消費税が免税になります。
その結果、国内で要した人件費以外の経費(オフィス賃料や機器購入費用など)に含まれる消費税の還付を受けられます。例えば日本のIT企業が海外企業と契約して開発サービスを提供する場合、売上に消費税は発生しませんが、国内で購入したパソコンやソフトウェア、通信費等の消費税は全て控除・還付されます。
一方、旅行業やホテル業など訪日外国人相手のサービスは、そのサービス提供が日本国内で行われ直接便益を享受させるもののため免税にならず、通常通り課税となります。
このようにサービス業でも取引の性質によって消費税の扱いが異なり、国外向けサービスを主とする事業者は輸出産業同様に還付を受けるケースがあります。
特別なケース
特別なケースや過去の事例としては、事業構造や取引形態に起因する消費税還付があります。例えば、設立初年度に巨額の設備投資を行った場合です。工場建設や大型機械の購入などで一時的に多額の消費税を支払うと、売上が立つ前でもその分の消費税は還付申告により取り戻すことができます。実際、赤字や経費過多の場合、預かった消費税より支払った消費税が多くなり還付を受けられます。
また、不動産業でオフィスビル等を購入したケースでは、購入時に支払った消費税がテナントへの課税賃貸料収入より大きければ還付となります。不動産の用途によっては課税売上が見込めず本来控除できないケースもあるため、一部では還付を得る目的で物件の用途変更を行うようなスキームが問題視されたこともあります。この分野について税制改正で調整措置が講じられ、意図的な還付取得を防ぐルールが整備されています。
日本の国税局の告発事例
消費税還付制度を悪用した不正行為に対しては、国税庁が厳しい姿勢で臨んでいます。国税庁によれば、不正は年々巧妙化しており、国税局は消費税還付申告に対する調査を強化しています。
近年明らかになった大規模不正の一例に、調剤薬局チェーンによる架空取引を利用した消費税不正還付事件があります。
このケースでは、処方箋医薬品販売が主で本来は非課税売上(社会保険診療)となる薬局グループが、グループ内で実態のない医薬品売買をでっち上げ、課税売上割合を意図的に引き上げていました。
課税売上割合を水増しすることで、本来控除できないはずの非課税売上対応仕入に係る消費税まで控除し、結果として約16億円もの消費税を不正に還付申告していたのです。
この不正は札幌国税局が関連会社の調査で疑いを掴み、大阪国税局や東京国税局と連携した広域調査によって発覚しました。
グループ企業は追徴課税として重加算税を含む約23億円を修正申告し、国税当局から告発される事態となっています。
国税庁全体で見ても、この大阪国税局管内の事例は規模が突出しており、当局が不正還付に警鐘を鳴らす契機となりました。
他にも架空の輸出取引を装った不正還付の事例があります。例えば2019年12月23日の津地方裁判所の判決では、ある企業が存在しない輸出免税売上と架空の課税仕入を計上し、不正に消費税還付を受けていた事実が認定されています。
このように、実際には輸出していないにもかかわらず書類を偽装して還付金を騙し取る手口は過去にも発生しており、国税当局は偽装された輸出許可証や取引請求書の発見に努めています。
不正還付が発覚した場合、消費税法違反(偽りその他不正行為による還付受領)として告発され、裁判で有罪となれば重い罰則が科されます。加えて、追徴税として重加算税が付されるなど経済的不利益も非常に大きくなります。
国税局は近年、還付申告に対する審査を一層厳格化しています。特に高額還付が継続する輸出企業や、不自然な取引を含む申告には重点的に実地調査を実施し、不正の摘発に力を入れています。
国税庁の統計でも還付申告に対する調査件数や追徴事例が報告されており、不正抑止の効果もあってか年々不正件数自体は横這いから微減傾向にあります。
いずれにせよ、正当な輸出取引に基づく還付は適法に受けられますが、虚偽の還付申請は高確率で発覚し告発リスクを伴うことに留意すべきです。適切な範囲で消費税還付制度を利用しつつ、法令遵守のもと健全な資金繰りに役立てることが重要です。
日本の輸出事業における消費税還付②

輸出事業における消費税還付について、その仕組みなどを複数回にわたって紹介します。2回目の今回は消費税還付の対象となる事業者や取引の要件、還付受取の方法や期間などについて紹介します。
対象となる事業者の要件
①課税事業者であること
消費税還付を受けられる事業者は、課税事業者に限られます。
免税事業者の場合、消費税の申告義務がないため、たとえ輸出取引があっても仕入税額の還付を受けることはできません。
輸出を行う企業・事業者であれば、規模が小さく基準売上高1000万円以下でも、必要に応じて課税事業者選択届出を提出し課税事業者となることで還付申請が可能となります。
これは、輸出で仕入税額が多額になる場合、還付を受けられるよう自主的に課税事業者になる選択が有利となるためです(届出を適用する課税期間開始前日までに提出)。
②仕入税額控除の適用要件を満たすこと
還付を受けるには課税売上に対する仕入税額控除の適用要件を満たす必要があります。具体的には、帳簿及び適格請求書(インボイス)等の保存要件を満たし、課税仕入れについて適法に税額控除できる状態であることが重要です(2023年10月以降インボイス制度開始により、適格請求書等の保存が仕入税額控除の要件)。
輸出免税となる売上であっても、帳簿・証憑不備で仕入税額控除が否認されると結果的に還付も受けられなくなるため注意が必要です。
対象となる取引
輸出取引の種類については、商品の国外輸送による販売だけでなく、国外向けの役務提供や無形資産の譲渡も含まれます。
例えばメーカーが製品を海外顧客に直接販売するケース、商社が国内商品を買い付けて海外に輸出するケース、ソフトウェア企業が海外法人にソフトを提供するケースなどが該当します。これらはいずれも法律上は課税取引扱いで免税となるため、それに要した仕入や経費の消費税は全額控除・還付対象となります。
一方、非課税取引(例:国内の医療、教育、住宅の賃貸、金融など)や不課税取引(給与支払い、寄附など)はそもそも課税対象外であり、対応する仕入税額は控除できません。
輸出取引は非課税ではなく「課税対象だが税率0%」という位置付けのため、国内課税取引と同様に仕入税額控除が可能である点が大きな特徴です。
したがって、輸出売上を有する事業者は、たとえ売上に消費税がかからなくても課税事業者でありさえすれば仕入税額の還付を受けられます。
ただし事業者によっては、課税売上と非課税売上が混在する場合もあります。例えば国内で医薬品販売(社会保険診療は非課税)と輸出販売を併営するようなケースでは、非課税売上に対応する部分の仕入税額は控除できないため、その部分は還付対象外となります。
このように、還付を受けられる仕入税額はあくまで課税売上(輸出を含む)に紐づく部分のみである点に留意が必要です。
還付の受け取りの方法や期間
①還付金の受け取り方法
還付金の受け取り方法は、申告時に指定した銀行口座への振込か、ゆうちょ銀行・郵便局窓口での受領の2通りがあります。
一般には口座振込が利用されますが、口座名義は申告者本人または納税管理人名義である必要があります。
②還付金が振り込まれるまでの期間
消費税還付が振り込まれるまでの期間は、申告から概ね1~2か月程度が一般的な目安です。
税務署による申告内容の確認や書類チェックにある程度時間を要するため、還付金の入金完了まで数週間から数ヶ月かかるのが通常です。
ただし、電子申告(e-Tax)を利用した場合は処理が迅速化される傾向があり、早ければ提出後2~3週間で還付されるケースもあります。
実際、繁忙期でない時期にe-Taxで申告書を送信すれば1か月以内に振り込まれる例も報告されています。
一方、2月~3月の確定申告シーズンは事務処理が立て込むため、通常より時間がかかる可能性があります。
資金繰り上、還付金を早めに受け取りたい場合は、できるだけ早期に申告手続きを行い、e-Taxを活用するのが望ましいでしょう。
還付額が継続的に発生する輸出業者では、資金繰りの観点から還付を迅速に受けるための制度活用も有効です。例えば課税期間の短縮特例を利用すると、通常1年ごとの課税期間を四半期毎や月毎に区切って申告できるため、還付発生時期を早めることができます(適用には事前に「課税期間特例選択届出書」を提出し2年間の継続適用が必要です)。
申告期限を徒過した場合の不利益
申告期限は厳守する必要があります。法人の場合、課税期間(事業年度)終了日の翌日から2ヶ月以内が確定申告の法定期限であり、これを過ぎると期限後申告となります。期限後申告でも還付自体は受けられますが、その場合税務上いくつかの不利益があります。
①還付加算金の計算起点の繰り下がり
還付加算金(税務署から支払われる利息相当額)の計算起点が繰り下がります。
通常、適法な期限内申告で還付となった場合、申告期限の翌日から還付される日までの期間について年利により算出した還付加算金が支払われます(国税通則法第58条)。
税務署側の処理遅延については、法律上、還付申告に対する還付金は速やかに支払うものとされています。万一、税務署の事情で大幅に還付が遅れる場合には、その期間に応じた還付加算金が付されます。
実務上は申告から1~2ヶ月程度で還付されることがほとんどですが、仮に調査が長引く等で還付が遅れた場合でも、納税者には一定の利息補填がなされる仕組みです。
しかし期限後申告で還付を受ける場合、加算金の起算日は本来の期限ではなく、課税期間終了後2ヶ月経過日や申告書提出日の属する月末などに修正されます。
その結果、期限内申告に比べて遅延した期間分の利息が付かなくなる(事実上、還付が遅れるだけ損をする)ことになります。
②ペナルティ
また、期限後申告そのものに対して無申告加算税などのペナルティが課される可能性もあります。
以上から、還付を確実かつ有利に受けるためには申告期限内に正確な申告を行うことが重要です。
日本の輸出事業における消費税還付①

輸出事業における消費税還付について、その仕組みなどを複数回にわたって紹介します。初回は消費税還付の仕組みや消費税還付を受けるための要件、申請の手続などについて紹介します。
消費税還付の仕組み
日本の消費税は「仕入れに係る消費税額」を「売上に係る消費税額」から差し引いて納付額を計算する仕組みです。
輸出取引は消費税法上 輸出免税(税率0%)の対象となるため、海外への商品販売や国外向けサービス提供には消費税が課税されません。
したがって輸出売上には消費税が発生しない一方、国内で仕入れや経費に支払った消費税(入力税額)は控除可能であり、売上に係る消費税額より仕入れに係る消費税額の方が大きい場合、その差額が還付されます。
例えば、輸出売上200万円(税抜)に対する消費税0円と、仕入150万円(税抜)に対する消費税15万円では、15万円の還付を受けられます。
消費税還付を受けるための条件
消費税還付を受けるにはいくつかの条件があります。
①課税事業者であること
課税事業者であることが必要です。
前々年度の課税売上高が1000万円以下の事業者(免税事業者)は原則として消費税の納税義務がなく、消費税申告を行わないため還付も受けられません。ただし、免税事業者でも「課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になる選択をすれば還付申請が可能です。
新設法人も原則初年度は免税事業者ですが、資本金1000万円以上など一定の場合は最初から課税事業者となります。
②原則課税で申告計算していること
原則課税で申告計算(課税期間中の課税売上げに係る消費税額-課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額=消費税額)していることも条件です。消費税の簡易課税制度を適用(課税期間中の課税売上げに係る消費税額に、事業区分に応じた一定の「みなし仕入率」を掛けた金額を課税仕入れ等に係る消費税額とみなして、納付する消費税額を計算)している場合、実額に基づく仕入税額控除が行えず還付を受けられないためです。
③確定申告で還付申告を行うこと
還付を受けるためには該当期間について確定申告で還付申告を行うことが前提となります。
④輸出免税に該当する売上であること
取引面では、輸出免税に該当する売上であることが必要です。
輸出免税の適用範囲には、例えば「日本国内から海外への商品の輸出」「国際運送や国際通信」「非居住者への特許や著作権など無形財産権の提供」「非居住者への役務提供」などが含まれます。
これら輸出取引に該当する売上であれば税率0%となり、対応する仕入税額の還付を受けられます。
ただし非居住者相手のサービスでも、日本国内で直接便益を受けるもの(例:国内での宿泊・飲食提供など)は輸出取引とみなされず課税対象です。
なお、輸出免税の適用を受けるにはその取引が輸出であることを証明する書類を備えることが求められます。
申請手続きや必要書類
消費税の還付は所轄税務署への消費税確定申告を通じて申請します。法人の場合、事業年度終了日の翌日から2か月以内(個人事業主は翌年3月31日まで)に確定申告書を提出する必要があります。
還付申告の際には、以下の書類を提出します。
・消費税及び地方消費税の確定申告書(主たる申告用紙)
・付表2「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算書」(売上高に占める課税売上割合や控除仕入税額を計算する明細)
・消費税の還付申告に関する明細書(還付となる理由や取引ごとの売上・仕入明細を記載した書類)
確定申告書に還付額を計算の上で提出すると、税務署による内容確認を経て還付金の支払い決定がなされます。
輸出取引による還付を申告する場合、輸出売上に対応する還付額と国内売上に対する納付額をまとめて申告することになるため、輸出事業と国内事業の両方がある場合は申告書上で相殺計算する点に注意が必要です。
還付申告の証拠書類の用意
還付申告の証拠書類として、輸出取引であることを示す資料を準備・保管する必要があります。
輸出する商品のケースでは税関の輸出許可書(税関長の証明付き)を用意しなければなりません。
20万円以下の少額輸出で通常郵便物を使う場合は、日本郵便が発行する引受証明書(品名・数量・価額の記載されたもの)が証拠書類となります。
サービス提供や無形資産の提供など物品以外の輸出取引では、契約書など取引内容と国外提供であることを示す書面が必要です。
これらの書類は申告時に提出を求められる場合もあるため、輸出許可証や契約書類の原本を手元に保管しておくことが重要です。
特に輸出代行業者が輸出手続きを代行した場合でも、自社が還付を受けるには輸出許可書等の原本保管と所定の通知手続きを行う必要があります。
なお、輸出免税の証拠書類や帳簿は7年間の保存義務があります。
消費税の還付申告を行うと、原則として税務署による税務調査や審査の対象となります。
還付申告額が大きい場合や内容に不明点がある場合には、書面照会や実地調査によって輸出の実態や仕入控除の妥当性が確認されます。不備や誤りがあれば還付は認められません。
そのため、日頃から取引証憑の整備や正確な帳簿記録を行い、還付申告に備えることが大切です。
赤字と消費税

赤字企業でも、消費税を納税する義務があるのでしょうか。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
間接税と直接税
まず、今回の質問について述べる前提として、税金には間接税と直接税の2つがあります。間接税は、納税義務者(税金を国や地方自治体へ納める義務がある人)と担税者(税金を負担する人)が異なるもので、消費税がその代表で、そのほか酒税等があります。一方、直接税は、納税義務者と担税者が同じであり、法人税、所得税等が挙げられます。
赤字でも消費税の納税義務はある。
今回問題となっている「赤字企業でも納税義務があるのか」という質問に対する回答は、結論から述べると、赤字でも消費税の納税義務はあるということになります。たとえば、会社が支払う税金の場合、消費税は、法人自体が負担するものと思いがちです。しかし、実際には、消費税は、商品やサービスを購入する消費者が負担するものなのです。
もっとも、商品を購入するたびに、税務署に申告するのは煩雑で面倒であり、そのため法人や個人事業主が消費者から消費税を預かって、「代わりに」納税するしくみになっています。消費税が納税義務者と担税者が異なる間接税であるというのは、そういう意味です。
商品やサービスの価格を設定する際には、消費税分の金額を上乗せするのが通常でしょうが、この場合、法人や個人事業主は、消費者が支払うべき税金を預かっている状態なのです。したがって、赤字であるかどうかは、消費税の納税義務があるかどうかとは関係ないことになります。
消費税について確定申告をしていない場合
消費税で、確定申告が必要であるのに、申告を忘れていたり、申告漏れがあった場合には、確定申告期限前であれば直ちに、申告漏れのない確定申告を行ってください。確定申告後であれば修正申告する必要があります。とりわけ、企業が赤字の場合、経営者によっては、消費税を払わなくてよいと勘違いしている人も実際おられますので、要注意です。消費税については、その意味を正しく理解し、税額についてきちんと把握しておく必要があります。その結果、消費税を払い過ぎている場合には、消費税の還付を受けられる場合もあります。
一方、申告をしていない金額が大きくなれば査察調査の対象となって、更に悪質性が高いと判断されれば刑事事件に発展してしまう場合もあります。 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を中心として扱っていますが、税法についても知識のある弁護士がそろっています。 初回の相談は無料ですので、一度ご相談にお越しください。
« Older Entries