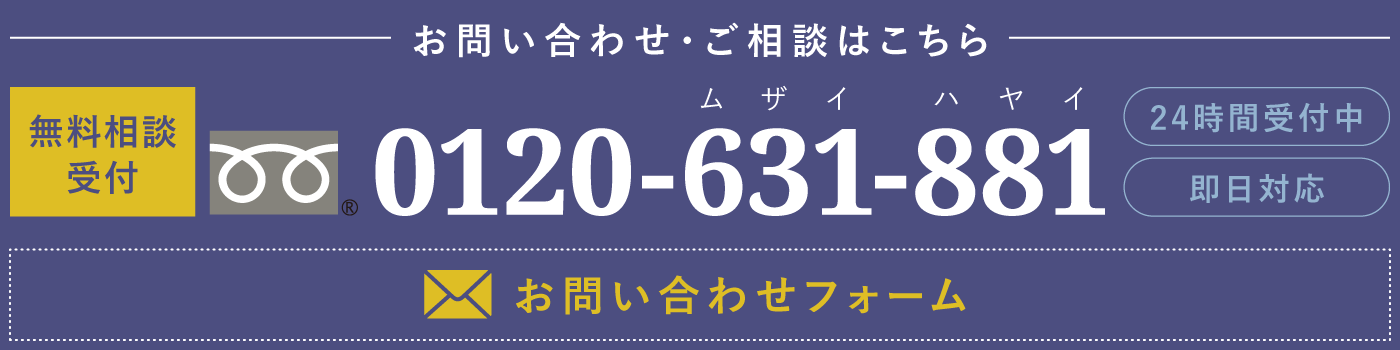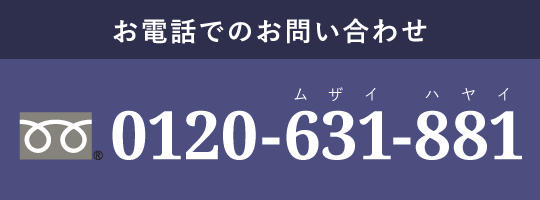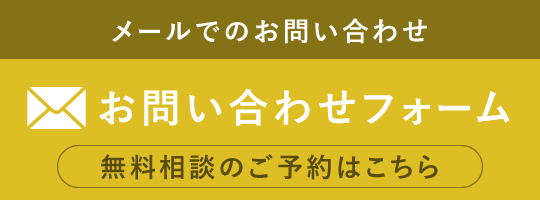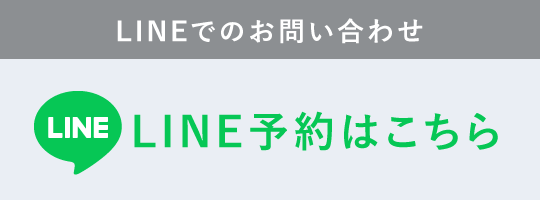Archive for the ‘税法全般’ Category
【国税庁発表】令和4年度査察の概要
国税庁が報道発表した令和4年度査察の概要について、要点をまとめてみました。
査察の概要とは
「査察の概要」は、毎年国税庁が前年度の査察調査に対する取り組みや実績を報道発表するための資料として作成されているものです。
査察調査の件数や告発件数、起訴された事件での有罪事案の紹介、不正資金の隠匿場所や告発の多かった業種などがまとめられています。
また、査察調査を行った事案についてが、その一部について事例付きで紹介されています。
令和4年度査察調査の概要は6月14日に公開されました。
令和4年度査察の概要
令和4年度の査察調査の概要としては、
①検察庁に告発した件数は103件、脱税総額(告発分)は100億円
悪質な脱税者に対して厳正な査察調査を実施し、1件当たりの脱税額は9700万円。新型コロナの影響を受けた令和3年度と比較して、告発件数及び脱税総額とも大幅に増加し、告発率は74.1%と平成18年度以来の高水準に。
②消費税事案、無申告事案、国際事案のほか、その他の時流に即した社会的波及効果の高い事案を積極的に告発
消費税事案では、不正受還付事案を多数告発。競艇情報販売をしていた個人事業者の無申告事案や大規模な国際事案を告発。そのほか、近年、市場規模が拡大しているトレーディングカード販売業者の事案、SNSを利用し多数の給与所得者に所得税の不正還付を指南していた事案や下請け業者から受けた資金提供を隠匿して自己の収入としていた元請け会社の従業員の事案など、社会的波及効果の高い事案を告発。
③一審判決61件全てに有罪判決が言い渡され、3人に対して実刑判決
実刑判決のうち、査察事件単独で最も重いものは懲役1年4月、他の犯罪と併合されたものは懲役2年8月だった。
という3項目が紹介されています。
重点事案への取り組み
重点事案への取り組みとして、以下の内容が紹介されています。
①消費税事案
消費税に対する国民の関心が極めて高いことを踏まえ、34件を告発。
消費税の仕入税額控除制度や輸出免税制度を悪用した不正受還付事案は、いわば国庫金の詐取ともいえる悪質性の高い事案であることから、16件を告発。
②無申告事案
納税者の自発的な申告・納税を前提とする申告納税制度の根幹を揺るがす無申告による逋脱犯について、15件を告発。
そのうち、不正行為はないが、故意に申告書を提出しないで税を免れた単純無申告逋脱犯を適用した事案は6件。
③国際事案
経済社会のグローバル化の進展に伴い、国境を越えた経済活動が複雑・多様化しているところ、様々な国との取引が行われており、国際取引を利用した脱税への対応が求められている。このような状況の中、外国法人を利用して不正を行っていた事案や海外に不正資金を隠しているなどの国際事案で、25件を告発。
また、外国当局と不正事案に対する取組等について情報交換を行うなど、当局間の連携強化に取り組んでいる。
④その他の社会的波及効果の高い事案
トレーディングカード販売業者の法人税逋脱事案、SNSを利用して所得税の不正還付を指南し虚偽の還付申告書を提出させた所得税不正還付事案などを告発。
不正資金の留保・費消状況及び隠匿場所
脱税によって得た不正資金の多くは、現金や預貯金として留保されていたが、不動産購入や有価証券への投資のほか、高級品の購入や遊興費への費消なども見られた。
脱税によって得た不正資金の隠匿場所として、①床下に置かれた袋の中、②銀行の貸金庫の中、③クローゼットに置かれた金庫の中などに現金を隠していた例があった。
その他参考計表
①税目別の告発件数
所得税19件、法人税47件、相続税2件、消費税34件、源泉所得税1件
②告発の多かった業種
1位:建設業 22業者、2位:不動産業 13業者、3位:小売業 12業者、4位:人材派遣業 5業者
建設業、不動産業はここ数年1位2位を占めており、取り扱う金銭の額が多いことからも査察調査で狙われやすい業種といえます。
【制度解説】税務行政に物申す(不服申立制度)
税(国税)に関する処分について不服申立制度について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。
制度の概要
税務署長,国税局長などがした処分に対し,納得がいかない場合には,その違法性や不当性を争って当該税務署や国税不服審判所長に対して不服の申立てができます。
たとえば,納税者が,確定申告により所得税の還付金請求をしたのに,反対に課税処分がなされたりした場合に,その誤りを指摘して是正を求めることができるという制度に不服申立てなどがあります。
不服申立には期限がある
上記のような不服のある納税者は,不服の対象となる処分があったことを知った日(通知文書を受けた場合はその文書を受け取った日)の翌日をスタートとして,原則として3か月以内に申立てをしなければならず(国税通則法77条1項),これを徒過すると申立ては却下されることなるので注意が必要です。
2つの手続き
不服のある納税者は,処分をした税務署長の所属税務署に対する①「再調査の請求」あるいは,国税不服審判所長に対する②「審査請求」のうち,いずれかを選択することになりますが,①の場合でも再調査の結果に納得できなければ②へと移行することが可能であるため,以下は②の国税不服審判所長に対する審査請求の概略となります。
国税不服審判所長に対する審査請求
審査請求では,標準審理期間が1年と指針で定められ,裁判所における税務訴訟一般と比し,大幅に短縮されることが想定されており,早期解決をめざす納税者の利益を重視したものとなっています。
さらに,審理の結果,出すべき裁決(却下,認容,棄却)では,審査請求人(納税者)の不利益に処分を変更することは許されず,ここでも納税者に不利益が増大しないルールが定められています(同法98条3項但書)。
また,裁判所への訴訟提起の場合,請求額に比例した手数料の納付が必要であるところ,審査請求では,手数料の負担なく制度の利用ができることもおすすめとなる点です。
気になる認容率について
このような審査請求の申立て認容率は,平成29年から令和3年までの直近5年間では,3%~10%の範囲で推移しており,現状残念ながらあまり高いとは言えません。
まとめ
納税の義務は,日本国憲法(30条)にも定められた国民の義務のひとつですが,税務行政を公正とするための制度がこの不服申立て制度となります。納税を納得の上で履行したいと思われる方は,弁護士や税理士に相談するのを検討することもおすすめです。
【国税庁発表】令和3事務年度法人税等の調査事績の概要
令和4年12月に国税庁から報道発表のあった「令和3事務年度法人税等の調査事績の概要」から国税庁の調査状況について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が考察します。
法人税との調査事績の概要
令和4年12月の報道発表では、法人税等の調査事績の概要のまとめとして
①新型コロナウイルスの影響を受けつつも、調査件数、申告漏れ所得金額、追徴税額が増加
②悪質な納税者には厳正な調査を実施する一方で、その他の納税者には簡易な接触を実施
とあります。
法人税・消費税の調査事績の概要
国税庁では、あらゆる資料情報と提出された申告書等の分析・検討を行った結果、大口・悪質な不正計算等が想定される法人など、調査必要度の高い法人について実地調査を実施しています。
実地調査の件数は、令和2事務年度が2万5000件だったのに対して、令和3事務年度では4万1000件と1.5倍以上の増加となっています。
この急激な増加については、令和2事務年度の実地調査件数は令和元年度と比べると32.7%にあたるものしか行われていないことから、令和2事務年度の件数が少なかっただけということができるでしょう。
もっとも、新型コロナの影響で実地調査が減少していた令和2事務年度と比べると、新型コロナ流行前の実地調査件数に戻ってきたということもできるため、令和4事務年度は昨年度ほどの大きな増加は見られないと思いますが、昨年度と同程度以上の実地調査が行われる可能性が高いと言えるでしょう。
実地調査の結果、申告漏れの所得金額は6028億円で、令和2事務年度の114%、追徴税額は2307億円で、令和2事務年度の119.2%となっています。
申告漏れ所得金額、追徴税額ともに令和元年度よりも増加していますが、実地調査の件数が増加しているため、当然の結果といえそうです。
それよりも重要なことは、実地調査の件数の増加率よりも、申告漏れ所得金額や追徴税額の増加率の方が低いことです。
調査1件当たりの追徴税額を見ると、令和2事務年度が780万6000円、令和3事務年度が570万1000円となっています。
つまり、令和2事務年度の方が1件当たりの申告漏れ所得額も多かったということができます。
このことは、令和2事務年度は新型コロナの影響により、より大口で悪質な案件のみに限って実地調査を行ったことも原因と考えられますが、一方、令和3事務年度では大口・悪質される案件のハードルが下がっていると考えることもできます。
そのため、今後もこれまでよりも少額や悪質性が高くないと思われる案件についても実地調査が行われる可能性を示唆しているといえます。
簡易な接触事績の概要
簡易な接触とは、税務署において書面や電話による連絡や来署依頼による面接により、納税者に対して自発的な申告内容の見直しなどを要請するものです。
単純な申告内容の誤りなど、悪質性が低いと思われる事案に対して行われるものと考えてください。
簡易な接触の件数は前年度と比べて98%とほとんど変わっていません。
実地調査は大きく増えているのに対して簡易な接触の増減が少ないことは、国税庁が大口・悪質性が高い事案に対して、積極的に取り組んでいることを示しているといえるでしょう。
これらのデータからは、新型コロナの影響が終息に向かっていくにつれて、国税庁の調査も本格化していることがわかります。
自分は大丈夫と安易に考えず、早めに専門家に相談し、取り返しがつかなくなる前に対処しましょう。
一人親方の脱税~①~
建築・土木工事に携わっている事業者の方たちには、雇用関係を持たずに事業を行う、いわゆる「一人親方」と言われる方が多くいらっしゃいます。
一人親方が脱税をしている場合になぜ脱税がばれるのか、脱税がばれるとどのようなペナルティが課されるのかについて2回にわたり弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説していきます。
今回は一人親方と個人事業主の違いとなぜ脱税がばれるのかについて解説します。
個人事業主と一人親方の違い
一人親方は、労働者を使用せずに特定の事業を行う人のことをいいます。
個人事業主は、法人を設立せずに個人で事業を営んでいる人のことをいいます。
そのため、一人親方も広い意味では、個人事業主の一種といえるでしょう。
しかし、一人親方は
①業種の範囲が限られている
個人事業主の場合には、業種の指定はありませんが、一人親方の場合には、建設業・林業・水産業など、7つの業種に限られています。
②従業員の雇用について制限がある
個人事業主の場合、従業員の雇用について制限はありません。一方、一人親方の場合には従業員の雇用日数が100日未満である必要があります。
③労災保険へ加入できる
個人事業主の場合には、原則として労災保険へ加入できませんが、一人親方の場合には特別に加入できることになっています。
といった3つの点で個人事業主とは異なっています。
もっとも、一人親方の場合でも、開業届を税務署に提出する義務があることや納税の義務があることは、個人事業主と同じです。
一人親方も開業届を提出することは義務
一人親方を含む個人事業主は、開業届を税務署に提出する義務があります(所得税法229条)。
開業届は、事業を開始した日または事業に関する事業所等を設けた日から1か月以内に税務署長に提出する必要があります(同条)。
開業届は提出していなくてもペナルティはありませんが、開業届を出すと、青色申告ができたり、事業用の銀行口座を開設出来たり、事業主を対象とした給付金を受け取れたりといった様々なメリットがあります。
また、開業届を出すと、個人事業主番号が付与されますが、この個人事業主番号はビジネスローンを組んだり銀行の融資を受けたりする際にも必要となるので、開業届を出しておくことにより、公的に事業主として認められることのメリットは大きいと言えるでしょう。
一人親方の脱税はなぜばれるのか
①取引先からの源泉徴収税の申告
源泉徴収税とは、一人親方が支払うべき税金を前もって取引先が徴収し納税するものです。
源泉徴収税の納付にあたっては、どの一人親方に関するものであるかも明示されるため、税務署や国税局には一人親方に売り上げがあることがわかってしまいます。
②反面調査
反面調査とは、税務署が調査対象者の取引先を調べ、取引の実態を把握するための調査です。
取引先や銀行に調査が行われることで、一人親方としての売り上げがあることが発覚してしまう可能性があります。
③資産状況の調査
不動産購入など高額なお金の動きがあれば、法務局から税務署に情報が伝わることがあります。
申告されている収入に比して高額な不動産の購入などがあれば、税務署に脱税の疑いをもたれてしまい、税務調査が入るきっかけになります。
④第三者からの密告
税務署は課税・徴収漏れに関する情報提供を呼び掛けています。
国税庁が公開している「課税・徴収漏れに関する情報の提供」によれば、様々な情報が寄せられていることがわかります。
国税庁のホームページには「情報提供フォーム」が用意されており、だれでも情報を提供できることになっています。
このように、税務署や国税庁は税金逃れがないように、様々な方法で情報収集をしています。
お金の怪しい動きや提出された資料に不審な点があれば、税務調査が入ることになり、脱税が明るみに出てしまうことになります。
そして、一人親方は国税庁が発表している申告漏れ所得金額が高額な業種上位10業種のうち約半数を占めていることから、税金逃れがないかを特に注意深く調査される対象になっているといえます。
そのため、一人親方は脱税していないか税務署から常に目をつけられているといえます。
~次回に続く
脱税と時効~②~
脱税をしてしまった場合の時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が前回に続いて解説します。
第2回目は、刑事事件化してしまった場合の時効について解説します。
刑事事件の時効(公訴時効)
いままで見てきた時効や除斥期間はあくまでも納税に関する時効でした。
しかし、脱税で査察調査が入り、刑事告発された場合には、刑事事件になってしまいます。
刑事事件になってしまった場合には、これまで見てきた時効とは別の時効(公訴時効)が定められています。
公訴時効とは、犯罪が終わった時から一定の期間を経過すると、犯人を処罰することができなくなるという制度です。
たとえば、脱税事件の中でもっとも重い刑罰が定められている「ほ脱犯」(偽りその他不正の行為により、税金の納付を免れ又は還付を受けた場合)では、「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれの併科」という罰則が定められています(例:所得税法238条1項、法人税法159条1項、消費税法64条1項、相続税法68条1項)。
この「ほ脱犯」の公訴時効は、「人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪」のうち「長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪」に当たるため、公訴時効は「7年」ということになります(刑事訴訟法250条2項4号)。
また、公訴時効の起算点は、「犯罪行為が終わった時」となっています(刑事訴訟法252条)。
つまり、偽りその他不正の行為によって税金の納付を免れたり還付を受けたりした時から7年を経過する時までに公訴提起(起訴)がされなかった場合には、罪に問うことができなくなるということです。
各税法上、上記のほ脱犯以外にも、偽りその他の不正の行為により税金の納付を免れたとは言えないものの、法定の期限までに申告書を提出しないことにより税金の納付を免れた場合には「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれの併科」という罰則が定められており(例:所得税法238条3項、法人税法159条3項、消費税法64条5項、相続税法68条3項)、この場合は「人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪」のうち「長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪」に当たるため、公訴時効は「5年」となります(刑事訴訟法250条2項5号)。
その他、「長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪」の場合には、公訴時効は「3年」となります。
公訴時効の停止
公訴時効を考えるにあたって注意しないといけないのは、「海外にいる間は公訴時効が進行しない」ということです。
「犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。」(刑事訴訟法255条1項)とされており、海外にいる期間を除いて公訴時効期間を経過する必要があります。
例えば金密輸事件の場合には、何度も海外に渡航して金を購入し、購入した金を密輸して消費税を免れたうえ、金を本邦で売却することにより消費税分の利益を得ることになりますが、この場合には、消費税及び所得税のほ脱犯として処罰を受ける可能性があります。
この場合、海外に渡航して金を購入する際には国外にいることになりますので、公訴時効の期間にはその期間が含まれないことになります。
そのため、公訴時効が完成しているか否かを判断するにあたっては、海外にどれくらいの期間いたのかを正確に把握しておく必要があります。
まとめ
このように、脱税の場合には、課税に関する時効や除斥期間だけでなく刑事事件化した場合には別途公訴時効も考えなければなりません。
また、時効や除斥期間は比較的長い期間が設定されていますし、徴収権などの時効には中断事由が定められており、容易に時効完成を狙うことはできないようになっています。
長期間にわたって脱税をしてしまった。悪意はなかったが申告を忘れてしまっていたというような場合には、どの部分について課税や罪に問われることになるのかを専門家に相談してみるのがいいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を見据えた一貫したアドバイスを差し上げることができますので、一度お電話ください。
脱税と時効~①~
脱税をしてしまった場合の時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が2回にわたって解説します。
第1回目は時効と除斥期間の違いや、賦課権の除斥期間、徴収権や還付請求権の時効について解説します。
時効と除斥期間
除斥期間:一定の権利について、法律で定められた期間内にその権利を行使しないと、権利が当然に消滅する場合の期間です。
時効:権利が一定期間行使されない時に、その権利を消滅させる制度です。
除斥期間と時効との違いは、主に以下の2つです。
①除斥期間には中断(完成猶予・更新)がないのに対して、時効には中断事由がある
②除斥期間は期間経過によって絶対的に権利が消滅するため当事者の援用を要しないが、時効は当事者の援用が必要
賦課権の除斥期間
賦課権とは、税務署長が納税義務の確定手続を行うことができる権利です。
賦課権の行使については、時効ではなく除斥期間が設けられています。
納税義務はあっても、未確定のまま賦課権の除斥期間を経過してしまった場合は、賦課権の行使による納税義務の確定はできないことになります。
①除斥期間の起算日
・申告納税方式の場合
法定納期限の翌日(ただし、還付請求申告書が提出されたものについては、その提出日の翌日)
・賦課課税方式の場合
ア 課税標準申告書の提出を要する国税の場合
提出期限の翌日
イ 課税標準申告書の提出を要しない場合
納付義務の成立した日の翌日
②除斥期間の長さ
・3年の除斥期間
課税標準申告書の提出を要する国税で申告書の提出があったもの(納付すべき税額を減少させるものを除く)(国税通則法70条1項)
・5年の除斥期間
更正、決定及び賦課決定(3年の除斥期間に該当するものを除く)(国税通則法70条1項)
・7年の除斥期間
偽りその他不正の行為により、税額の全部若しくは一部を免れ若しくは還付を受けた国税についての更正決定等又は偽りその他不正の行為により、その課税期間において生じた純損失等の金額が過大である納税申告書を提出していた場合における純損失等の金額についての更正(10年の除斥期間にあたるものを除く)(国税通則法70条5項)
・10年の除斥期間
法人税にかかる純損失等の金額で当該課税期間において生じたものを増加させ、若しくは減少させる更正又は当該金額があるものとする更正(国税通則法70条2項)
徴収権の消滅時効
徴収権とは、すでに確定して国税債権の履行を求め、収納することができる権利です。
私法上の債権に極めて似た性格を持つことから、国税の優先権(国税徴収法8条)と自力執行権(国税徴収法47条など)が認められている点を除いて、私債権と同様に扱うものとされており、時効制度がとられています。
もっとも、徴収権の時効には、民法上の時効とは違い、①当事者は時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができなかったり(消滅時効の絶対的効力)、②民法の中断事由のほかに特別の中断事由(完成猶予・更新)があります。
①消滅時効の起算日
国税の徴収権の消滅時効は5年です(国税通則法72条1項)。
この5年の起算日は、原則としてその国税の法定納期限の翌日となっています(同条)。
②時効の中断(完成猶予・更新)
民法では、時効の中断事由(完成猶予・更新)として①請求等、②差押え(強制執行等)仮差押え又は仮処分、③催告、④承認などを定めています。
国税の徴収権の消滅時効には、民法上の中断事由のほか、①納税申告、納税の猶予の申請又は換価の猶予の申請、延納の申請及び一部の納付、②税務署長によってなされる更正、決定、賦課決定、納税の告知、督促、交付要求についても中断事由(完成猶予・更新)として定められています(国税通則法73条1項)。
③消滅時効の停止
時効の停止とは、時効の完成を一定期間延長するものであり、中断とは異なり、停止の時までに進行した時効期間の効果は失われません。
国税の徴収権の時効は、延納、納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予をした国税について、その延納又は猶予がされている期間内は、停止します(国税通則法43条4項)。
還付金等の還付請求権の消滅時効
還付請求権とは、納税者が還付を求めるために申告などをして、納め過ぎた税金を返してもらう権利です。
還付請求権についても徴収権と同様に時効制度が採用されています。
①消滅時効の起算日
還付請求権の消滅時効は5年です(国税通則法74条1項)。
この5年の起算日は、その還付を請求することができる日(過誤納金の発生した時の翌日及び還付金の還付請求の日又は還付請求ができる日)です(同条)。
②時効の中断(完成猶予・更新)
納税者が行う還付を受けるための納税申告書、還付請求書の提出は、民法上の「催告」としての効力があり、また、税務署長から支払通知書などが還付請求者に送達されたときに、国の「承認」として時効が中断します。
また、徴収権の消滅時効にかかる中断に関する規定が準用されています(国税通則法74条2項)。
~次回に続く~
Newer Entries »