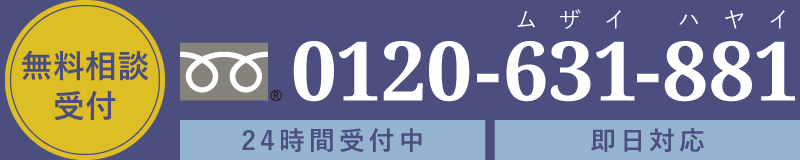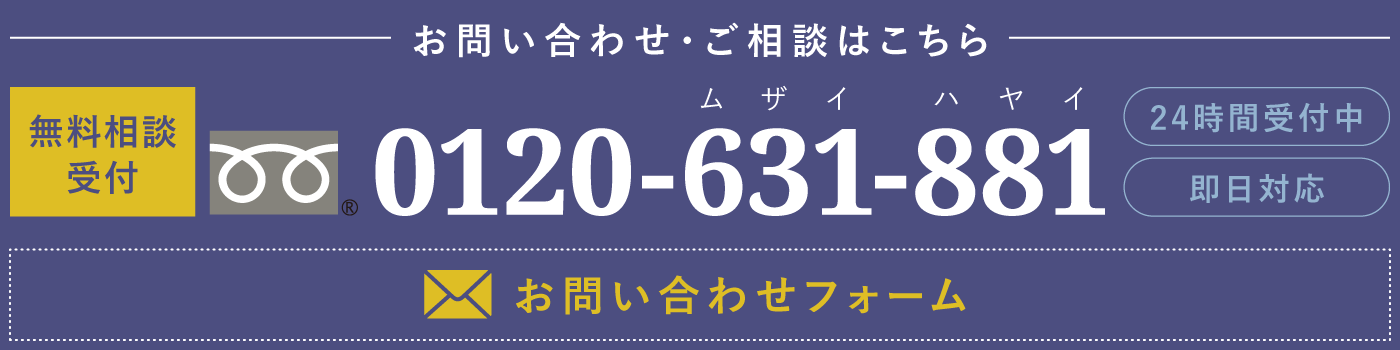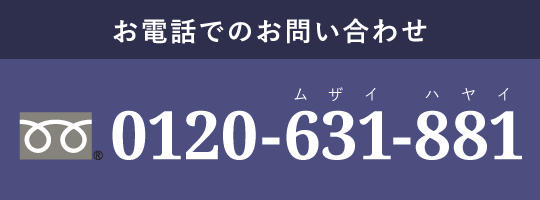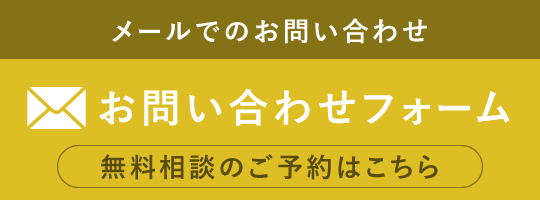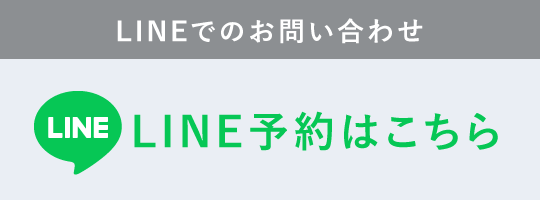Archive for the ‘所得税・法人税’ Category
NISAでも確定申告が必要?
NISA(少額投資非課税制度)で得た利益について、確定申告が必要になる場合があることをご存じでしょうか?弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
NISAとは
NISA(少額投資非課税制度)は、「NISA口座(非課税口座)」内で、毎年一定金額の範囲内で購入した株式や投資信託などの金融商品から得られる利益が非課税になる制度です。
通常であれば、株式や投資信託といった金融商品に投資をした場合、これらを売却して得た利益や受け取った配当に対して約20%(消費税15.315%(復興特別所得税を含む)、地方税5%)の税金がかかります。
NISA口座内での取引は、年間非課税枠内で購入したものに対する利益について、所得税や住民税といった税金が課税されない、つまり、税金を払う必要がないということになっています。
そのため、NISAで利益を得たとしても、通常は確定申告は必要ないということになります。
NISAの種類
NISAには現在①一般NISA、②つみたてNISA、③ジュニアNISAの3種類があります。
①一般NISAは、株式・投資信託等を年間120万円まで購入でき、最大5年間非課税で保有できます。
②つみたてNISAは、①一般NISAと違い、購入方法や購入可能商品が限られていますが、一定の投資信託を年間40万円まで購入でき、最大20年間非課税で保有できます。
③ジュニアNISAは、20歳未満を対象とした制度で、株式・投資信託等を年間80万円まで購入でき、最大5年間非課税で保有できます。
※なお、2024年以降は、現行のNISA制度が見直され、年間投資枠が大きくなったり、非課税保有期間が無期限となったりといった現行制度の拡充・恒久化が図られた新しいNISA制度が始まることになっています。
NISAで確定申告が必要な場合
NISAは少額投資に関して非課税にする制度ですので、原則として確定申告は必要ありません。
しかし、以下の3つのパターンの場合には、確定申告が必要になるので、注意が必要です。
①NISA口座から他の口座に資産を移した場合
非課税期間が終了した場合、翌年の非課税投資枠に移管するか、課税口座に移管するか、売却するかを選択できます。
NISA口座からそれ以外の課税口座へ移管した場合には、移管後に出た利益については課税対象となります。
ここで注意が必要なのは、移管時点の価格が取得価格とされる点です。
NISA口座で購入した価格と課税口座へ移管した時点での価格が値上がりしていればそこまで問題はありませんが、逆に値下がりしていた場合、移管時の値下がりした価格が取得価格となるため、その後に値上がりした場合には、多くの税金を支払う必要があります。
②ジュニアNISAで得た利益を18歳未満で払い出した場合
ジュニアNISAには払い出し年齢に制限を設けてます。
18歳未満で払い出しをする場合、購入時にさかのぼって課税対象とされるため注意が必要です。
なお、2024年以降についてはこの制限が廃止されます。
③配当金の受け取りを証券会社を通じて受け取る方法(株式数比例配分方式)以外の方法で行う場合
国内上場株式の配当金、ETF(上場投資信託)・REIT(不動産投資信託)の分配金は、証券会社を通じて受け取る場合(株式数比例配分方式を選択している場合)のみ非課税となります。
配当金などの受け取り方法は、ゆうちょ銀行から受け取る方法、指定の銀行口座から受け取る方法、証券会社を通じて受け取る方法から選択できますが、証券会社を通じて受け取る方法以外を選択した場合には、非課税とはならず税金が源泉徴収されます。この場合、確定申告をすることで控除や損益通算をすることが可能です。
脱税と言われないためにもしっかりとルールの確認を
NISAは非課税という大きなメリットがある一方、ルールを知らないと思わぬところで落とし穴があり、デメリットもあります。
2024年以降はこういったデメリットが緩和されることが期待されていますが、それでもルールをしっかりと確認しておくことが必要です。
NISAを利用していたのに、税務署から調査が入ったなど不安がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に一度ご相談ください。
投げ銭は贈与?税金は?
投げ銭(スーパーチャット)は贈与でしょうか?税金はかかるのでしょうか?その疑問に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所がお答えします。
投げ銭(スーパーチャット)とは
投げ銭という言葉は、もともと路上パフォーマーなどのパフォーマンスに対して、観客がパフォーマー側が準備した集金箱などに金銭を投げ入れる行為のことを指していました。
映画などで大道芸人が演技が終わった後にシルクハットなどを観客に差し出してそこに観客からお金を入れてもらう場面を見たことがあるのではないでしょうか?
しかし、インターネットが普及した現在においては、「投げ銭」の意味も変化しています。
今回取り上げる「投げ銭」とは、インターネットでの配信などに対して、視聴者やファンなどがオンラインで送金する行為を言います。
YouTubeではスーパーチャット(スパチャ)と言われていますが、これも代表的な「投げ銭」と言えるでしょう。
「投げ銭」のシステムは、オンライン上で金銭を送金する以外にも、有料ギフトを購入し送るなどの方法もあり様々ですが、いずれも配信者を金銭面で支援しているという面で共通しています。
投げ銭は贈与か?
投げ銭は贈与でしょうか?
贈与とは、無償で金銭等を譲渡する(譲り受ける)行為をいいます。
そのため、インターネット配信をしている人が何もパフォーマンスなどをしていないのに、投げ銭をされた場合には贈与に当たるといえるかもしれません。
しかし、ほとんどの場合、なにがしかのパフォーマンスを配信し、そのパフォーマンスに対して投げ銭が行われています。
そうすると、対価性が認められることになり、もはや「贈与」ということはできなくなります。
この場合、投げ銭で得た利益は「所得」として申告する必要があります。
贈与か所得かは納税の段階で非常に大きな違いが出てきます。
「贈与」の場合、贈与税の申告が必要となりますが、1年間に得た贈与の額が110万円を超えていなければ申告する必要がありません。
一方「所得」の場合には、基本的に20万円を超えている場合には確定申告が必要となります。
投げ銭の所得は何所得か?
投げ銭が「所得」になるとして、その所得の種類が問題となります。
すなわち「事業所得」か「雑所得」かです。
この点、基本的には「事業所得」となると考えられます。
たとえば、YouTuberの方などは動画配信を仕事として行っており、その動画配信を通じて「投げ銭」を得ていることになるので、仕事=事業によって得た収入と考えられます。
つまり、なにがしかの事業若しくは反復継続性のある行為によって得た利益は「事業所得」となると考えられます。
一方、一般の方が趣味でアップした動画などについては、「雑所得」となる可能性の方が高いと言えます。
反復継続性がなかったり、その行為によって利益を得ることを目的としているとはいえないからです。
投げ銭の確定申告
事業所得に当たる場合、総収入から経費や控除額を引いたものが課税対象の金額となります。
ここで、青色申告か白色申告かによって、控除額が異なります。
たとえば、個人事業主で開業届を提出し青色申告承認申請をしている場合、青色申告をすることができます。
青色申告では最高55万円(令和元年以前は65万円)を控除することができます。
投げ銭は履歴が残るため、税務調査が入ると申告漏れが発覚しやすいといえます。
投げ銭が贈与になるのか事業所得になるのかわからない、所得になるのに贈与として申告していて心配という方は専門家に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では無料の法律相談を実施していますので、税務調査・査察調査が入ったという方は一度お問い合わせください。
宗教法人には課税されないのか?
宗教法人には課税されないのかについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
宗教法人に対して追徴課税
令和5年1月31日の報道で、和歌山県内で寺を運営する二つの宗教法人が2021年、大阪国税局の税務調査を受け、各法人の代表を務める住職2人が檀家からのお布施計約1億5000万円を私的に流用していたとして、所得税の源泉徴収漏れを指摘し、2法人に対して重加算税を含む計約7000万円を追徴課税したというニュースがありました。(令和5年1月31日付読売新聞オンライン)
この事件では、住職2名は7年間で、読経などで得たお布施を自分名義の口座に入れ、個人的に使ったり、預金していたりして私的に流用していたことが、源泉徴収の対象となる「給与」と認定されたということです。
宗教法人は課税されないのでは?
宗教法人は課税されないと思っている人は多いと思います。
しかし、実際には宗教法人に対しても課税はされます。
なぜこのような勘違いが起きてしまうのかというと、「宗教活動」には課税されないからです。
宗教法人は、「宗教活動」を行う団体ということができますが、宗教活動以外にも様々な活動をしています。
そのため、宗教法人が行う活動のうち、宗教活動以外で収益事業を言えるものには法人税などが課税されます。
宗教法人に法人税が課せられる場合
宗教法人の収益事業には法人税が課されます。
宗教法人の収益事業としては、物品販売業や不動産の貸付業など34種類の事業があります。
もっとも収益事業に該当するかどうかについての線引きは微妙な部分もあります。
例えば、お守りやおみくじなどの販売については、物品販売業に該当しそうですが、その売価と仕入原価との関係からみてその差額が通常の物品販売業における売買利潤ではなく、実質的な喜捨金と認められるような場合には、収益事業には該当しないことになっています。
一方、一般の物品販売業者においても販売されているような性質の物品(例えば、絵葉書、写真帳、暦、線香、ろうそくなど)を通常の販売価格で販売する場合には、その物品の販売は収益事業に該当します。
このように、法人税が課税されるか否かについては、その線引きが難しいものもありますので、収益事業に該当するかについて、税理士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
住職の給料
お寺の住職さんに対して宗教法人から給料が支払われている場合があります。
この給料については、源泉徴収の対象となっています。
そのため、宗教法人は源泉徴収義務者として、住職さんに支払う給料から源泉徴収し、国に源泉徴収税を納付する義務を負っています。
上記報道で、住職が私的に流用した金銭を「給与」と認定されたことによって、源泉徴収義務を果たしていないことになり、追徴課税を受けたということになります。
また、今回の事件では、重加算税が課されていますが、これは、私的流用が仮装・隠ぺいを伴う悪質性の高い不正行為であると認定を受けたことによるもので、通常の加算税よりもより重いペナルティといえます。
まとめ
お布施は現金で受け取るため、資料が残っていないことが多いですが、国税庁が実施した調査では、約7割で源泉徴収漏れがあったということです。
税務調査が入った場合には、徴収漏れが発覚する可能性が高いといえますので、早めに専門家にご相談ください。
早めに修正申告などをすることで、重加算税などの重いペナルティを避けられる可能性が上がります。
損害賠償金に税金はかかるのか?
損害賠償金に対して課税はされるのかについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
損害賠償金
不法行為などによって損害を被った場合、損害を被った側は損害を与えた側に対して損害賠償を請求することができます。
損害賠償は通常の場合、金銭で支払われることになりますが、損害賠償金を受け取った場合、所得として課税対象となるのでしょうか。
今回は、犯罪によって損害を被った場合における損害賠償金に課税されるかについて、事例をもとに解説していきます。
事例1~過失運転致傷の場合~
Aさんは自動車を運転中によそ見をしてしまい、東京都千代田区の横断歩道を青信号に従って歩行中のVさんをはねて怪我をさせてしまいました。
Aさんは、Vさんが怪我の治療により支払った治療費や休業損害、慰謝料などを含め200万円をVさんに支払うことで、Vさんから許してもらいました。
この場合、Vさんは、200万円の利得を得たことになりますが、「心身に加えられた損害に対する損害賠償金」については、「非課税所得」となるため(所得税法9条1項18号)、所得税の課税対象とはなりません。
事例2~業務上横領の場合~
Bさんは、愛知県名古屋市にある会社の経理を任されていましたが、会社の売上金から合計1000万円を横領していました。
会社から問い詰められたAさんは、横領の事実を認め、会社に対して1000万円の損害賠償金を支払うことで示談しました。
この場合、会社には実際に1000万円の損失があり、1000万円の損害賠償金はその損失を回復しただけということになるので、課税されないことになります。
事例3~窃盗の場合~
Cさんは、大阪府堺市にある店の倉庫に忍び込み、商品を盗んで売り払っていましたが、あるとき忍び込んだところを店員に見つかり、警察に逮捕され、逮捕された後の捜査で、Cさんが盗んだ商品の総額が300万円になることが判明しました。
店は今回の事件を受けて防犯のために防犯カメラの設置などを行ったため、その費用も含めてCさんに請求しようと考え、盗まれた商品が売れたとしたならば得られたであろう利益と防犯カメラの設置代などを合わせて500万円をCさんに請求し、支払ってもらいました。
この場合も、店としては商品の損害を受けているため、それを補填してもらっているのであるから、非課税となりそうです。
しかし、事業用の資産に対しての損害賠償金の場合には注意が必要です。
社会通念上ふさわしいとされる範囲での見舞金の金額に相当する部分については非課税とされますが、商品を売った場合に得られる売却益を損害賠償金として受け取った場合、収入金額に代わる性質をもつものとして課税対象となります。
また、防犯カメラの設置代などについては、本来であれば会社の経費として算入される金額を補填するためのものと言えるため、非課税とはならず、事業所得の収入金額となる可能性が高いです。
そのため、今回の事例では、社会的に相当と言える範囲を超えた部分や事業収入の代わりに支払われたと考えられる部分については、課税されることになります。
まとめ
損害賠償金として受け取った金銭については、基本的には非課税所得となりますが、場合によっては課税対象となる場合があります。
そのため、損害賠償金として受け取ったとしても、確定申告が必要となる場合があり、税理士や弁護士に確認しておく必要があります。
【事件解説】インフルエンサーに追徴課税
インフルエンサー9人に対して東京国税局が追徴課税をした実際の事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。
事件の概要
「インフルエンサー」の女性9人が東京国税局の税務調査を受け、2021年までの6年間に合計約3億円の申告漏れを指摘された。
東京国税局から,税務調査を受けたのは,インスタグラムやYou Tubeなどでいわゆる「インフルエンサー」と呼ばれる活動をする女性ら9名で,同女性らは,広告主から商品やサービスの宣伝業務を受注すると,広告主の商品である化粧品や美顔器などについて,実際にこれらを使用している写真などをSNS上に投稿するとともに,販売を促進する旨の分かりやすいコメントを載せることにより,同女らのフォロワーらに購入意欲を促進させるなどして売上げにつなげることで,広告主から,そのフォロワー数に応じた報酬を受け取り,多額の利益を上げていた。
同インフルエンサーらは,報酬の全部または一部を確定申告していなかったり,うち1名については,SNSを通じて販売したいわゆる情報商材の売上収入を,海外のペーパーカンパニーの収入と装って所得を隠すなどしていた。
(令和5年3月8日読売新聞オンラインの記事より抜粋)
税務調査
課税庁が,納税者の申告内容に疑問を感じた時に,事後の追徴課税の要否を判断するためなされるのが税務調査です。個人で対象となるのは,個人事業主,フリーランス,ITプログラマー,新規ビジネスモデルのアントレプレナーなど多種多様に及びます。これは憲法に規定された国民の納税義務に基づく課税行政の適正実現のために,所得の生じる事業に対し,過去5年(悪質ケースでは7年)まで遡って(国税通則法72条,73条),事業に関する帳簿書類その他の物件の提示若しくは提出を求め,事業者に対し,事業の収支関係等に関し質問することができるとするものです(同法74条の2)。
このような税務調査がなされれば,税務のプロによる調査からもはや逃れることはできないでしょう。
今回は,人気女性インフルエンサー9名に対し,東京国税局が税務調査をした結果,2021年までの6年間に計約3億円の所得申告漏れが判明しました。
インフルエンサーは狙われている
SNS上のインフルエンサーによる広告は,拡大を続けており,市場調査会社であるSNSマーケティング会社によると,2021年は前年の2倍以上のおよそ741億円の市場規模であり,予測によると,これが2027年には1302億円に上ると推計されています。
インフルエンサーはほとんどが個人で行ってることから、個人事業主ということになります。
企業とタイアップしたりスポンサード契約を結んだりしている場合もありますが、その場合でも個人事業主として扱われる場合がほとんどです。
今回の事件のように、広告によって得た収入は事業所得となり、所得税の確定申告が必要になります。
インフルエンサーの市場規模が年々拡大を続けている現状から、インフルエンサーは、国税局や税務署が特に注目している事業分野だといえます。
特にYouTubeやInstagramなどでは、フォロワー数が表示され、どれくらいの広告収入を得ているかが推測されやすく、税務調査に入りやすいといえるでしょう。
追徴課税
今回の事件では、インフルエンサー9人に対して、百数十万から約3000万円が追徴課税され、追徴税額は合計約8500万円に上るということです。
追徴課税とは、本来納めるべきであった税(本税)に加えて、無申告や過少申告に対するペナルティとしての加算税を加えたものです。
今回の事件では、報酬の一部を申告していなかった人には、過少申告加算税が、報酬の全部を申告していなかった人には無申告加算税が追加で徴収されていることになります。
また、今回の事件のうち1名のインフルエンサーは海外のペーパーカンパニーの収入と偽っていたとのことですが、これは悪質性の高い隠匿行為と評価される可能性があります。
悪質性が高い隠匿行為とされると、無申告加算税や過少申告加算税よりも加算される税額が重くなる重加算税が課せられる可能性もあります。
本来納めるべき税額に加えて、加算税が課せられますので、きちんと確定申告をして納税していれば課せられなかった多額の税金を追加で納めなければならなくなってしまいます。
税務署の税務調査より前に修正申告を行うことによって、こういった加算税を課せられることを防ぐことができますので、申告漏れに気づいた場合には、早めに専門家に相談して対処しましょう。
まとめ
今回の事件ではインフルエンサーに対する追徴課税がなされたという報道でしたが、うち1名については、悪質性の高い隠匿行為をしているとして重加算税の対象になる可能性があるだけでなく、刑事告発を受けて刑事罰を科せられる可能性もあります。
インフルエンサーはその社会的影響力から、税務署も目を光らせていますので、確定申告の内容に不安があったり、申告漏れが疑われてしまった場合には、早急に税理士や弁護士などの専門家に相談しましょう。
本記事を解説してくれた河田弁護士は「国民主権の下,国の存立を図るためには,国民一人一人が,その能力に応じて納税義務を履行し,国の財政を支えなければならないの当然となります。天網恢恢疎にして漏らさずのとおり,不正な申告や所得隠しはいずれ発覚することになりましょう。そうなれば,本来の税額に加えペナルティとして加算税の追徴を受けるなど金銭的に少なからずの損失を被ることになります。誰しも納税には負担を感じるものです。しかし,納税することが国の存立に寄与すると思えば,気持ちも変わるはずです。くれぐれも適正申告に務めたいものです。」と語っています。
【事件解説】所得税不正還付指南で刑事告発
所得税の還付を不正に受ける方法を指南したとして刑事告発された実際の事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。
事件の概要
「納めすぎた税金を取り戻そう」と全国の会社員にSNSで呼びかけ、不正な還付申告による脱税の手口を指南していたとして、東京国税局査察部が、東京都新宿区のコンサルタント会社の代表者Aを所得税法違反の疑いで東京地検に告発した。
Aは、東京や埼玉、愛知、岐阜、大阪、兵庫、福岡、熊本など19都府県の会社員ら109人に、架空の副業で計約7億2900万円の損失を出したように装わせ、計約4300万円分の所得税の還付を不正に申告させた疑いが持たれている。
(令和5年3月1日、朝日新聞DIGITALの記事から抜粋)
所得税の還付
会社員の方などは、給与から所得税が源泉徴収されています。
この源泉徴収をされた所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納めすぎた所得税の返還を受けることができます。このことを所得税の還付といい、還付を受けるための申告を還付申告と言います。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
会社員の方の場合には、給与から所得税が源泉徴収されているため、基本的には所得税の確定申告をする必要はありません。
しかし、副業をしている方で、その副業で損失を出してしまった場合には、その損失部分を所得から差し引くことができるため、損失部分を含めて確定申告をすることで、納めすぎた所得税の還付を受けることができるのです。
刑事手続
Aさんは、所得税法違反で刑事告発を受けています。
刑事告発を受けた検察庁は、Aさんを被疑者として取り調べ、その後起訴することになります。
査察部から刑事告発をする場合には、事前に査察部と検察庁で協議を行い、告発をするかどうかを決定することがほとんどです。
そのため、刑事告発されると7割を超える確率で起訴まで至っています。
起訴されると、公開の法廷で裁判が開かれます。
今回のAさんの場合、架空の副業で損失が出たように装って還付申告をすることを指南していたということなので、「偽りの方法により所得税の還付を受けた」ということになり、所得税法238条1項の罪に該当すると思われます。
同条で規定されている法定刑は、「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれの併科」です。罰金については、情状によって、還付を受けた所得税の額に相当する金額以下まで科すことができます(同条2項)。
Aさんの場合には、脱税を指南していたという立場になるため、実際に不正に還付申告をした人たちとの共犯関係にあるということになりますが、申告書作成の手数料を受領したりもしていたようなので、共謀共同正犯として処罰されることになるでしょう。
実際に不正に還付を受けた会社員の方たちは、国税局から所得隠しを指摘されて、大半が重加算税を含む追徴課税を受け、修正申告と納税に応じているということですので、Aさんに対する判決については、執行猶予が付く可能性が十分にあると考えられます。
しかし、かなり多数の人に対して脱税を指南していたこと、受け取っていた手数料の総額が高額なことなど悪質性が高い事案であるともいえます。
そのため、執行猶予が付かず、実刑判決を受けてしまう可能性もあります。
また、罰金の併科も受けることになると考えられ、不正に還付を受けた金額が約4300万円ということからすれば、1000万円近くの罰金も併科される可能性が高いです。
まとめ
今回は、実際報道されている事件をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の末吉弁護士に解説をしてもらいました。
末吉弁護士は、「所得税の不正還付については、国庫に対する詐欺のようなものなので、国税局も本腰を入れて調査しますし、告発もされやすい部類に当たるといえます。そのため、もし不正還付に加担してしまったという場合には、早急に弁護士に相談して告発をさけるための活動をしていくべきでしょう」と語ってくれました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、脱税に関する相談を無料で承っていますので、早急にお問い合わせください。
取締役の横領が発覚した場合の税務上の問題~②~
取締役が横領をしていた場合の税務上の問題について、前回に引き続き弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
税務上の問題2~横領金と役員給与~
会社代表者が横領をした場合、横領金は役員賞与になるという考え方が一般的です。
あらかじめ金額を定めていたり、定期で支払われるものなど以外の場合には、役員賞与として会社の損金には該当しないとされています。
したがって、具体例②のBさんの場合には、代表者が横領しているため、横領金はそもそも損金に算入されず、法人税の減額はされません。
また、役員賞与は源泉徴収の対象となっているため、会社には所得税の源泉徴収義務まで課されていることになり、会社は2重に税金を取られてしまうことになります。
そのため、具体例②の場合であれば、Y社には過少申告加算税だけでなく、源泉徴収所得税の不納付加算税まで課せられる可能性があります。
では、具体例①の場合はどうでしょうか。
具体例①の場合、Aさんは代表者ではなく、経理を担当している取締役です。
しかし、経理担当取締役など一定の権限がある場合にも、役員賞与と認定された事例があります。
そのため、Aさんに対する役員賞与と税務署から指摘された場合には、Aさんに対して会社が賞与として支払ったものではないということを、実際の取締役の権限等に照らして主張立証する必要があります。
また、役員賞与ではなく役員に対する貸付であったという処理をすることも有効です。
貸付であれば、源泉徴収の対象とはならないため、2重に課税されることを避けることができます。
もっとも、そのような処理ができるか否かについては、実際の事案に即して検討する必要があるため、専門家にアドバイスをもらいましょう。
税務上の問題3~加算税~
具体例①も②も過少申告にあたるため、税務署の税務調査など調査が入った後であれば、X社やY社に対して過少申告加算税が課せられることになります。
また、役員賞与となる場合には、上述のように源泉徴収義務を果たしていないことになるので、不納付加算税も課せられることになります。
そして、具体例②の場合には、代表者が売り上げ除外をしているため、隠ぺいや仮装による脱税行為として、重加算税が課せられる可能性もあります。
具体例①の場合には、経理担当取締役が行っているため、会社ぐるみで行っていたと考えられてしまうと重加算税が課せられてしまう場合もあるため、会社の行為とは同一視できないなどの主張立証を行う必要があります。
もっとも、税務署などからの調査を受ける前であれば、修正申告をして正しい税金を納めることにより、加算税を課せられることを避けることができます。
会社内部での横領などが発覚した場合には、できるだけ早く専門家に相談し、調査が入る前に修正申告をしていくことが非常に重要です。
まとめ
会社代表者が横領をした場合には、その横領額については役員賞与として損金計上できず、過少申告加算税が課せられる可能性があるほか、源泉徴収を行っていないとして不納付加算税も課せられることがあります。
また、会社代表者ではないとしても、その人の立場によっては、同様の加算税が課せられる可能性もあります。
そのため、不正が発覚した場合にはできるだけ早く修正申告をして、本来納めるべきであった税金を納めていくことにより、加算税を課せられないようにしていく対策が必要となります。
不正が発覚した場合には、税理士や弁護士など専門家に早急に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回相談は無料です。
取締役の横領が発覚した場合の税務上の問題~①~
取締役が横領をしていた場合の税務上の問題について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が2回にわたり解説します。
取締役の横領
取締役が会社のお金を横領した場合には、その取締役には業務上横領罪が成立します。
業務上横領罪は10年以下の懲役刑が定められており、警察に告訴することで、取締役に刑事処罰を受けさせることができます。
また、横領されたお金は当然会社にとって損害となるため、取締役に対して損害賠償を請求することができます。
さらに、取締役の横領により会社の資金繰りが悪くなったり、株式が下落するなどの損害が生じた場合には、当該取締役に対する責任を追及するだけでなく、株主から代表取締役やその他の取締役などに対して監督をする義務を行ったとして、任務懈怠責任を追及されることもあります。
このように、取締役が横領をした場合には、さまざまな責任を問うことができます。
では、税務上はどのような問題が生じるでしょうか。
具体例を参考に検討していきましょう。
具体例
具体例①
大阪市北区に本店を置く株式会社Xで経理を担当していた取締役のAさんは、X社から貸与されていた会社のクレジットカードを私的な飲食や息子に対するおもちゃなどの私的な目的のために使用していました。
しかし、Aさんは、私的に使用した部分について「接待交際費」などの名目で経費として計上し、X社の確定申告を行っていました。
具体例②
兵庫県西宮市に本店を置く株式会社Yの代表取締役Bさんは、Y社の売り上げの一部をBさん名義の個人口座に移し、私的に利用するとともに、個人口座に移した金額については売り上げから除外して確定申告を行っていました。
税務上の問題1~損金として計上できるか~
具体例①について
Aさんが会社から貸与されていたクレジットカードを私的に使用していたことは、Aさんが取締役であることから特別背任にあたる可能性が高いといえます。
そして、私的に使用しているにも関わらず、支払った金額について「接待交際費」と偽りの名目で経費計上していることから、実際には経費計上できないものを経費計上していたということになり、X社は過少申告をしていたということになります。
ここで、会社は損失を実際に被っているのであるから、損金として計上できるのではないか、過少申告とはいえないのではないかということが問題となります。
しかし、Aさんの不法行為によりX社は損害を被っていることになるため、X社はAさんに対して損害賠償請求権を取得しているといえます。
そうすると、損害賠償請求権はX社にとって利益となり、損失と利益を同時に計上するのが原則となっているため(最判昭和43年10月17日)、損金のみを計上することはできないことになり、過少申告となることは変わらなくなってしまいます。
もっとも、Aさんに対する損害賠償請求をしたとしても、Aさんに資力がない場合には、X社は賠償を受けられないことになってしまいます。
そうすると、X社としては、Aさんから賠償を受けられないのに、損金として計上できず、損しか残らないということになります。
そこで、最近では、相手方の資力等を考慮して、損害賠償請求権の実現性が客観的に疑わしい場合には、損失の発生のみを計上すればよいという考え方が有力となっています。
この考え方によれば、Aさんに資力がない場合には、Aさんから実際に返還された金額や返還を約束された金額を利益として計上し、それ以外の部分については、損金として計上できることになります。
Aさんの資力がどれくらいあるかや損金と益金の関係などの調査やアドバイスを受けるためにも、X社としては、早急に税理士や弁護士などの専門家に依頼すべきです。
具体例②について
BさんはY社の代表であり、Y社の売り上げを除外して個人口座に入金しているため、Bさんには業務上横領罪が成立します。
また、そもそも売り上げを除外して申告していますので、過少申告となります。
具体例②の場合には、代表者が横領をしているため、具体例①と違い後述のとおり役員賞与として損金算入ができません。
会社代表者が不法に会社のお金を着服していた場合には、早急に専門家に相談しましょう。
~②に続く~
入居者が賃料にかかる税金を納税しないといけない?
不動産を借りた際に、賃料にかかる税金を借りた側(賃借人)が納税しないといけない場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【問題】
Aさんは、友人のBさんから「海外に1年以上出張することになったから、自分の家を借りないか?」と言われ、月20万円で大阪市北区にあるBさんの家を借りることにしました。
①Aさんが、Bさんの家を自分が住むために借りた場合
②Aさんが、Bさんの家を自分の趣味で集めた品物を保管する倉庫として借りた場合
③Aさんが、Bさんの家をAさんが代表を務める会社の名義で借りた場合
で、Aさんが賃料について納税する必要がある場合はあるか?
【解答】
Bさんが実際に1年以上日本に居住していない場合には、
①の場合には、賃料にかかる税金をAさんは納税する必要はないが、
②及び③の場合には、Aさんは賃料から所得税(及び復興特別所得税)を源泉徴収し、納税する必要がある。
【解説】
非居住者から不動産を借り受けた場合の源泉徴収義務
非居住者や外国法人から日本国内にある不動産を借り受け、日本国内で賃借料を支払う者は、原則としてその支払いの際20.42%の税率により計算した額の所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
そして、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として賃料を支払った(源泉徴収した)月の翌月10日までに納税しなければなりません。(所得税法212条、213条など)
ただし、借主が個人で、借主が自分又は借主の親族の居住用のために賃借する場合には、源泉徴収する必要はありません。
非居住者とは
原則として、日本国内に住所がなく、かつ現在まで引き続いて1年以上日本国内にいない人のことを言います。
ここでいう「住所」とは「生活の本拠となる場所」のことをいうとされていますので、住民票がたとえ日本にあったとしても、1年以上海外で生活している長期出張中の人などは「非居住者」となる可能性があります。
Aさんの場合
①自分が住むために借りた場合
借主であるAさんが自分で住むために借りた場合には、源泉徴収義務がないため、Bさんに賃料を普通に支払えばよいということになります。
②品物の倉庫として借りた場合
Aさんの居住用として借りたわけではないため、AさんはBさんに賃料を支払う際に源泉徴収をする必要があります。
この場合、Aさんは、所得税及び復興特別所得税として賃料の20.42%にあたる4万840円を差し引いた15万9160円をBさんに支払い、さらに4万840円は翌月の10日までに納税する必要があります。
③会社が借り受けた場合
会社(法人)名義で借りた場合は、どのような用途かにかかわらず、借主には所得税などの源泉徴収義務が課せられます。
そのため、②の場合と同様の処理を行う必要があります。
非居住者から不動産を賃借する場合の注意点
非居住者から不動産を賃借する場合には、居住用以外の場合には賃借人が源泉徴収を行ったうえで納税する義務があります。
そして、このことは仲介業者などに告知義務は課せられていません。
そのため、賃貸人が国外にいるのに源泉徴収をせずに普通に賃料を払い続けてしまっており、税務署から滞納通知が届いてから初めてこの制度を知ったという人が多くいます。
また、借りたときには賃貸人が日本に居住していたが、途中から海外に移住してしまったような場合にも、その期間が1年を超えてくると源泉徴収する必要が出てきて、知らない間に税金を滞納しているという場合もあります。
この制度自体に問題があると思われますが、法律がある以上、知らなかったでは納税義務を免れません。
こういったトラブルに合われた方は、賃料を払いすぎていたということにもなるため、賃貸人に払いすぎた分を請求するなどの対応も必要になるでしょうから、税理士だけではなく弁護士にも相談して対応を検討していくべきでしょう。
【裁判例解説】所得税法違反で建設会社従業員に有罪判決
単純無申告ほ脱罪により有罪判決が下された実際の事件を例に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
判決の概要
①事案の概要
大手建設会社に勤務していたAさんが、特定の下請業者を選定する見返りとして、下請業者から2年間で合計1億9500万円の謝礼金を受け取ったのに、その謝礼金及び各年の給与所得について確定申告を行わずに所得税を免れていた。
②判決
懲役1年及び罰金2000万円
懲役刑につき3年間の執行猶予
(求刑:懲役1年及び罰金2500万円)
③量刑の理由
マイナス事情
・ほ脱税額が2年間で合計8300万円を超え、多額
・ほ脱率が通算95%を超える高率
・当初から裏金になるとの認識
・遊興費等に費消
・Aさんが積極的に主導したわけではないが、偽装工作を行って課税を免れようとした
プラス事情
・犯行を認めて反省の弁を述べている
・起訴後に修正申告を行い、ほ脱税額の半分を超える金額の本税を納付
・残りの税額についても納税の意思を示している
・前科前歴がない
解説
①単純無申告ほ脱罪
今回の判決は、令和3年に仙台地方裁判所で実際に下された判決です。
同判決において適用されている法律は、「所得税法238条3項」とされているので、この事件は所得税法違反事件の中でも「単純無申告ほ脱罪」に当たるとして判断がなされたということができます。
「単純無申告ほ脱罪」は平成23年の所得税法改正によって新設された罪で、「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定められています。
全く確定申告をしていないものを無申告といいますが、無申告について所得税法では、「単純無申告ほ脱罪」のほかに、無申告ほ脱罪と単純無申告罪が規定されています。
・無申告ほ脱罪(所得税法238条1項)
「偽りその他不正の行為により(中略)所得税を免れ」た場合の罪で、「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とされています。
・単純無申告罪(所得税法241条)
「正当な理由がなくて(中略)申告書をその提出期限までに提出しなかった者」は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」とされています。
・単純無申告ほ脱罪(所得税法238条3項)
偽りその他不正の行為があったとは言えないまでも、所得税を免れる意思をもって確定申告をしていない場合に当たる犯罪です。
②量刑についての解説
今回の事件では所得の金額が2億円ちかくあり、ほ脱税額も8300万円と非常に高額なため、告発・起訴はおよそ避けられない事件であったといえるでしょう。
また、判決の量刑理由の中で「偽装工作」を行っていたと言われており、「偽りその他不正の行為により所得税を免れた」として無申告ほ脱罪に問われてもおかしくなかったと言えます。
しかし、偽装工作を主導したのはAさんではないといわれていることから、「偽りその他不正の行為」をAさんが行ったとは認定できなかったか、検察官がその立証が難しいとして単純無申告ほ脱罪での起訴を行ったかということだと思います。
判決では「強い非難に値する」とも述べられており、悪質性が高いと裁判所は判断しているということができますが、反省をし修正申告をして実際に納付をしたり納付する意思を示していることが執行猶予を付ける決め手となっているといえます。
罰金については、「この種事犯が経済的にも見合わないものであることを感銘させるため」として罰金刑を併科しています。
ほ脱事件においては、ほとんどの事件で罰金刑が併科されており、罰金額は、ほ脱税額の20~30%くらいの金額となることが多いです。
なお、単純無申告ほ脱罪における罰金刑は所得税法238条3項によれば「500万円以下」とされていますが、同条4項によって「免れた所得税の額が500万円を超えるときは、情状により(中略)その免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる」とされています。
そのため、今回の事件でも500万円を超えて、「2000万円」という罰金刑を課すことができているのです。
③執行猶予を得るためには
今回の事件で執行猶予を得られたのは、反省していることだけではなく、修正申告をして実際に納税をしていることが大きかったといえます。
脱税事件では、納税義務を果たしていないことが非難の対象となるため、修正申告をして納税義務を果たす姿勢を示すことが何よりも大事でしょう。
また、今回の事件では起訴後に修正申告をしているようですが、税務調査の段階から修正申告をして納税義務を果たしていくことで、査察や告発を避けられたり、不起訴を勝ち取れたりといったメリットが生まれます。
脱税事件では、なるべく早い段階から税理士や弁護士などの専門家に依頼し、税務調査や査察、刑事裁判などに向けた活動をしていくことが重要です。
脱税事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談をご利用ください。