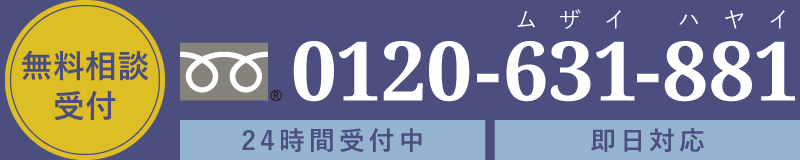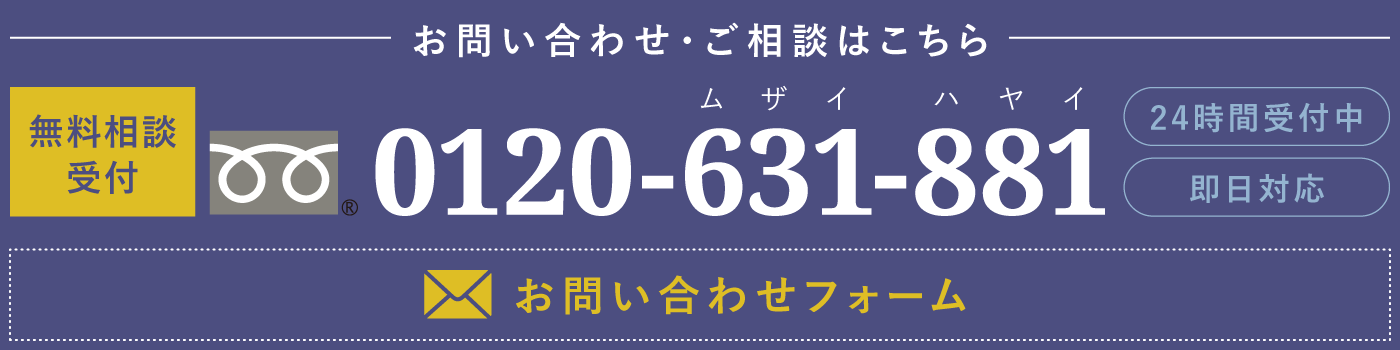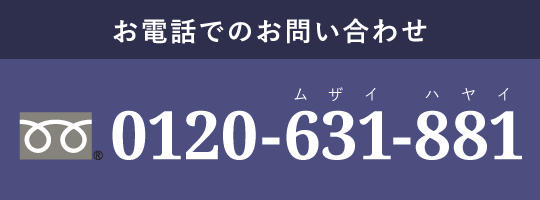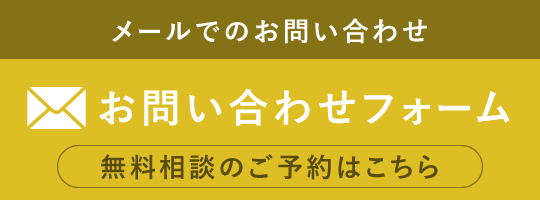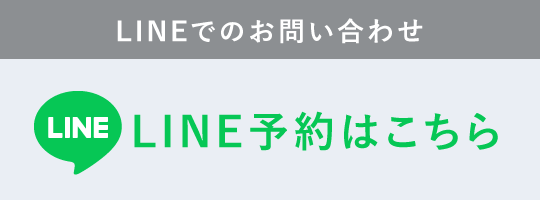Archive for the ‘事件別’ Category
見積額を費用として計上することができるのか

完成工事原価の見積額を費用(損金)として計上した場合における問題について、事例を参考に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
1 事例
大阪府大阪市に本社を置く建設会社X社は、令和4年の確定申告において、令和4年に大阪市と契約をした公共工事(以下、「本件工事」といいます。)の完成工事原価の見積額約1億円を、費用として計上しました。
X社は税務調査を受けることになりましたが、上記のことが不安で、担当者が、弁護士に相談することになりました。
2 完成工事原価の見積額を費用として計上することの可否
完成工事原価とは、請負工事契約に基づく工事の原価を意味し、請負による収益に対応する原価の額には、その請負の目的となった物の完成または役務の履行のために要した材料費、労務費、外注費および経費の額の合計額のほか、その受注または引渡しをするために直接要したすべての費用の額が含まれます。
通常、請負工事を発注する際、事前に、どれくらいの費用(これが完成工事原価)がかかるか見積もりを出します。
その上で、請負契約を締結しますが、実際に、工事が完成するのは、事業年度をまたぐこともあります。
そのような場合、当該事業年度の収益が大きいと、完成工事原価の見積額を費用として計上し、課税対象となる所得を減らせないかということが問題となります。
この点について、最判平成16年10月29日刑集58巻7号697頁は、売上原価等(ここに完成工事原価も含まれます)を構成する費用の額の全部または一部が事業年度終了の日までに確定していない場合、すなわち債務が未確定である場合にも、①近い将来に当該未確定の費用を支出することが相当程度の確実性をもって見込まれており、かつ、②事業年度末日の現況によりその金額を適正に見積もることが可能であったという事情があるときには、収益と対応する売上原価等として損金算入することができるとしました。
仮にそうした事情が認められない場合には、法人税に違反するということになります。
3 税務調査等における弁護活動
X社としては、税務調査において、本件工事について、見積額を費用として計上していることが問題となった場合、まず、そうした見積額を費用として計上することができるか検討する必要があります。
その上で、費用計上できると判断される場合には、①近い将来に、その費用を支出することが相当程度確実であること、②事業年度末日の現況によりその金額を適正に見積もることが可能であったことを説明していくことになります。
具体的には、契約に至った経緯や契約内容、工事の進捗状況等を説明したり、見積もりの算定根拠を、資料に基づき説明していったりすることが考えられます。
一方で、本件工事に関する見積額を費用として計上することが認められないと判断される場合には、早期に修正申告をすることが考えられます。
税務調査などにおける説明や修正申告については、基本的に税理士が行っていくことになりますが、法的な判断が必要になりますので、弁護士のアドバイスのもと、上記のような対応をしていく必要性はあります。
また、その他にも法人税法違反があるなどして、刑事事件化した場合においては、弁護士が対応する必要があります。
その際には、脱税事件や税金関係に強い弁護士のサポートが不可欠ともいえます。
4 最後に
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、脱税事件に強い弁護士が所属し、法人税法違反など多数の事件を取り扱っています。法人税法違反の疑いがあるとして税務調査を受けた方は、初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
収賄罪と課税

収賄した金銭は課税対象となるでしょうか?犯罪行為によって得た利益に対する課税について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。※併せてこちらもご覧ください(業務上横領と課税)
事例
国会議員であるAさんは、職務に関し、長年の友人である個人事業主Bさんから、2000万円の金銭を受け取りました。Aさんは、この金を遊興費等に費消しましたが、賄賂だと思っていたお金なので確定申告はしませんでした。
(フィクションです)
解説
Aさんについては、職務に関して金銭を受けとっていますので、少なくとも単純収賄罪(刑法197条1項前段)が成立します。
収賄した金銭は、所得税の課税対象となるか
収賄した金銭が不法な原因による利得であることは疑いありません。もっとも、この点について、所得税基本通達36-1は、「法第36条1項に規定する『収入金額とすべき金額』又は『総収入金額に算入すべき金額』は、その収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わない」と規定しています。
したがって、本件のAさんが収賄によって得た金銭についても原則として所得税が課税されることになります。
ただ、ここで「原則として」課税されると述べた趣旨は、汚職の罪については、刑法197条の5により、「収受した賄賂はこれを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。」と規定されていますので、本件が刑事事件になっており、近く有罪判決を受け、没収追徴を受ける見込みがある場合には、せっかく課税しても、没収追徴のときに課税を取り消す必要がある関係上、例外的に判決まで課税を保留することが行われることがあるからです。
一時所得か雑所得か
次にAさんが収賄によって得た利益が、「一時所得」なのか「雑所得」なのかが、問題となります。
この点、所得税法34条1項は、一時所得について、「一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的所得から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。」と規定しています。そして、同法35条1項は、雑所得について、「雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。」と規定しています。
そうすると、収賄した金銭は、「職務に対して収受した賄賂」と解されますから、税法上は、役務の対価といえ雑所得として課税されるものと考えられます。
雑所得の場合、課税所得金額は、雑所得の金額-必要経費=雑所得の課税所得金額という計算式で求めます。
本件のAさんの場合、2000万円-0円=2000万円となり、Bさんから受け取った2000万円全額が課税所得金額となります。1800万円を超え4000万円以下の所得税の税率は40%、控除額は279万6000円です。
そのため、Aさんに課税される所得額は、2000万円×0.4-279万6000円=520万4000円となります。
Aさんは今後どうなるか
Aさんは、収賄しているため、このことが警察などの捜査機関に発覚すれば、収賄罪の被疑者として逮捕され取り調べを受けたり、刑事裁判で有罪の判決を受けて前科が付く可能性があります。
このこととは別に、Aさんには収賄によって得た利益について確定申告をしていないので、税金の問題があり、無申告又過少申告についてのペナルティを別途受ける可能性があります。
確定申告期限内に一切の所得について確定申告がなされていなかった場合には無申告加算税、一部だけしか確定申告をしていなかった場合には、過少申告加算税がペナルティとして課されます。
また、仮装隠ぺいなど悪質性が高いと判断された場合には、無申告加算税又は過少申告加算税に代えて重加算税が課せられます。
さらに、納税が遅れると、その期間に応じた「延滞税」の支払いが求められます。
なお、Bさんについては、贈賄罪(刑法198条)が成立しますが、所得税法45条2項には、賄賂として支出した金額は、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されないと明文で規定されており、贈賄を行った者も、前科が付く可能性とともに、税金の問題があることに注意する必要があります。
まとめ
Aさんのように犯罪によって得られた利益も課税対象になりますので、確定申告をしていなければ、収賄の罪とは別に所得税法違反など税法違反の罪にも問われてしまう可能性があります。
そのため、犯罪行為によって利益を得ている場合には、その犯罪だけではなく税金の問題についても考慮しておく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を中心として扱っていますが、税法についても知識のある弁護士がそろっています。
初回の相談は無料ですので、一度ご相談にお越しください。
【ニュース解説】東京国税局がフォートナイト運営企業に税務調査し約35億円の追徴課税

フォートナイトを運営する企業に対し、東京国税局が税務調査を実施し、追徴課税を課したというニュースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ニュースの内容】
東京国税局は,人気ゲームを配信するアメリカノースカロライナ州に本社のある企業で世界各地に40以上のオフィスがある企業に対し,その海外子会社に税務調査を執行した。
その結果,同国税局は,同子会社が2020年12月までの3年間で約30億円の申告漏れをしていたことを発見して指摘した。
申告漏れの内容は,同社の配信するオンラインゲームで,日本人ユーザーが支払った,同ゲームのアイテム購入代金などの一部に係る消費税が計上されていなかったというもの。
追徴税額は,過少申告加算税を含めると,約35億円となるという。
関連ニュース記事(令和5年11月1日付YAHOOニュース「課金収入300億円申告計上せず フォートナイト会社に35億円追徴 東京国税局」)
【フォートナイトとはどんなゲーム】
ゲームは,スマートフォン,パソコン,ゲーム専用端末などどれでもでプレイできる。プレイヤーは,銃を中心とした武器をゲーム内キャラクターに持たせて,これをプレイヤーが操作してゆき,現れてくる敵キャラクターを武器を使って倒すというゲーム。
世界中で数億人のユーザー(プレイヤー)がいるとされている超人気ゲームだ。
この種のオンラインゲームは,キャラクターの能力向上やプレイ時間短縮のため課金されることが多いが,フォートナイトでは,キャラクターやその装備品の見た目を変えるといったゲームのプレイ自体とは直接関係しない品物(アイテム)が主な課金の対象とされているという。
日本には,大人から子供達を含め幅広いファンがいるという。
【課税の対象】
ゲームは,基本的に無料で配信されているが,上記のようにゲーム内で使えるアイテムを購入した際には課金される。
東京国税局は,同社のルクセンブルクにある子会社が,日本に向けて「フォートナイト」を配信して課金していることを把握して税務調査を開始した。その結果,課金収入約300億円について,前記子会社に消費税の申告納税義務があるのに申告に計上されていないとして約30億円の申告漏れを指摘したという。
【親会社のコメント】
親会社は,取材に対し,「日本の税務当局による定期的な調査の中で,弊社側の不注意により一部の消費税が未払いの状態にあることを認識できました。東京国税局の指摘を受けてすでに税の納付をしました。」とコメントした。(関連記事:令和5年11月1日付日本経済新聞「フォートナイト開発元、ゲーム課金巡り消費税35億円追徴」)
【海外の会社まで追及して逃げ得を許さない,国税当局のすごさ】
今回,税務調査により,人気オンラインゲームをめぐりその配信会社に対して,高額の申告漏れを特定するに至った。東京国税局は,海外にいる親会社側の担当者に対し,web会議で面談するなどして効率的に調査を進め,比較的短期間で修正申告に至ったとみられる。
この点について,元国税庁国際業務課のOBによれば「企業のコンプライアンスの重視は,国際的風潮であり,世界的な有名企業であれば,脱税によるイメージダウンは避けたいはずである。税務調査担当者は,その弱みをうまく突き,協力的姿勢を引き出したのではないか。web会議で面談するのも調査手法の新たな向上だ。」と話す。
国税庁は,世界各国の税務当局と租税条約に基づいて情報交換をしており,日本と関係する海外企業の資金の流れについても注視している。ただ,海外企業の税務調査は,地理的遠隔,使用言語の壁といった国内企業に対するそれとは格段の困難を伴う。今回のような数十億円規模の追徴課税は異例であり,国税当局の面目躍如だ。
【今後の動向】
オンラインゲーム,アプリ,音楽の配信などのインターネット上のサービスは急速に拡大している。日本の総務省の情報通信白書によると,モバイル端末向けアプリの売上高は2024年に387億ドルとなる見込みであり,2015年の5倍超になると予想されている。
東京国税局は,2017年海外に拠点を置くゲームアプリの開発・配信業者に着目して消費税を申告していない約数百社をリストアップし,このうち日本での売上高が多いと見込まれる会社に絞って納税義務があることを通知する文書を送付して啓蒙した。しかし,その反応は芳しくなかった。
国は,納税義務を果たさない海外事業者の「逃げ得」を許さないため,2021年度の税制改正でその事業者と取引のあるプラットフォーム運営事業者などを「特定納税管理人」に指定できることを定めた。これは国税当局と納税者間の書類授受を「特定納税管理人」に担わせる仕組みであり,税務調査の端緒を付けたものとして大きい。国税幹部は,「海外当局と連携し,売上高の大きな事業者を中心に粘り強く対応する。」と話しており,税徴収の公正,適正な実現に注力することを明らかにしており,世界規模の自主申告の適正化が図られている。
今後もその動向に注目し,海外事業者のコンプライアンス遵守が実現されることが望まれる。
業務上横領と課税
業務上横領によって得た利益についても課税対象となるでしょうか?犯罪行為によって得た利益に対する課税について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
福岡県福岡市にある会社で経理を担当していたAさんは、会社のために保管していた現金を着服し、1年間で合計4500万円ほど横領していました。
会社の売り上げと決算書の内容に不審な点があることから、会社に福岡国税局資料調査課から税務調査が入り、Aさんの業務上横領が発覚しました。
今後のことが不安になったAさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談を利用することにしました。
(フィクションです)
解説
業務上横領によって得た利益は所得税の課税対象となるか
業務上横領によって得た利益は、違法な行為によって得た利益といえるため、所得と言えるでしょうか。
この点について、所得税基本通達36-1は、「法第36条1項に規定する『収入金額とすべき金額』又は『総収入金額に算入すべき金額』は、その収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わない」と規定しています。
したがって、本件のAさんが業務上横領によって得た利益についても所得として確定申告をする必要があるということになります。
一時所得か雑所得か
次にAさんが業務上横領によって得た利益が、「一時所得」なのか「雑所得」なのかが、税額を計算するベースとなる「課税所得金額」に大きな差がでるため問題となります。
①一時所得の場合
(一時所得の金額-必要経費-特別控除額)×2分の1=一時所得の課税所得金額
という計算式で求めます。
本件のAさんの場合、(4500万-0円-50万)÷2=2225万円となり、2225万円が一時所得の課税所得金額となります。
※一時所得の金額から経費を差し引いた金額が50万円以上の場合、特別控除額は50万円
Aさんに他に収入がない場合には、総所得金額も2225万円となるため、所得税の税率は40%となります。
また、この場合の所得税の控除額は279万6000円です。
そのため、Aさんに課税される所得税は2225万×0.4-279万6000円=610万4000円となります。
②雑所得の場合
雑所得の金額-必要経費=雑所得の課税所得金額
という計算式で求めます。
本件のAさんの場合、4500万-0円=4500万円となり、4500万円が課税所得金額となります。
4000万円を超えている場合の所得税の税率は45%、控除額は479万6000円です。
そのため、Aさんに課税される所得税は4500万×0.45-479万6000円=1545万4000円となります。
このように、一時所得か雑所得かでは、所得税の額に2倍以上の差が出てしまうことになります。
では、本件のAさんの場合には一時所得と雑所得のいずれに当たる可能性が高いでしょうか。
この点について、最高裁は「所得税法上、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得および譲渡所得以外の所得で、営利を目的とする継続的行為から生じた所得は、一時所得ではなく雑所得に区分されるところ、営利を目的とする継続的行為から生じた所得であるか否かは、文理に照らし、行為の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判断するのが相当である」と判示しています(最判平成29年12月15日)。
そのため、一時所得か雑所得かの区別は、ほかの8種類の所得に当たらないことを前提として、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」といえるか否かが主な基準となっているということができるでしょう。
本件のAさんの場合には、1度に4500万円を着服したのであれば、継続的行為とは明らかにいえないので、一時所得に当たるということになるでしょう。
一方、何回かに分けて着服していた場合には、行為の期間や回数、頻度そのほかの態様など判例が示している考慮要素をもとに判断していくことになり、一概にどちらに当たるということは難しいといえます。
一時所得に当たるのか否かについては、このように様々な考慮要素をもとに判断していくことになるため、一度専門家に相談してみるのがよいでしょう。
Aさんは今後どうなるか
Aさんは、会社のお金を業務上横領しているため、会社が警察などの捜査機関に被害届の提出や告訴をすれば、業務上横領の被疑者として取り調べを受けたり、刑事裁判で有罪の判決を受けて前科が付く可能性があります。
業務上横領の金額が多額ですので、会社と示談ができなければ実刑となる可能性が高いといえるでしょう。
一方、会社が被害届の提出など刑事事件化をしなかったとしても、会社から業務上横領によって失われた利益を返還するよう、損害賠償請求をされる可能性もあります。
このような会社との関係とは別に、Aさんは業務上横領によって得た利益について確定申告をしていないはずなので、無申告又過少申告についてのペナルティを別途受ける可能性があります。
確定申告期限内に一切の所得について確定申告がなされていなかった場合には無申告加算税、一部だけしか確定申告をしていなかった場合には、過少申告加算税がペナルティとして課されます。
また、仮装隠ぺいなど悪質性が高いと判断された場合には、無申告加算税又は過少申告加算税に代えて重加算税が課せられます。
さらに、納税が遅れると、その期間に応じた「延滞税」の支払いが求められます。
このほか、Aさんの場合には、税務調査が入っていますが、悪質性が高かったり脱税額が巨額になる場合には、査察調査に発展することもあります。
査察調査は財務調査と違い、強制的に調査をすることができ、最終的には刑事告発に至る場合が少なくありません。実際、査察調査から刑事告発される割合は約70%と言われています。
まとめ
Aさんのように犯罪によって得られた利益も課税対象になりますので、確定申告をしていなければ、業務上横領の罪とは別に所得税法違反など税法違反の罪にも問われてしまう可能性があります。
そのため、犯罪行為によって利益を得ている場合には、その犯罪だけではなく税金の問題についても考慮しておく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を中心として扱っていますが、税法についても知識のある弁護士がそろっています。
初回の相談は無料ですので、一度ご相談にお越しください。
【裁判例解説】「偽りその他不正の行為」を行ったとは認められないとして無罪
「偽りその他不正の行為」を行ったとは認められないとして無罪となった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事案の概要
「夫が死亡したことによって全財産を相続したAが相続税を免れようと企て、相続財産から預貯金、株式等を除外する方法により相続税賦課額を減少させ、過少な金額を記載した内容虚偽の相続税申告書を提出し、もって不正の行為により、正規の相続税額との差額1億4090万円の税を免れた」として相続税法違反で起訴された事件
神戸地方裁判所が平成26年1月17日に宣告した判決では、Aの供述の信用性を肯定し、Aが「偽りその他不正の行為」を行ったとは認められないとして無罪となっています。
なお、同事件では検察官が控訴をし、控訴審ではAの供述の信用性が否定され、Aは逆転有罪となって、懲役1年6月執行猶予3年及び罰金2800万円が言い渡されています。
「偽りその他不正の行為」の意義
神戸地方裁判所の判決によれば、最高裁昭和42年11月8日大法廷判決により示されている「『偽りその他不正の行為』とは、逋脱の意図をもって、その手段として税の賦課徴収を不能もしくは著しく困難ならしめるような何らかの偽計その他の工作をいう」との解釈を引用し、これを本件のような過少申告事案にあてはめると、「(過少申告逋脱罪の成立には、)単に過少申告があったというだけでは足りず、税を不正に免れようとの意図(逋脱の意図)に基づき、その手段として、申告書に記載された課税物件が法令上のそれを満たさないものであると認識しながら、あえて過少な申告を行うことを要し、反対に、行為者が、そのような意図に基づかず、例えば不注意や事実の誤認、法令に関する不知や誤解などの理由によって過少申告を行った場合には、『偽りその他不正の行為』にはあたらないと解するのが相当である。」と述べています。
本判決の意味
逋脱罪が成立するために必要な「偽りその他不正の行為」という要件について、
①税を不正に免れようとの意図(逋脱の意図)
②不法な過少な申告であることの認識
③過少申告の事実
の3つが必要としていると整理することができます。
逋脱罪の成立に関する故意の内容について、①及び②を必要としている点が重要なポイントとなります。
主観的な要素について、未必的な認識では足りず、確定的な認識が必要と考えているということができ、その意味で検察官が逋脱犯の立証をする上でハードルが高くなったといえるでしょう。
逋脱犯の弁護活動
この判決は、控訴審で逆転有罪となっていますが、控訴審では「偽りその他不正の行為」の意義について第一審判決の解釈を否定したわけではなく、Aの供述の信用性を安易に肯定して間違った事実を認定していることが問題視され、Aには確定的故意があったとして有罪となっています。
そのため、故意の内容として「偽りその他不正の行為」の認識がなかったという主張は、それが信用されれば無罪が勝ち取れる可能性があるということです。
供述の信用性の判断には、客観的証拠との一致だけではなく、税務調査や捜査における供述と変遷がないか、一貫しているかという点なども考慮されます。
ですので、調査や捜査の段階でどのように供述していくのかもしっかりと検討して臨む必要があります。
脱税を疑われた場合には、早急に専門家に相談し、適切なアドバイスをもらいましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回相談は無料ですので、ご不安がある方は一度ご相談ください。
【告発事例紹介】国税庁発表の告発事例②
前回に引き続き、国税庁が6月14日に公開した令和4年度査察調査の概要で紹介されている告発事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
国際事案
事例5
E社及びF等は不正加担者と共謀し、同人が日本における代表者を務める外国法人に架空の支払い手数料等を計上する、あるいは暗号資産を取引所で譲渡した取引の主体を外国法人に仮装する方法などで、法人税又は所得税を免れていた。
解説
事例5で、支払い手数料を外国法人に支払ったように仮装した点は、その分を経費として計上することで過少申告となることはわかりやすいと思いますが、暗号資産の譲渡を外国法人が行ったように仮装したことも、本来であれば譲渡利益が発生しているはずなのにその部分を外国法人に割り当てていることにしているため、利益が出ていないとして過少申告をしているということになります。
国税庁は外国法人を利用したこういった国際取引についても重点事案として積極的に取り組んでいるため、国際取引だからといって安易に加担すべきではありません。実際に、この事例では加担者についても告発されています。
その他の社会的波及効果の高い事案
事例6
トレーディングカードゲームの小売を目的とする店舗を全国に展開し、各店舗においてイベントを行っているG社が、取引事実のない虚偽の領収書等を作成して、架空の仕入高を計上する方法により所得を秘匿し、法人税を免れていた。
事例7
Hは、多数の給与所得者を勧誘し、架空の事業所得の損失を計上して給与所得と損益通算することで所得税の還付を受ける不正手段を指南したうえ、内容虚偽の所得税の確定申告書を作成して同給与所得者に交付し、同人らの所得税を免れさせていた。
事例8
大手繊維会社の従業員Iは、下請業者から資金提供を受けていたが、親族が主宰する法人名で架空の請求書を作成し、当該請求書に基づき、下請業者から自身が管理する借名預金口座に資金を振り込ませるなどの方法により所得を隠匿したうえで、所得税の確定申告書を申告期限までに提出せずに多額の所得税を免れていた。
解説
いずれの事例も架空の請求書や領収書を作成して、金銭を支払ったかのように仮装し、実際には金銭(所得)を隠していたという事例です。
隠匿していた所得の額が高額であったり、不正スキームの指南役がいたり、立場を悪用したりといった悪質性が高いといえる事案が告発を受けています。
トレーディングカードについては、一部レアカードが数千万円の値段が付いたり、最近では投資の対象となったりしており、社会的にも注目されている分野であると言えます。
こういった社会的に波及効果が高いと考えられている事案についても、告発を積極的にして公表することで将来の脱税を抑止しようという目的もあるため、注目されている業種の方については、しっかりと確定申告をしていく必要があります。
まとめ
2回に分けて、国税庁が発表した令和4年度査察調査の概要に紹介されている告発事例を見てきました。
告発を受けると刑事事件として刑罰を受ける可能性が出てくるだけでなく、重加算税などの追徴課税も課されることになります。
そのため、査察調査を受けることになった場合には、告発を見据えて早めに専門家に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、脱税に関する相談は無料で行っておりますので、一度ご相談ください。
【告発事例紹介】国税庁発表の告発事例①
令和4年度査察調査の概要が6月14日に公表されましたが、そこで挙げられている告発事例を2回に分けて紹介します。第1回目は消費税事案と無申告事案について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説をします。
消費税不正受還付事案
事例1
日用品の輸出販売や輸出物物品販売場の経営等を行うA社が、取引事実がないにもかかわらず、不正加担者と共謀して、同人が主宰する法人から化粧品等を仕入れたかのように装い、架空の課税仕入れを計上し、当該化粧品等を輸出物品販売場において外国人観光客に販売したかのように装い架空の免税売り上げを計上する方法で、不正に消費税等の還付を受け、または受けようとした。
事例2
B社等数社は、不正指南者から指示されたとおり、B社等各社の代表者からパワーストーンを仕入れたかのように仮装し架空の課税仕入れを計上するスキームを利用して、不正に消費税等の還付を受けようとした。
解説
事例1及び2はいずれも架空の仕入れを計上する形で行われた、消費税の不正受還付事件です。
消費税の還付は免税などで本来であれば支払わなくてよかった消費税を支払っている場合、後から払いすぎた消費税分を返してもらえる制度です。
消費税の還付制度を悪用して不正に利益を得ることは、国庫金の詐取ともいえる悪質性の高い事案として、国税庁が毎年力を入れて調査をしている事案です。
架空の仕入れを計上することは、明らかに脱税意図があると認定される事情となるため、悪質性が高い事案であると言えます。
事例1では一部が、事例2では全部が未遂犯として告発されているようです。
また、事例2では、会社やその代表者だけでなく、指南役も告発されています。
無申告事案
事例3
親族の死亡に伴い多額の財産を他の相続人とともに共同相続したCは、相続財産である現金を複数の場所に隠匿したうえで、相続税の申告書を申告期限までに提出せずに、多額の相続税を免れていた。
事例4
ウェブサイト上で競艇予想情報の販売を行うDが、当該販売収入について所得税の申告義務を認識していたにもかかわらず、確定申告書を提出しないまま法定納期限を徒過させ、所得税を免れていた。
解説
無申告事案とは、本来であれば確定申告書を期限までに提出したうえで納税すべきにも関わらず、申告をしないで納税すべき期限までに納税をしていないという事案です。
国税局や税務署は、様々なところから情報を集めており、たとえば事例3の場合で言えば、亡くなった被相続人の財産についての情報を事前に持っていた可能性があります。その持っていた情報と実際にCさん以外の共同相続人が申告した相続財産の額が大きくかけ離れていることから調査のメスが入れられた可能性があります。
また、インターネットサイトやSNSの情報なども税務署は積極的に集めており、事例4の場合にはそういったインターネットの情報からDさんの収益を割り出していた可能性があります。
このように、国税局や税務署が把握している財産や所得の情報と照らし合わせて税務調査などが行われることになり、うっかり忘れていたのか意図的に申告しなかったのかということを厳しき追及されてしまうことになります。
消費税事案や無申告事案は狙われやすい
消費税事案や無申告事案は毎年国税庁が重点事案として積極的に取り組んでいる事案です。
消費税の還付を不正に受けてしまっていた場合や申告期限までに申告ができていない場合には、早急に税理士や弁護士などの専門家に相談して対応してください。
早めの対応で告発を免れる場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回の相談は無料です。
~国税庁発表の告発事例②に続く~
国税局から告発されたらどうなるの?
国税局から検察庁に告発された場合にどうなるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、自らが代表取締役を務める甲会社の所得約1億3000万円を隠し、法人税約3500万円を脱税したとして、大阪国税局から大阪地方検察庁に告発されてしまいました。(フィクションです)
告発とは
告発とは、犯罪の被害者ではない第三者が捜査機関に犯罪が行われたことを報告し、犯人の処罰を求める意思表示のことです。
似た用語として、被害届の提出や告訴がありますが、被害届の提出や告訴は原則として被害者が行うのに対して、告発は被害者以外の第三者が犯人の処罰を求める点で違いがあります。
脱税事件においては、国税局査察部(いわゆるマルサ)が査察調査を行い、脱税の事実があり、その態様が悪質であったり、脱税額が多かったりした場合には、管轄の地方検察庁に対して告発を行います。
税金は国に対して納めるもので、国税局自体は被害者ではありませんので、被害届の提出や告訴ではなく、脱税した人を処罰してほしい場合には「告発」を行うことになります。
事例のAさんの場合は、大阪国税局が査察調査を行った結果、約1億円以上の所得隠しが発覚しており、悪質性が高いと考えられること、脱税額も3000万円を超えており多額と言えることから、刑事処罰を求めるために告発されたと考えられます。
告発されると
地方検察庁に告発されると、刑事事件としての手続きが始まります。
一般の刑事事件との違いとして、脱税事件の捜査は警察ではなく、検察官が行うことが挙げられます。
告発を受けた検察庁は、検察官が被疑者の取調べを行ったり、追加の証拠収集を行ったりします。
捜査を開始するにあたっては、逮捕される場合もあります。
逮捕されるか否かは、事件内容の軽重、証拠隠滅や逃亡のおそれの有無、共犯者の有無、自白しているか否かなどによって変わってきます。
たとえば、脱税額が巨額で、関係者が多数いる場合などは逮捕される可能性が高いといえます。
逆に、査察調査の段階から脱税の事実を認めて、脱税を指摘された部分についての税金を追徴課税も含めて納税済みである場合などは逮捕されない可能性が高くなります。
事例のAさんの場合には、脱税を指摘された部分について納税を一部でもしていれば逮捕を免れる可能性が高いと考えられます。
そして、捜査の上で、検察官が起訴するか不起訴にするかを決定します。
不起訴となった場合には、罪に問われることはなく、身体拘束を受けていた場合には釈放されます。
一方、起訴された場合には、その後刑事裁判が開かれることになり、身体拘束を受けていた場合には、身体拘束が継続してしまいます。
起訴するか不起訴にするかは、事件内容の軽重、脱税額を事後的にでも納税しているか、前科前歴の有無などによって決まってきます。
なお、脱税事件の起訴率は約70%くらいです。
事例のAさんの場合には、脱税額が多く、所得隠しという悪質性の高い行為を行っていることから起訴される可能性が高いと考えられます。
告発されたらどうすべきか
告発をされた場合には、刑事事件となり、逮捕されたり、起訴されて裁判を受けることになったり、悪い場合では実刑になってしまう場合があります。
そのため、逮捕や起訴、実刑を避けるために、まずは脱税を指摘された部分について納税義務を果たしていくことが重要となります。
その他にも、証拠の隠滅や逃亡をしないことを誓約して、身元の引受人などの監督者を選任するなど逮捕を避けるための準備をするなど逮捕、起訴、裁判の各段階で必要な準備をしておく必要があります。
すべてを抱え込んでしまうと、刑事事件化したことによるストレスや不安で押しつぶされてしまい、十分な準備ができなくなってしまったり、そもそもどういったことをすれば有効なのかわからないといったことも考えられます。
そのため、告発されたら早い段階で専門家である弁護士に相談してアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を中心に扱っている事務所ですので、刑事事件に精通した弁護士が丁寧にアドバイスします。
ぜひ一度ご相談ください。
【事件解説】インフルエンサーに追徴課税
インフルエンサー9人に対して東京国税局が追徴課税をした実際の事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。
事件の概要
「インフルエンサー」の女性9人が東京国税局の税務調査を受け、2021年までの6年間に合計約3億円の申告漏れを指摘された。
東京国税局から,税務調査を受けたのは,インスタグラムやYou Tubeなどでいわゆる「インフルエンサー」と呼ばれる活動をする女性ら9名で,同女性らは,広告主から商品やサービスの宣伝業務を受注すると,広告主の商品である化粧品や美顔器などについて,実際にこれらを使用している写真などをSNS上に投稿するとともに,販売を促進する旨の分かりやすいコメントを載せることにより,同女らのフォロワーらに購入意欲を促進させるなどして売上げにつなげることで,広告主から,そのフォロワー数に応じた報酬を受け取り,多額の利益を上げていた。
同インフルエンサーらは,報酬の全部または一部を確定申告していなかったり,うち1名については,SNSを通じて販売したいわゆる情報商材の売上収入を,海外のペーパーカンパニーの収入と装って所得を隠すなどしていた。
(令和5年3月8日読売新聞オンラインの記事より抜粋)
税務調査
課税庁が,納税者の申告内容に疑問を感じた時に,事後の追徴課税の要否を判断するためなされるのが税務調査です。個人で対象となるのは,個人事業主,フリーランス,ITプログラマー,新規ビジネスモデルのアントレプレナーなど多種多様に及びます。これは憲法に規定された国民の納税義務に基づく課税行政の適正実現のために,所得の生じる事業に対し,過去5年(悪質ケースでは7年)まで遡って(国税通則法72条,73条),事業に関する帳簿書類その他の物件の提示若しくは提出を求め,事業者に対し,事業の収支関係等に関し質問することができるとするものです(同法74条の2)。
このような税務調査がなされれば,税務のプロによる調査からもはや逃れることはできないでしょう。
今回は,人気女性インフルエンサー9名に対し,東京国税局が税務調査をした結果,2021年までの6年間に計約3億円の所得申告漏れが判明しました。
インフルエンサーは狙われている
SNS上のインフルエンサーによる広告は,拡大を続けており,市場調査会社であるSNSマーケティング会社によると,2021年は前年の2倍以上のおよそ741億円の市場規模であり,予測によると,これが2027年には1302億円に上ると推計されています。
インフルエンサーはほとんどが個人で行ってることから、個人事業主ということになります。
企業とタイアップしたりスポンサード契約を結んだりしている場合もありますが、その場合でも個人事業主として扱われる場合がほとんどです。
今回の事件のように、広告によって得た収入は事業所得となり、所得税の確定申告が必要になります。
インフルエンサーの市場規模が年々拡大を続けている現状から、インフルエンサーは、国税局や税務署が特に注目している事業分野だといえます。
特にYouTubeやInstagramなどでは、フォロワー数が表示され、どれくらいの広告収入を得ているかが推測されやすく、税務調査に入りやすいといえるでしょう。
追徴課税
今回の事件では、インフルエンサー9人に対して、百数十万から約3000万円が追徴課税され、追徴税額は合計約8500万円に上るということです。
追徴課税とは、本来納めるべきであった税(本税)に加えて、無申告や過少申告に対するペナルティとしての加算税を加えたものです。
今回の事件では、報酬の一部を申告していなかった人には、過少申告加算税が、報酬の全部を申告していなかった人には無申告加算税が追加で徴収されていることになります。
また、今回の事件のうち1名のインフルエンサーは海外のペーパーカンパニーの収入と偽っていたとのことですが、これは悪質性の高い隠匿行為と評価される可能性があります。
悪質性が高い隠匿行為とされると、無申告加算税や過少申告加算税よりも加算される税額が重くなる重加算税が課せられる可能性もあります。
本来納めるべき税額に加えて、加算税が課せられますので、きちんと確定申告をして納税していれば課せられなかった多額の税金を追加で納めなければならなくなってしまいます。
税務署の税務調査より前に修正申告を行うことによって、こういった加算税を課せられることを防ぐことができますので、申告漏れに気づいた場合には、早めに専門家に相談して対処しましょう。
まとめ
今回の事件ではインフルエンサーに対する追徴課税がなされたという報道でしたが、うち1名については、悪質性の高い隠匿行為をしているとして重加算税の対象になる可能性があるだけでなく、刑事告発を受けて刑事罰を科せられる可能性もあります。
インフルエンサーはその社会的影響力から、税務署も目を光らせていますので、確定申告の内容に不安があったり、申告漏れが疑われてしまった場合には、早急に税理士や弁護士などの専門家に相談しましょう。
本記事を解説してくれた河田弁護士は「国民主権の下,国の存立を図るためには,国民一人一人が,その能力に応じて納税義務を履行し,国の財政を支えなければならないの当然となります。天網恢恢疎にして漏らさずのとおり,不正な申告や所得隠しはいずれ発覚することになりましょう。そうなれば,本来の税額に加えペナルティとして加算税の追徴を受けるなど金銭的に少なからずの損失を被ることになります。誰しも納税には負担を感じるものです。しかし,納税することが国の存立に寄与すると思えば,気持ちも変わるはずです。くれぐれも適正申告に務めたいものです。」と語っています。
【事件解説】所得税不正還付指南で刑事告発
所得税の還付を不正に受ける方法を指南したとして刑事告発された実際の事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。
事件の概要
「納めすぎた税金を取り戻そう」と全国の会社員にSNSで呼びかけ、不正な還付申告による脱税の手口を指南していたとして、東京国税局査察部が、東京都新宿区のコンサルタント会社の代表者Aを所得税法違反の疑いで東京地検に告発した。
Aは、東京や埼玉、愛知、岐阜、大阪、兵庫、福岡、熊本など19都府県の会社員ら109人に、架空の副業で計約7億2900万円の損失を出したように装わせ、計約4300万円分の所得税の還付を不正に申告させた疑いが持たれている。
(令和5年3月1日、朝日新聞DIGITALの記事から抜粋)
所得税の還付
会社員の方などは、給与から所得税が源泉徴収されています。
この源泉徴収をされた所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納めすぎた所得税の返還を受けることができます。このことを所得税の還付といい、還付を受けるための申告を還付申告と言います。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
会社員の方の場合には、給与から所得税が源泉徴収されているため、基本的には所得税の確定申告をする必要はありません。
しかし、副業をしている方で、その副業で損失を出してしまった場合には、その損失部分を所得から差し引くことができるため、損失部分を含めて確定申告をすることで、納めすぎた所得税の還付を受けることができるのです。
刑事手続
Aさんは、所得税法違反で刑事告発を受けています。
刑事告発を受けた検察庁は、Aさんを被疑者として取り調べ、その後起訴することになります。
査察部から刑事告発をする場合には、事前に査察部と検察庁で協議を行い、告発をするかどうかを決定することがほとんどです。
そのため、刑事告発されると7割を超える確率で起訴まで至っています。
起訴されると、公開の法廷で裁判が開かれます。
今回のAさんの場合、架空の副業で損失が出たように装って還付申告をすることを指南していたということなので、「偽りの方法により所得税の還付を受けた」ということになり、所得税法238条1項の罪に該当すると思われます。
同条で規定されている法定刑は、「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれの併科」です。罰金については、情状によって、還付を受けた所得税の額に相当する金額以下まで科すことができます(同条2項)。
Aさんの場合には、脱税を指南していたという立場になるため、実際に不正に還付申告をした人たちとの共犯関係にあるということになりますが、申告書作成の手数料を受領したりもしていたようなので、共謀共同正犯として処罰されることになるでしょう。
実際に不正に還付を受けた会社員の方たちは、国税局から所得隠しを指摘されて、大半が重加算税を含む追徴課税を受け、修正申告と納税に応じているということですので、Aさんに対する判決については、執行猶予が付く可能性が十分にあると考えられます。
しかし、かなり多数の人に対して脱税を指南していたこと、受け取っていた手数料の総額が高額なことなど悪質性が高い事案であるともいえます。
そのため、執行猶予が付かず、実刑判決を受けてしまう可能性もあります。
また、罰金の併科も受けることになると考えられ、不正に還付を受けた金額が約4300万円ということからすれば、1000万円近くの罰金も併科される可能性が高いです。
まとめ
今回は、実際報道されている事件をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の末吉弁護士に解説をしてもらいました。
末吉弁護士は、「所得税の不正還付については、国庫に対する詐欺のようなものなので、国税局も本腰を入れて調査しますし、告発もされやすい部類に当たるといえます。そのため、もし不正還付に加担してしまったという場合には、早急に弁護士に相談して告発をさけるための活動をしていくべきでしょう」と語ってくれました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、脱税に関する相談を無料で承っていますので、早急にお問い合わせください。